 |
| 背中や腕の皮膚がケロイドになった女性(10月、米軍撮影) |
ケロイド(熱傷はん痕)
1946年初めごろから、いったん治ったと思われていた熱傷の跡の皮膚や肉が盛り上がって、ケロイドが生じたり、皮膚がひきつる症状が現れてきました。ケロイドの発生は、爆心地から2キロ前後までの地域で熱線の直射で熱傷を負った人の50〜60%にも達しました。これは放射線の影響であったと考えられています。
やけどをした跡の肉が盛り上がったり、皮膚がひきつる症状は、人々の心にも深い傷を刻みました。顔にケロイドがある人はいっそう苦しみました。背中や肩にできた人も肌を露出するのをためらい、広島では、夏でも長そでのシャツを着て過ごした人々が大勢ありました。
 |
| 背中や腕の皮膚がケロイドになった女性(10月、米軍撮影) |
白血病は血液の工場である骨髄が、何らかの原因で白血球を無限に作り出してしまう病気です。血液中の白血球の若い段階の細胞がとどまるところなく増殖して正常な機能を失い、病気の感染に対する抵抗力を低下させます。
原爆で被爆していない人でもかかる病気ですが、広島や長崎では近距離で被爆した若い年齢層の人に多発し、放射線による血液の後障害と考えられるようになりました。
1950年代に多く発生し、代表的な原爆症として人々に不安を与えました。後に広島市平和記念公園に「原爆の子の像」が建てられるきっかけになった佐々木禎子さんは幟町中学一年生だった1955年10月25日、亜急性骨髄性白血病のため、広島赤十字病院で亡くなっています。
 |
| 佐々木禎子さん(上)と病床で自ら血球数を書きとめた半紙 |
被爆翌年の1946年になると、比較的近い距離で被爆した母親から、頭の小さな子供が生まれました。子供たちが大きくなるにつれ、知能の遅れるケースがあることも分かりました。こうした症状を「原爆小頭症」と言います。
母親が受胎して8〜25週(大部分は8〜15週)の、胎児の細胞が最も放射線の影響を受けやすい時期に被爆した場合に、こうした悲劇が起きました。1946年5月31日までの間に生まれた、爆心地から2キロ以内の胎内被爆者は約 1,100人と推定されています。
がん(悪性腫瘍)
白血病の発生ひん度が落ち着いてきた1960年ころからは、甲状腺がん、乳がん、肺がん、唾液腺腫瘍(だえきせんしゅよう)などの発生率が高くなり始めました。
放射線は発がんの因子として重要な意味を持ち、被爆距離や被爆放射線量と発生率との間に関係があると認められるがんの報告もされています。現在、放射線との関係が認められているがんの中でも、甲状腺がんのように1955〜65年に増え始めたものや、結腸がん、骨髄腫のように、比較的最近になって目立ち始めたものもあります。被爆した時の年齢が若いほど、がんになりやすいとされています。
原爆白内障
目の水晶体が濁って、視力が低くなるのがこの病気です。広島では1948年秋、長崎では49年6月に 確認されました。老人性の白内障とは異なり、放射線によるものです。原爆白内障が発生するひん度 と水晶体が濁る程度は被爆した線量と関係し、近距離で被爆するほど発生ひん度が高いとされています。
「人を長く、元気で生かすのが医者。原爆に遭った人も同じです。被爆者に特有の病気があるなら、原因を調べ、苦痛をやわらげること。1日でも長く生きてもらって、家族のために、平和のためになることをしてもらいたい」。それが重藤さんの人々に残した言葉でした。
被爆後の「原爆医療」を支えたヒロシマの医師たちは、被爆者を「生かす」ことに心をこめたのでした。広島に投下された原爆で亡くなった医師は 225人に上ると言われます。医師もまた被爆者でした。被爆直後から被爆者の病変を調べた東京大学の都築正男教授ら全国の医学研究者と広島の開業医が協力して、被爆者のための医療活動が行われました。
その中で、原爆後障害の研究会ができ、健康管理のセンターができ、調査・研究のための機関、治療の中心になる専門病院ができ、施設や医療器具が整っていったのです。そして今、ヒロシマの医療・研究機関は原爆医療の経験を、被爆者のためだけでなく、核兵器開発や原発事故など新たに世界で生まれているヒバクシャの医療にも役立てる活動を始めています。
●街のヒロシマ医師
被爆10年前後で被爆者のがん死亡率が高いことを突き止めたのは、内科医の於保源作(おほ・げんさく)さんでした。戦後、疎開先から広島に戻り、全焼を免れた自宅で内科医院を再開。街にあふれる被爆者の診察を始めました。その過程で被爆者に白血病や胃がんなどで亡くなる患者が多いのに気付き、1951〜1955年に広島市が受け付けた死亡診断書11,400枚をチェック。被爆者のがん死が全国の平均を上回っていることを統計的に突き止め、1956年に医学専門誌に発表しました。
於保さんと同じ志を持つ内科や外科の医師たちは早くから研究会を開き、情報を交換、被爆者の治療対策を進める原動力になりました。
●広島原爆障害対策協議会
被爆者の医療を組織的に進めるため、広島市と医師会が協力して1953年1月に「広島市原爆障害者治療対策協議会」ができました。略称は「原対協」。被爆者の合同診察を開始し、実態調査を進めました。1955年には原爆のケロイドが残る女性たちの渡米治療に協力しました。1956年に財団法人となり、現在の名称になりました。被爆者のための「健康管理・増進センター」は現在、中区千田町3丁目8−6の市総合健康センターの中にあり、被爆者検診などを実施しています。
●放射線影響研究所
広島市南区比治山公園のかまぼこ型の建物で、略称「放影研」。前身はABCC(原爆傷害調査委員会)で、米国が原爆調査のため1947年に医学調査を開始。48年に広島、長崎の研究所に日本側の研究組織ができました。今の建物は50年に完成。被爆者12万人を抽出した寿命に関する疫学調査、うち2万人の成人健康調査などを続けています。
ABCCには「調査しても治療しない」など被爆者の批判がでました。75年に日米共同運営の財団法人に移行、現在の名称になりました。放影研の長期間の被爆者とその健康に関するデータは貴重なものです。しかし、運営をめぐっては市内への移転問題、米国側の体制変更などについて日米間の協議が続いています。
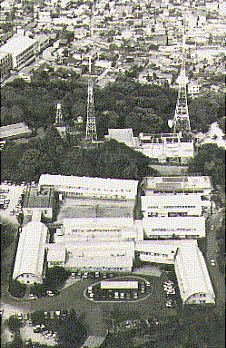 |
| 比治山公園の放射線影響研究所(旧ABCC) |
1961年に原爆医療研究のため、南区霞1丁目2−3に開設されました。略称「原医研」。障害基礎研究、病理学研究、血液学研究など10部門があり、後障害だけでなく、被爆者の社会的調査も含めた原爆医療の研究をしてきました。最近は旧ソ連チェルノブイリ原発事故の被害者救援など国際的な医療協力を放影研とともに進めています。
●広島赤十字・原爆病院
被爆直後の救援活動や後障害の治療を通じ、被爆者が最も頼りにしてきた病院です。お年玉付き年賀はがき収益金で、1956年に中区千田町1丁目9−6の広島赤十字病院に併設して原爆病院ができました。88年に両病院が合併、原爆病院はその原爆医療部門になっています。
56年〜93年度末で約8万人が受信。93年度の一日平均入院患者は内科77人、外科36人。開院から38年間に死亡した入院患者は 2,584人。死因は胃がん、肺がん、肝がんの順で白血病は 109人です。
【世界のヒバクシャへの医療協力】
被爆者だけでなく、世界には原発事故や核兵器製造・核実験などによる放射線被曝(ばく)者がいます。健康被害に悩むこれらの人々を救援するため、1991年に「放射線被曝者医療国際協力推進協議会」(略称「放医協」)ができました。広島県、広島市、医師会、原医研、放影研、原対協、広島赤十字・原爆病院などが参加。原爆医療の経験を生かし、放射線に被曝した患者、研修のための医師や研究者の受け入れなどが行われています。
―あの日を語り伝えて―実に大勢の人々が、原爆の恐ろしさを伝える努力をしてきました。被爆者自身の証言、新聞の報道や記録写真、ラジオやテレビの放送、小説やルポルタージュ、童話などの文学、絵画や彫刻などの美術、映画やアニメーションなどの映像芸術、演劇、音楽、舞踊などの舞台芸術…。国際的に評価を受けた芸術活動もあれば、ヒロシマの子供たちの手記、体験を受け継ごうとする高校生による演劇活動もあります。各界各層の人が、次の時代を担う若い人と世界の人々に向かって、「ヒロシマ、ナガサキの体験を直視しよう」と呼びかけ、核兵器の被害についてできるだけ深い理解を求めようとしたのです。
|
沈黙と叫びと
被爆直後、被爆者たちの間に「あの残酷な光景は到底、言い尽くせない」という思いが強くありました。現実はそれほど悲惨でした。その中でも原民喜さんの小説『夏の花』(1947年)などの作品が生まれました。
しかし、時とともに「事実を伝えてこそ世界の人が核兵器の恐怖と愚かさを知り、次の時代に平和を築くことになる」と考えられるようになりました。『原爆の子―広島の少年少女のうったえ』(1951年長田新編)、「にんげんをかえせ」と訴えた序で知られる峠三吉さんの『原爆詩集』(1951年)などが作られました。
早くからヒロシマに心を寄せた大江健三郎さんは『ヒロシマ・ノート』(1965年)を、井伏鱒二さんはベトナム戦争の中で小説『黒い雨』(1966年)を書き、人々の体験から深い意味をくみ取って次の世代に伝えました。
絵画では丸木位里、俊さんが『原爆の図』シリーズ第1作(1950年)、平山郁夫さんが炎に包まれた街を『原爆生変図』(1974年)に描きました。映画も新藤兼人監督が『原爆の子』(1952年)、今村昌平監督が『黒い雨』(1989年)を作りました。目で見た原爆の記録はNHKが募集した被爆者の絵(1974年)、「原爆」を撮った人たちの写真集(1987年)もあります。
ジョン・ハーシーさんの『ヒロシマ』(1946年)など外国のジャーナリストや学者たちの活動もありました。被爆者の手記も各地の被爆者団体の手記集などを通じなお収録が続いています。そのすべてが、被爆の体験を、核時代を生きる人類の共通の経験にしていくための営みです。
