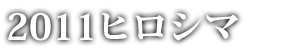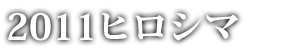今年の平和宣言をめぐる松井一実広島市長との一問一答は次の通り。(論説委員・江種則貴)
―被爆体験を盛り込むことで、訴求力のある平和宣言となりそうですか。
自分自身が悲惨な目に遭いながら、より大変な人を救えず、後ろ髪を引かれる思いで逃げるしかなかった。そんな体験が寄せられ、読んで「ずきっ」と感じた。
それが核爆弾だ。市民の日常を奪い、平和を崩した。むごい兵器だということをまず分かってもらいたいし、その意図は十分に伝わるだろう。自分としては得心しながら宣言文を仕上げている。
―今後も体験の継承や発信を平和行政の軸とする考えですか。
証言者が少なくなる時代。被爆体験の共有こそが原爆を否定する思いにつながる。そうした思いを集めるのが市の役割だ。原点にこだわり続ける。
―原爆を投下し、先頃も臨界前核実験を繰り返した米国などの核保有国に何を訴えますか。
平和を願う私たちと同じ価値観の人は米国にも少なくない。だが国家全体の意思となるとギャップが出る。そこはいかんともしがたいのだが、国家に対しては強く「核を持つな」と言いたい。
原爆を落とした米国を憎むという発想だけでは(世界平和の実現は)難しいだろう。ただ各国の為政者には、その国の民意が投影されるはずだ。その良心、人間性に期待し、広島に来てもらって原爆被害を理解してもらう。核兵器廃絶や世界平和の訴えを聞いてもらう。それが私の言う「迎える平和」だ。
各国のリーダーが広島に集まる国際会議の開催を提唱したい。
―被爆者援護策についての訴えは。
在外被爆者も含め、高齢化が進んでいる。援護の充実を日本政府に求め続けるのが市の立場であり、市民の立場も同じだろう。
「黒い雨」に遭い、被爆者と変わらない状況の人にも援護が必要だ。しかも急いでもらわないと。きちんと宣言に盛り込んでいく。
【写真説明】「国際会議の被爆地開催を提唱したい」と話す松井市長