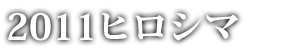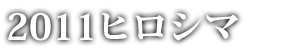▽失われた暮らし 伝える
平和記念公園(広島市中区)の芝生広場東の木立に、ひっそりと立つ高さ約70センチの自然石。爆心地から約400メートル。「材木町跡」と刻むその文字が、原子爆弾さく裂の間際まであった暮らしの証しだ。
軒を連ねる食料品店や茶店、石材店、トンボの飛ぶ池…。当時、中島国民学校6年で疎開していた理容店経営木曽真隆さん(77)=南区=は「活気ある町だった」と振り返る。
中国新聞社が2000年に調べたところ、1945年8月6日の材木町の居住者で確認できたのは154世帯474人。その日のうちに330人が亡くなったとみられる。
戦後の公園建設に伴い、生き延びた住民も移転を余儀なくされた。碑は57年、旧住民が犠牲者の冥福を祈り、故郷に思いをはせて建てたという。

灰じんに帰した広島は今、津波や原発事故で生活を奪われた東北の地と重なる。「誰にも同じ思いをしてほしくない」と木曽さん。風雨に耐えた樹木のように傾く碑。家族の記憶を静かに伝える。(写真・宮原滋、文・馬上稔子)
動画はこちら
【写真説明】平和記念公園内の通路脇に立つ材木町跡碑。壊滅した町への思いが消えることはない