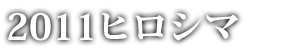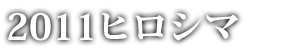福島第1原発事故を受け、原発の問題にどう言及するか注目が集まる今年の平和宣言。だが、核兵器の非道を告発し続けた平和宣言はこれまで原子力の平和利用に伴う問題はほとんど触れてこなかった。
1947年の第1回平和祭以降、平和宣言に「原子力」「原発」という言葉が登場したのは計10回。多くは核兵器の悲惨さを訴えると同時に、非軍事目的の核利用は科学技術の進歩として歓迎した。
56年5月、被爆地の反核感情を和らげ、原発導入の地ならしとされる「原子力平和利用博覧会」を日米両政府の強い支援で広島県、広島市などが開いた。渡辺忠雄市長はその夏の平和宣言で核兵器の脅威や被爆の悲劇を訴えたが、「原子力の解放が一方において人類に無限に豊かな生活を約束する」との認識も示す。
史上最悪のチェルノブイリ原発事故が起きた86年、荒木武市長は「(事故が)人々を放射能の恐怖に陥れ、世界は核時代の現実にりつ然とした」と指摘した。ただ、原発の是非やエネルギー政策の在り方には踏み込まなかった。ほかにも社会を大きく揺るがした東海村臨界事故(99年)や米国のスリーマイルアイランド原発事故(79年)は平和宣言で触れられてもいない。
91年、就任1年目の平岡敬市長は「これ以上ヒバクシャを増やしてはならない」と宣言した。核兵器だけでなく、原発事故など核被害者を広く救済するため、放射線被曝(ひばく)者医療国際協力推進協議会(HICARE)を県などと設立した。
主張の柱はヒロシマの蓄積を生かした国際貢献。ただ、この時も原子力の平和利用の問題とは距離を置いた。
市長在任の8年間、平和宣言の起草に心血を注いだ平岡さんは「自分も広島も核兵器にばかり注目し、平和利用の問題と向き合ってこなかった」。福島第1原発事故で放射線への不安が広がる中、「平和や命を脅かす今起きている問題に発言せずして平和宣言は説得力を持たない」と語る。