米ニューヨークの国連本部で五月二日に始まる核拡散防止条約(NPT)再検討会議は、論議が決裂するとの悲観的な見方がある。核兵器廃絶への「明確な約束」の実現を求める非核兵器保有国と、核の拡散防止に照準を絞り核軍縮には後ろ向きの米国との対立が必至の情勢だからだ。一定の役割を果たしながら、限界も指摘されるNPT体制は今、重大な岐路にさしかかった。核軍縮は進むか―。世界の核状況と再検討会議の課題を展望する。
(宮崎智三)
■米が逆行 合意至難/2020ビジョン 支持集めるか
|
核兵器をめぐる世界の現状
|
|---|
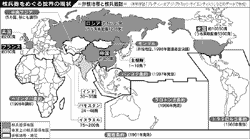
|
|
画像をクリックしてください。拡大します。
|
「核の時代」と呼ばれた二十世紀の最後の年に開かれた前回(二〇〇〇年)の会議は、核兵器廃絶への「明確な約束」を全会一致で決めた。ブラジルやメキシコなど「新アジェンダ連合」の七カ国を中心に非核兵器保有国が結束し、米国をはじめとする保有国を包囲して勝ち取った歴史的な成果だった。
テロで状況一変
しかし、〇一年九月の米中枢同時テロが状況を一変させた。米国はテロを封じ込める名目で、小型核兵器の開発に走り、核実験の再開をうかがうなど、核軍縮とは真反対の軍拡へと動く。今回の再検討会議でも、核軍縮には冷淡で拡散防止を重視する姿勢を取るとみられている。
そうした流れを受け、核軍縮面では限定的な成果さえ危うい、と悲観的な見方がある。前回の「明確な約束」の再確認▽包括的核実験禁止条約(CTBT)の早期発効と、発効までの核実験停止▽兵器用核分裂物質生産禁止(カットオフ)条約の交渉即時開始―などで合意できるかどうかが焦点だ。
平和市長会議(会長・秋葉忠利広島市長)が提唱し、世界の非政府組織(NGO)などからの賛同が相次ぐ「2020ビジョン」は、二〇二〇年までの核兵器廃絶をめざす。期限を切った廃絶の提起に、再検討会議がどう反応するか。CTBTの発効促進に力点を置く被爆国日本の言動も注目される。
そもそもNPTをめぐる議論は常に、条約の不平等性が影を落としてきた。米国、ロシア(旧ソ連)、英国、フランス、中国の五カ国だけに核兵器の保有を認め、他国の保有は禁じているからだ。この点を強く批判するインドやパキスタン、イスラエルの三カ国は今もNPTに加盟していない。いずれも事実上の核兵器保有国だ。
ただ、NPTは第六条で核兵器国の核軍縮を義務付けている。非保有国の訴えは、ここに立脚する。前回の「明確な約束」は、保有国の都合で先延ばしされかねない「究極的な廃絶」を否定し、六条の確実な履行を強く迫る内容とも言える。
| NPT再検討会議の主な争点 |
|---|
【核軍縮】
- 核保有国による一層の核軍縮努力
- 包括的核実験禁止条約(CTBT)早期発効または核実験凍結継続
- 兵器用分裂物質生産禁止(カットオフ)条約交渉の早期開始
|
【核拡散防止】
- NPT脱退規定の厳格化
- ウラン濃縮・再処理の制限
- 核拡散防止構想(PSI)強化
- 核物質の輸出管理強化
|
広がる非核地帯
一九九六年の「核兵器の使用と威嚇は一般的に国際法に違反する」とした国際司法裁判所(ICJ)の勧告も、六条については核軍縮交渉を誠実に行うだけではなく、完成する義務もあると解釈し、その「成果」を求めた。
核兵器を排除する「非核の傘」で地域の安全を確保する非核地帯は、既に南半球を覆った。中央アジアなど北半球にも広がろうとしている。
平和市長会議やNGOのロビー活動も含め、非保有国陣営がきっちり手を結び、前回と同様に米国をはじめとする保有国を包囲できるかどうか。核軍縮面での焦点はここに尽きる。
■新たな脅威次々/抜け穴どう封じる
核の拡散面でも、この五年間の変化は激しい。NPT脱退や核兵器製造・保有を宣言した北朝鮮、ウラン濃縮やプルトニウム分離を含む活動を国際原子力機関(IAEA)に申告せずに繰り返していたイラン、核技術や関連部品が簡単に入手できる「核の闇市場」…。
拡散防止に逆行するこうした新たな動きは、天野之弥外務省軍縮不拡散・科学部長が「今までなかった新しい現象が次々に出てきている」と評するほど厳しい状況だ。こうした脅威に歯止めがかけられるのかも、再検討会議の焦点となりそう。
例えば、原子力の平和利用をNPTは「奪い得ない権利」とする。しかし、それを隠れみのにした核兵器開発や、核技術獲得後に容易にNPTから脱退できる「抜け穴」にどう対応するか。脱退に制裁的措置を課す方策も話し合われる見通しだ。
ブッシュ米大統領は昨年、日米欧各国による大量破壊兵器の拡散防止構想(PSI)の拡大や、非核保有国の核燃料生産規制などを提案した。今回の会議でも米国は、拡散防止策を強く主張する考えだ。
そのために米国は、核軍縮面で譲歩するのかどうか。最大の核超大国は、前回の核兵器廃絶の「明確な約束」を死文化する構えとも伝えられる。そうした非保有国との対決姿勢を崩さなければ、会議は最終文書を採択しないまま幕を閉じるだろうとの見方もある。拡散防止の論議は、核軍縮の行方とも密接に絡み合う。
このページのTOP
| キーワード |
|
兵器用核分裂物質生産禁止条約(カットオフ条約=FMCT) 核弾頭の原料となる高濃縮ウランやプルトニウムなど兵器用核分裂物質の生産禁止が目的。核兵器製造の道を閉ざすことで、新たな核兵器保有国の出現を防ぎ、保有国の核兵器生産も制限する効果がある。ミサイル防衛構想や宇宙への軍拡に絡んだ米国と中国による長年の対立などにより、交渉は始まっていない。
|
|
拡散防止構想(PSI) 北朝鮮やイラン、あるいはテロリストを念頭に、大量破壊兵器やミサイル関連技術の拡散を阻止する新たな取り組みとして、米国が2003年に提唱した。疑わしい貨物を積んだ船舶や飛行機に対する海上などでの臨検が主な内容。日本をはじめ主要8カ国(G8)などが参加し、共同訓練も始まっている。核の平和利用を阻害するとの反発もある。
|
|
非核地帯 国際条約などで核兵器の開発や、生産、取得、保有、管理を禁止した地域。一般的に核兵器保有国は、地域内の国家に対する核攻撃や威嚇をしないと誓約する議定書を締結する。中南米、南太平洋、アフリカ、東南アジアの4地域が条約化に成功。中央アジア5カ国も今秋には条約に調印する見込みだ。南極も、南極条約で核兵器などの配備が禁止されており、非核地帯の一つとみなされている。
|
|
北朝鮮の核問題 1980年代から北朝鮮は核開発を本格化させたとされる。米国との間で94年に「枠組み合意」がなされ、主な核施設は凍結されたが、2002年にウラン濃縮型核開発計画が表面化。北朝鮮は03年、NPT脱退を宣言した。問題解決に向け韓国、中国、ロシア、日本を加えた6カ国協議が3回開かれたが、北朝鮮は今年2月、協議参加の無期限中断と、核兵器の製造・保有を初めて公式宣言した。
|
|
イランの核開発疑惑 2002年、イランが核兵器開発計画を進めているとの疑惑が浮上。国際原子力機関(IAEA)に申告せずにウラン濃縮やプルトニウム分離を含む原子力活動を長期間繰り返していたことが判明し、疑惑は深まった。イランは「すべての活動は平和目的」と主張しつつ、査察強化につながるIAEAの追加議定書に署名するなど前向きな対応も見せるが、米国などは強い懸念を示している。
|
|
「核の闇市場」 パキスタンの「核開発の父」と呼ばれるカーン博士らが構築した、核物質や核関連機材を不正に取引する国際ネットワーク。国際原子力機関(IAEA)の調査では、欧州や中東、北朝鮮を含むアジアに広がり、少なくとも30以上の国と、その国の企業が取引にかかわっていたという。
|
|
包括的核実験禁止条約(CTBT) 従来の部分的核実験禁止条約が禁止対象にしていない地下核実験を含めて、爆発を伴うあらゆる核実験を禁止する。1996年の国連総会で採択され、既に120カ国が批准した。発効には、研究・発電用の原子炉を持つ44カ国(発効要件国)の批准が必要。うち未署名のインド、パキスタン、北朝鮮を含め、米国、中国など11カ国が批准していないため、発効の見通しは立っていない。
|
|NPT再検討会議TOP|