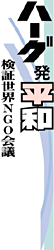反核思想どう肉付け 海外と積極的連帯必要 ラップ音楽風にアレンジした大阪・河内音頭に合わせ、浴衣姿の日本の若者たちが飛び跳ねながら踊る。歌詞は、日本の平和憲法の理念をアピールする内容。珍妙な取り合わせだが、結構受けた。小気味良いリズム感に海外の若者たちが集まり、体を揺らす。 ▼被爆者の証言埋没
世界から八千人の市民が集った「ハーグ平和アピール1999」に、日本からは約二十人の被爆者を含め四百人以上が参加した。連日、被爆体験を証言し、ブースには原爆の惨禍を伝える写真パネルを並べた。そうした取り組みも、若者たちの踊りも、日本の参加者がハーグで共通して訴えたのは、武力や暴力の完全否定であり、その思想の原点であるヒロシマだった。 だが、証言の集いにしても、五、六十人収容の小部屋が割り当てられ、訪れる外国人は少なかった。十人ほどの日もあった。コソボ危機が話題を集めた会議の約四百に上る分科会のなかで、被爆者の証言が埋没したのは否めない。 世界の平和運動にとって、ヒロシマの存在は薄らいでしまったのか。広島市の秋葉忠利市長が指摘したように、原爆投下は二十世紀最大の悲劇であり、その戦争の世紀を振り返る会議でありながら、開会式の壇上に招待された被爆者はいなかった。閉会式でスピーチした唯一の日本人はピースボート代表だった。 ▼新たな運動模索へ 「私の体験談に涙を流す人もいた。ヒロシマが埋没してしまったのではない。ただ、体験を話すだけではなく、その次の行動や論理がないと世界の運動の担い手には通用しないのだろう」と広島県被団協の坪井直事務局長。もう一つの県被団協の金子一士理事長も「署名集めなど従来の運動がひと休みしている今、観念的、抽象的でない具体的な行動が必要だ」。二人がハーグで得た感想は、新たな運動の模索で一致する。 三重大の児玉克哉助教授が指摘する。「ヒロシマが相手にされないのは被爆者のせいじゃない。日本のNGOが世界の運動に主体的にかかわってこなかった。そのツケがハーグで現れたのだ」 ▼今こそ市民の出番 確かに、世界法廷運動やアボリション(廃絶)2000など、最近の核兵器廃絶を求める世界の市民運動の潮流に、日本のNGOは協力こそすれ、自ら行動を提起し、リードする場面はほとんど見られなかった。ヒロシマが提唱してきた世界の核被害者との連帯にしても、交流の成果は重ねつつも、各国政府との補償交渉などへと運動を深めていく動きはまだ弱い。 北大西洋条約機構(NATO)のユーゴスラビア空爆は、紛争を武力で解決する力の思想の根強さをまざまざと見せつける。世界で六千万人が戦争や紛争の犠牲となったとされる今世紀の末に、ハーグがヒロシマに問いかけたのは、絶対平和のその思想を肉付けする行動、市民のほう起なのだ。
|
|