下.あすへの選択
― 問われる国際世論の力 ―
一九七〇年に発効した核拡散防止条約(NPT)の再検討会議は、五年ごとに加盟国が一堂に会して開かれる。七回目を数える今回、開幕が迫った今も議題は固まっていない。会議の成果は乏しい、との予測が関係者の間に目立つ。
前回(二〇〇〇年)と同様、日本政府代表団の一員として会議に出席する大阪大大学院の黒沢満教授も「かなり悲観的だ」とみる。考えられるシナリオは四つある。
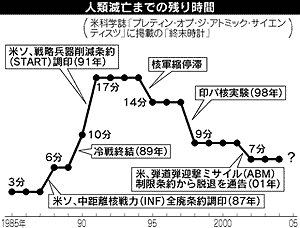
核兵器廃絶への「明確な約束」など十三項目の核軍縮措置を盛り込んだ前回と同じような最終文書が採択できればよい。何も文書を採択しないまま終われば最悪だ。その中間に、ごく簡単な文書か宣言を採択する▽議長が個人の見解として「議長声明」を出す―の二つの可能性があるという。
議長声明は公式文書とはみなされず、過去に例もない。ただ、再検討会議が空転すれば、議長を務めるブラジルのドゥアルテ軍縮・核不拡散担当大使が、苦肉の策として使うかもしれない。
全会一致で採択する最終文書の行方に、こうした紛れが生じるのは、米国の強硬姿勢が予測されるためだ。包括的核実験禁止条約(CTBT)の発効を認めない米国は、前回の合意の死文化を狙うとされる。今回の採択にも反対しそう。黒沢教授が「最悪のケースとなる可能性が五割以上」と予測するゆえんだ。ただ、皮肉めいてこうも言う。「何をもって成功なのか。決裂しても、その責任は米国にあると明らかにする方法もある」
原水禁国民会議の福山真劫事務局長は、核のない世界へと一歩でも進むため「前回の合意の確認が最低線」と主張する。「そのために非政府組織(NGO)を含め反核平和勢力の盛り上がりが問われる」と指摘する。
「今までの反核運動の背景には(核戦争への)危機感があった。今回の会議は希望が原動力になる」と話すのは日本原水協の高草木博事務局長。希望とは前回の最終文書の「明確な約束」。渋る核兵器保有国に廃絶を約束させたのは、メキシコなど七カ国でつくる新アジェンダ連合の勢いがあったから。今回も核兵器廃絶を求める世界の潮流は変わらないとみる。
その一例が、平和市長会議(会長・秋葉忠利広島市長)が提唱した、二〇二〇年までの核兵器廃絶をめざす緊急行動(2020ビジョン)。昨年来、欧州連合(EU)欧州議会に続き、千百八十三市でつくる全米市長会議が支持決議をした。
反核市民団体「ピースデポ」(横浜市)の梅林宏道代表もビジョンに期待を寄せる。「前回の新アジェンダ連合の活躍はNGOの後押しがあったからこそ」。そしてビジョンは今回、NGOや国際世論をまとめる芯(しん)の役割を果たす可能性があるというのだ。
原爆を投下した米国は今、核軍拡へ突き進もうとしている。その姿勢を追認するのか、見直しを迫るのか。再検討会議の鍵を握るのが国際世論とすれば、それを発信する被爆地広島の責任もまた重い。
(宮崎智三)
2005.4.28
| 
