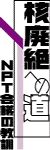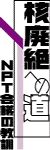上.決裂の背景
― 米の一国主義 障壁に ―
閉幕前日の二十六日、今回の再検討会議を象徴する場面があった。日本政府代表団が「最後まで合意に努力を」と呼びかけたのに対し、欧州連合(EU)を代表してルクセンブルクが賛意を表明。その直後だった。

|
| 成果のないまま閉幕したNPT再検討会議(5月27日)
|
エジプトがアラブ諸国を代表して「合意に努める」と演説したのだ。会場は一気に失笑で覆われた。会議の冒頭から最終場面まで、議事進行を遅らせ合意形成を妨げ続けたのがエジプト。その発言だけに、「何をいまさら」との受け止めが広がったのも無理はない。
だが、失笑の真の対象は「米国」だと、関係者の多くが指摘する。エジプトがこだわったのは、NPTに未加入で事実上の核兵器保有国であるイスラエルの扱い。会議で取り上げるべきだと主張しても、親イスラエルの米国は「聞く耳を持たない」姿勢に終始した。
中東問題ばかりではない。米国は今回、ことごとく「一国主義」を貫いた。一例が、包括的核実験禁止条約(CTBT)への対応。前回(二〇〇〇年)の再検討会議では全会一致で早期発効に合意しながら、今回は他の核兵器保有国ともたもとを分かつ形で「CTBT反対」を明言した。
さらに、新型核兵器開発など新たな核軍拡を進めているとの批判を真っ向から否定。戦略核弾頭の削減でロシアと交わしたモスクワ条約などを挙げ、NPT第六条が核兵器保有国に義務づける「核軍縮」を履行していると強調してみせた。
再検討会議は、一国でも反対すれば最終合意はできない「コンセンサス(全会一致)方式」を取る。前回は、核兵器廃絶を求める潮流が、一国の脱落も許さないほどに強いうねりとなり、最終文書での「明確な約束」として結実した。
しかし、「相手に譲る気がないなら、こちらも譲歩なんてしない、となる」と阿部信泰国連事務次長(軍縮担当)が指摘するように、批判覚悟の国が一つでも現れれば、コンセンサス方式はたちまち障壁となる。核兵器廃絶を妨げるのはどの国なのか―。水泡に帰した最終合意と引き換えに、今回の会議はそこを明確に浮き彫りにした。
被爆地から一言 日本被団協代表委員 坪井直さん(80)
■世界が連携 保有国包囲

核兵器廃絶の鍵を握るのは、やはり米国だということが、今回の再検討会議でもはっきりした。五年後の再検討会議を待つことはできない。今から、米国に廃絶を迫る国際的な包囲網をつくっていく必要がある。被爆地広島が、日本が、ことあるごとに訴え、行動を起こさないといけない。
もし米国が核兵器廃絶の先頭に立てば、ロシアなど他の四つの保有国でも、事実上の保有国であるインドやパキスタン、さらにイスラエルや北朝鮮でも、廃絶が可能になると私は思う。
確かに、米国の考えを変えるのは非常に難しいだろう。だが、「核兵器は絶対悪だ」という被爆者の訴えは世界中に浸透し、大多数の市民は核兵器の廃絶を求めている。各国の市民団体などと連携を深め、国際世論を盛り上げていくしかない。
そもそもNPTは、米国など五カ国だけに核兵器の保有を認める不平等な条約だ。核兵器をすべて禁止するよう、根本的に改めていかないといけない。非核兵器地帯を北半球に広げていくことも必要だ。
2005.6.7
|