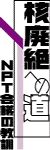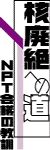中.被爆国の努力
― 「傘」に依存 限界生む ―
核拡散防止条約(NPT)再検討会議が大詰めに差し掛かったころ、日本政府代表団は米国のサンダース軍縮大使に、こう迫った。「合意がないまま終われば、会議は単なるトークショーになってしまう」。何ら譲歩をせず、合意を妨げる米国は、会議が失敗すればその責任が問われるに違いない。そう諭して翻意を迫る直談判だった。

|
| CTBTの早期発効をめざし、日本が賛同国を集めて開いたフレンズ会合
|
日本政府が核軍縮面での再検討会議の最重要項目に掲げたのが、包括的核実験禁止条約(CTBT)の早期発効。そのためには、批准を拒否する米国の姿勢を変えなければならない。日本は会議期間中、早期発効に賛同する十以上の国の大使らに呼び掛けて「フレンズ会合」を国連本部内で開くなど、会議の舞台裏で米国包囲網を敷いた。
核軍縮を話し合う第一主要委員会。議長による議論の総括案にはいったん、「CTBTの早期発効を期待して」との表現が盛り込まれた。その削除を要求する米国と、さらに表現を強めようとする日本の主張は、最後まで平行線をたどった。結局、委員会は論議の総括自体に合意が得られず、議長案も日本の提案も、幻と消えた。
被爆国日本が努力した場面はほかにもあった。例えば、核兵器保有国が非保有国を核攻撃しない「消極的安全保障」も含めた小委員会の設置を非同盟諸国が求め、不要とする米国など西側諸国とが対立したときだ。日本は「妥協しないと実質審議が始まらない」と粘り強く説得し、米国の譲歩を引き出した。
会議の最終盤でも、包括的な最終文書の採択が難しいとみるや、日本はドゥアルテ議長に「議長声明」を出すよう促した。その声明が審議内容には踏み込まないと察すると、今度は議長に数行のメモを渡し、NPTの重要性など将来につながるメッセージを発するよう求めた。
こうした奮闘は一定に評価されたものの、米国の強硬姿勢は変えられなかった。その要因を、英国の市民活動家レベッカ・ジョンソンさんは「戦略や強い政治的意志に欠けた」と指摘する。
自国の安全保障を米国の「核の傘」に依存しながら、国際社会には核軍縮を呼び掛ける。今回の再検討会議も結局のところ、被爆国の矛盾と限界を示す結末で終わった。
被爆地から一言 前広島市長 平岡敬さん(77)
■安全保障のビジョン示せ

日本がいくら唯一の被爆国として核兵器廃絶を訴えても、米国の「核の傘」に入っていたら説得力を持たない。インドやパキスタン、北朝鮮などに日本が核兵器の放棄を迫るのは、向こうから見れば、おかしな話。他国にとっては、日本は核兵器保有国と同じだからだ。国際社会では通用しないし、ものすごい矛盾がある。
核の傘から出るよう日本政府に迫るべきだ。そのためには、核の傘がなくても安全だと国民を説得できるかどうかが鍵になる。
中央アジア五カ国で進む非核地帯構想のように、日本政府も朝鮮半島を含めた非核地帯構想や、東アジア共同体の安全保障策の具体的ビジョンを提示すべきだ。
また、核兵器の廃絶は全人類的問題との認識に立ち、世界の核実験被害者を含めた「原爆展」を日本政府が開催すべきだと思う。ネバダやセミパラチンスク、マーシャル諸島などの(核実験被災の)データや写真を示せば、広島・長崎は過去のことではなく、現在につながる問題だと分かるだろう。
2005.6.8
|