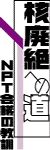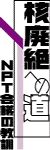下.ヒロシマの使命
― 保有国動かす戦略を ―
核拡散防止条約(NPT)再検討会議が開かれた米ニューヨークの国連本部で、日本被団協は初めて原爆展を開いた。原爆の熱線で焦げた学生服、溶けたステンドグラス、破壊し尽くされた市街地の写真パネル…。訪れた市民たちは多くが押し黙って見入り、被爆者たちが語るあの日の体験に耳を傾けた。

|
| 再検討会議に合わせて国連本部で開かれた原爆展。写真パネルなどが核兵器廃絶を無言で訴えた
|
「核兵器のない世界の実現に向け、力を注ぐ使命があるとあらためて感じた」。非政府組織(NGO)などの核軍縮ネットワーク「中堅国家構想」の提唱者として知られるカナダのダグラス・ローチ元軍縮大使が漏らした感想からも、被爆者の肉声と惨状を物語る資料の訴求力が分かる。
被爆地からのアピールは原爆展だけではなかった。広島から被爆者や市民ら百人以上がニューヨーク入りし、前回(二〇〇〇年)の再検討会議が合意した、核兵器廃絶への「明確な約束」を実行するよう迫った。
圧巻は、再検討会議の開幕前日にマンハッタンであった四万人規模のパレードと集会。被爆者たちは摩天楼を縫う行進の先頭に立ち、「核兵器は絶対悪だ」との訴えを響かせた。
広島、長崎両市などでつくる平和市長会議も、「二〇二〇年までの核兵器廃絶」を呼びかけた。各国から計百近い都市の市長らが集まった会合には国連のアナン事務総長も姿を見せ、「国際協力の橋渡しをする特別な役割がある」と市長会議の活動への期待を表明。被爆者である廿日市市の山下三郎市長の体験談は、万雷の拍手を浴びた。
核兵器廃絶から遠のく国際情勢だからこそ、そのカンフル剤としてのヒロシマの訴えに、世界は注目している―。原爆を投下した国で被爆者たちは、そんな手応えを強く感じたという。
半面、広島市の秋葉忠利市長らが再検討会議の昼休みを利用してスピーチした際は、聞き入る政府代表は最後には三十カ国程度に減り、国連の総会議場は空席ばかり目立った。国際情勢を左右する政策決定者、とりわけ核兵器保有国は、被爆地からの訴えに耳を傾けようとしない現実がある。
そのギャップをどう埋めていくのか―。再検討会議の失敗は、ヒロシマに、核兵器廃絶の訴えをより効果的に伝え響かせる戦略を問いかける。
被爆地から一言 広島市立大広島平和研究所長 浅井基文さん(63)
■米依存の矛盾解消が前提

広島と長崎は、被爆体験を普遍化し、それは六十年前の出来事ではなく今日的な課題なのだと方向付ける必要がある。これができれば、非政府組織(NGO)がけん引役になってつくった対人地雷禁止条約のように、核兵器廃絶に向けたエネルギーが世界的に盛り上がっていく。その素地はある、と思う。
核兵器は、大量殺りくと放射線被害の二重の残虐さを持つ。そして大量虐殺も、チェルノブイリやビキニ、劣化ウラン弾などの放射線被害も、世界各地に例があり、それぞれに普遍性、共通点がある。被爆体験と、現在のさまざまな人類的課題とを結びつけることができれば、被爆地はリーダーシップを発揮できる。
ただし、前提がある。日本中が一つになって、核兵器廃絶をめざして動くことが不可欠。そのためには、非核三原則を掲げながら米国の核抑止力に依存する政府の政策矛盾を突き、国民の意識を高めないといけない。
そこをあいまいにしたままでは、いくら叫んでも核兵器廃絶の訴えは、国際的な説得力に乏しく、念仏に終わる。
2005.6.10
|