 |
| 「いつか日本を訪れ、被爆者への医療対策などについて学びた い」と話すエレーナ・ヤクボブスカヤさん(ロシア・ノボシビルス ク市) |
 |
| 「いつか日本を訪れ、被爆者への医療対策などについて学びた い」と話すエレーナ・ヤクボブスカヤさん(ロシア・ノボシビルス ク市) |
 |
| 「先生の家庭訪問で教育を受けているけど、脳腫瘍の手術 後はついていくのが難しくなった」とアナトーリー君(中)の将来 を心配する母親のスベトラーナ・ズビンスカヤさん。(左)は二男 のジーマ君(セミパラチンスク市) |
 |
| 「被曝とともに経済の悪化が住民の健康に悪影響を与えている」 と話すサガダット・サガンディコーバさん(セミパラチンスク市) |
![]()
| Top page |
||||||
 [10] |
||||||
| 1年間 子ども6人死亡
ブルーの着衣に聴診器を手にしたアバイ地区総合病院小児科主治 医のショルパン・ムハメドジャノバさん(41)は、回診を終えると自 室に戻り、カラウル村を中心とした地区の人びとの健康状態につい て、自らの体験を交えながら話し始めた。 「実は私の父は、一九五三年八月十二日の初めての水爆実験の際 に、村に残された四十人の男性の一人でした。ソ連軍によって、人 体実験に使われたのです」。彼女はのっけから、ショッキングな話 を持ち出した。 アバイ地区の中心で、カザフ人が誇りとする民族詩人アバイ・ク ナンバエフの生誕の地でもあるカラウル村は、セミパラチンスク核 実験場の南端から南東へ約八十キロ。大気圏核実験が行われた「シ ャー地区」からは約二百キロである。 ソ連軍は実験に伴う「死の灰」の影響を避けるために、当時人口 一万人弱(現六千人)だったカラウル村をはじめ、風下地域の住民 の強制避難を実施した。しかし、このとき「四十人の成人男性は村 に残せ」との命令が出されたのだ。 「信じられないかもしれないけど事実です。父は爆発時の太陽の ような光や、異様な色をした雲が流れてくるのを見たと言っていま した」 地上三十メートルの鉄塔上で炸裂(さくれつ)し、地表のあらゆる物 を空に巻き上げながら南東に流れたその雲は、やがて放射性降下物 としてカラウル村周辺を激しく直撃。はるか彼方(かなた)にまで 降りそそいだ。 「村に残された住民は、全員大量の死の灰を浴びたのです。その ために父は、私がもの心ついたときには牛の世話など農作業をして いてもすぐに疲れが出て病気がちでした」 ムハメドジャノバさんの父は、八四年に肺がんのために六十五歳 で死亡した。彼女によれば、当時村に残された住民のほとんどは六 十代までに亡くなり、生存している人はもういないという。 「五四年に生まれた六歳年上の姉は、先天性心臓疾患のために二 十三歳で死亡した。私も貧血で疲れやすい。恐らく大気圏や地下核 実験が続いた当時にセミパラチンスク核実験場周辺に住んでいた人 たちで、本当に健康な人はいないと思う。その子どもたちへの影響 も深刻です」 核実験場に隣接するサルジャール村や、広島の市民団体「ヒロシ マ・セミパラチンスク・プロジェクト」が支援に力を入れるカイナ ール村などを含むアバイ地区の人口は約一万七千人。うち十五歳以 下の子どもたちは五千七百四十人。その中で重度の先天性障害者 は、二〇〇〇年末で百六十一人に達し、その数は年々増えていると いう。 「今年の初めから四カ月間で三人の子どもが脳腫瘍(のうしゅよう) で死亡し、白血病で亡くなった者もこの一年で成人ひとりを含め四 人もいます。ほかにも子どもたちの免疫力が弱いとか、妊婦の流産 や死産が目立つとか、挙げたら切りがないほどです」。地区の統計 資料を参照しながら説明するムハメドジャノバさんの口調は、だん だんと重くなっていった。 セミパラチンスク市内の市立診断センターで会った内科主治医の サガダット・サガンディコーバさん(50)も、「病人が多いのはポリ ゴン(実験場)周辺の村だけではない。セミパラチンスク市や周辺 でも同じ傾向にあります」と強調した。 同センターの患者の診断では、胃がんや肺がん、食道がんのほか に、最近は女性の乳がんや子宮がんも増えているという。さらに 「第二、第三世代への影響も見逃せない」とも。特に子どもたちの 甲状腺がんが顕著であるほか、脳腫瘍なども見られるとい う。 「これらのすべてが放射線被曝の影響とは限りません。 でも、四十年間にわたって続いた核実験による直接、間接の被曝と 深く結びついているのは間違いありません」と、サガンディコーバ さん。 彼女の紹介で脳腫瘍の手術を九八年に受け、今も家庭で療養中の アナトーリー・シェル君(14)の家族を、セミパラチンスク市内のア パート二階に訪ねた。 こぢんまりとした居間。ソファに腰を下ろした母親のスベトラー ナ・ズビンスカヤさん(32)は、そばのアナトーリー君の肩にときお り手を掛けながら体験を語った。「息子は小さいときは、近くの川 で泳いだりしてとても元気な子どもだった。でも、十歳になる前か ら歩いていてふらついたり、少しずつ様子がおかしくなった。九七 年末に小脳のがんだと診断されたときは、頭の中が真っ白になって しまって…」 診断から二週間後には、セミパラチンスクの病院より設備の整っ たロシアのバルナウル市で手術を受けた。他の器官への悪影響を防 ぐため、腫瘍はまだ少し残っているという。その腫瘍を刺激しない ように、抗がん剤は使わず、ハーブ治療を続ける。 「アナトーリーの病気は百パーセント核実験のせいだと思ってい ます。川で泳いでいて放射性物質を体内に取り込んだかもしれない し、この町で生まれ育った私たち親の影響かもしれません」 母親にとって、心配は長男の病状ばかりではなかった。今は元気 な二男のジーマ君(7つ)の将来の健康が気になって仕方がないのだ。 「長男もジーマの年ごろはまだ元気だった。でもその後の経過を考 えると、気にしないようにと思っても気になってしまいます」 セミパラチンスク市出身の彼女は、両親をがんなどで失った後の 七七年、兄のいるノボシビルスクへ移り住んだ。自らも足や腕の痛 み、ひどい頭痛などに苦しみながら、耳鼻咽喉(じびいんこう)の専門 医として州立病院で勤務。年金生活に入った九九年に「セミパラチ ンスク同盟」をつくり、会長として核実験被害者の健康相談に乗る などの支援を続ける。 「私は医者としての体験を基に、二世・三世の問題を含めて核実 験がもたらした健康被害について二冊の本を出しました。今はここ に住むヒバクシャに体験記を書いてもらっています。まだ六十人分 ほどしか集まっていないけど、多くのヒバクシャが健康被害だけで なく、精神的な不安を抱えているのがよく分かります」 人口百五十万人のノボシビルスクには、かつてセミパラチンスク 核実験場で兵役に就いた元兵士や、バルナウルなどアルタイ地方の 汚染地域から移り住んだ人たちら約八千人の核実験被害者がいると される。 「ヒバクシャはいつも放射線という見えない脅威にさらされてい るのです。もともと被曝によって免疫性が弱められたうえに精神的 なストレスが加わるために、より病気にかかりやすくなっていま す」 ヤクボブスカヤさんの話は、そのまま広島・長崎の被爆者が半世 紀余にわたって体験したことと重なっていた。そのことを口にする と、彼女は間髪を入れずに言ったものである。 「確かに同じです。でも、こちらでは先天性障害やがんの発病な どの形で、次世代への影響がよりはっきり出ています。それだけに 余計に怖い気がしてなりません」 「安全保障」の名のもと、旧ソ連が四十年にわたりセミパラチン スク核実験場で行った大気圏と地下核実験は、合わせて四百六十六 回。核爆発の総威力は、広島型原爆千百六十個分に相当する一七・ 四メガトン。その代償は、「冷戦のツケ」として片づけるにはあま りにも大きい。 |
下 |
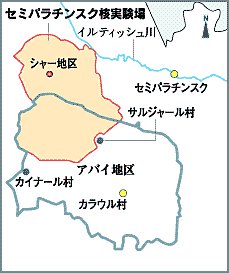
|
||||
| Top page |
||||||