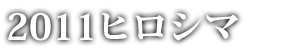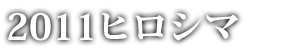12年ぶりとなった被爆地の市長交代に伴い、平和宣言も変わる。
きのう松井一実広島市長が、6日の平和記念式典で読み上げる宣言文の骨子を発表した。公募した被爆者の体験記を引用するのが、これまでにない特色である。
東日本大震災にも言及して復興を願うとともに、エネルギー政策の早急な見直しを国に求める。
新市長としてのカラーは、それなりに出るのではないか。
宣言で紹介するのは2人の手記だ。79歳の男性は原爆投下の前日、川で遊ぶ平穏な暮らしがあったことを伝える。82歳の女性は皮膚を焼かれて逃げ惑う中、泣き叫ぶ子どもを助けられなかったつらい記憶をたどる。
体験風化が心配されて久しいだけに、原点の継承に重きを置いたといえよう。昔なら言うに及ばなかった原爆投下時刻にも触れる。
このところの宣言には市長の個性がにじみ出ていた。先々代の平岡敬氏、先代の秋葉忠利氏ともに、内外の情勢を自分なりに分析して筆をふるい、明確に主張した。半面、幅広い市民の声を十分に反映したとは言いにくかった。
今年は手法を見直した。市長が執筆するのは同じだが、被爆者や有識者ら9人にどうあるべきか諮った。引用する手記を選んでもらう委員会を「活用」した格好だ。
松井市長は被爆2世とはいえ、厚生労働省の官僚時代には原爆や核の問題を突き詰めて考える機会はあまりなかったと聞く。そうした事情も背景にあるのだろう。
長崎市の平和宣言は毎年、有識者らの起草委員会が練り上げる。かねて広島でも同じ仕組みを求める意見があった。今年は市民サイドに一歩近づいたとみていい。
共感を広げようとの工夫はほかにもある。平易な言葉をできるだけ使い、「見ても聞いても理解しやすい表現」にしたという。昨年まで「格調高いが難解」と指摘された点を意識したとみられる。
ただ被爆地が世界に向けて発信する提言としては、どう受け止められるだろうか。
福島第1原発の事故を受け、原子力の平和利用への姿勢が問われている。骨子によると「脱原発を主張する人々がいる」と第三者的な言い回しでエネルギー政策の見直しを訴えるという。物足りなさを感じる人がいるかもしれない。
核兵器廃絶は従来通り、2020年を目標とする。新たに核不拡散体制を議論する国際会議の広島誘致を呼び掛ける。
一方、米国の臨界前核実験にも触れるが、核保有国全体に廃絶への取り組みを促すにとどめるようだ。昨年の宣言で日本政府に求めた「核の傘」からの離脱も、今回の骨子には見当たらない。
こうした点を強調しなければ、核兵器廃絶への訴えも具体性に欠けてしまう。
市長は来年も同じ方式を続ける意向という。寄せられる反響に耳を傾け、訴求力をより高めてもらいたい。被爆者や市民の思いをくみ、市長の決意も盛り込むための一層の工夫が欠かせまい。