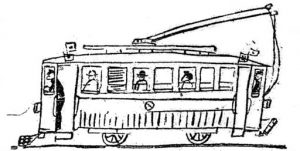「がんす横丁」シリーズ 夢の盛り場―新天地界わいの思い出― (九)京口門付近砂絵師の話②
15年7月5日
文・薄田太郎 絵・福井芳郎
砂絵師のそばには、その女房らしい、温和そうな老婆がいて、色分けにした砂の調合をやり、投げ銭あつめの役をやる。いろいろに染められた砂――それは砂というより石炭を色づけにした粉のようなもので、コバルト色のくっきりと感じの明るさを現(あら)わした色とか茶かっ色のなんとなく妖気を帯びたもの、みどり色、そして紅色のこれはまた、はればれとした感じを現わしたものなど、それぞれが皿に盛られて、砂絵師の右側前に並べられてある。
静かに右手に、この砂を握って体を前にのめり出して、右に左に細い砂の線を描きあげてゆく。だれにも幼いころに、砂いじりをした思い出があるもので、川砂を握って小山をつくりあげるとき、一筋の砂が右手の半節から流れ落ちるとき、われにもなく心たのしいものであるが、この老人はそれを右に動かし、左に回して岩見重太郎大蛇退治の図を、たたみ二枚くらいの大きさに描きあげるのである。重太郎の太刀を引き抜いて、大上段にふりカブった胸のあたり講談風のくさりかたびらが見えたり、上衣のクッキリしたミドリ色野袴(のばかま)のコバルト色、大蛇全体が茶かっ色で描かれ、口から吐かれた火焔のような舌は、目もさめるような紅色が流されている。
それがいつも客を前にして、自分はそのままで、客の方向にこの砂絵を描くので、まさに逆描きの妙技である。然(しか)もこの絵をひととおり描きあげると、向(むか)って右角のあたりに、漢文で説明を書き添えるが、これとても逆書きで、非凡な腕前である。
やがて、投げ銭が飛んでゆく。銅貨のなかに白銅や銀貨が混(まじ)っている。間もなく老婆が進み出て、このケッサクを手ぼうきで、こともなく消してゆく、砂絵師はおもむろに、大ぎせるを出して煙草(たばこ)を吸い、やがて物凄(ものすご)い幽霊を描きはじめた。その時の老砂絵師の、おそろしい表情が、子供心に忘れられなかった。砂絵師を見たのはわずか一回限りであるが、彼らは土地の者でなく、旅をしのぎの夫婦者であったらしい。それも、広島を訪れた最後の砂絵師であったかも知れない。その後京口門一帯は、もと偕行社裏の砂ッ原に、夏は納涼場として、奇術や水芸を見せる小屋が出来たり、秋には菊人形が飾られて、埋めたての砂を、ザクザクと歩いたことを覚えている。
(2015年7月5日中国新聞セレクト掲載)
砂絵師のそばには、その女房らしい、温和そうな老婆がいて、色分けにした砂の調合をやり、投げ銭あつめの役をやる。いろいろに染められた砂――それは砂というより石炭を色づけにした粉のようなもので、コバルト色のくっきりと感じの明るさを現(あら)わした色とか茶かっ色のなんとなく妖気を帯びたもの、みどり色、そして紅色のこれはまた、はればれとした感じを現わしたものなど、それぞれが皿に盛られて、砂絵師の右側前に並べられてある。
静かに右手に、この砂を握って体を前にのめり出して、右に左に細い砂の線を描きあげてゆく。だれにも幼いころに、砂いじりをした思い出があるもので、川砂を握って小山をつくりあげるとき、一筋の砂が右手の半節から流れ落ちるとき、われにもなく心たのしいものであるが、この老人はそれを右に動かし、左に回して岩見重太郎大蛇退治の図を、たたみ二枚くらいの大きさに描きあげるのである。重太郎の太刀を引き抜いて、大上段にふりカブった胸のあたり講談風のくさりかたびらが見えたり、上衣のクッキリしたミドリ色野袴(のばかま)のコバルト色、大蛇全体が茶かっ色で描かれ、口から吐かれた火焔のような舌は、目もさめるような紅色が流されている。
それがいつも客を前にして、自分はそのままで、客の方向にこの砂絵を描くので、まさに逆描きの妙技である。然(しか)もこの絵をひととおり描きあげると、向(むか)って右角のあたりに、漢文で説明を書き添えるが、これとても逆書きで、非凡な腕前である。
やがて、投げ銭が飛んでゆく。銅貨のなかに白銅や銀貨が混(まじ)っている。間もなく老婆が進み出て、このケッサクを手ぼうきで、こともなく消してゆく、砂絵師はおもむろに、大ぎせるを出して煙草(たばこ)を吸い、やがて物凄(ものすご)い幽霊を描きはじめた。その時の老砂絵師の、おそろしい表情が、子供心に忘れられなかった。砂絵師を見たのはわずか一回限りであるが、彼らは土地の者でなく、旅をしのぎの夫婦者であったらしい。それも、広島を訪れた最後の砂絵師であったかも知れない。その後京口門一帯は、もと偕行社裏の砂ッ原に、夏は納涼場として、奇術や水芸を見せる小屋が出来たり、秋には菊人形が飾られて、埋めたての砂を、ザクザクと歩いたことを覚えている。
(2015年7月5日中国新聞セレクト掲載)