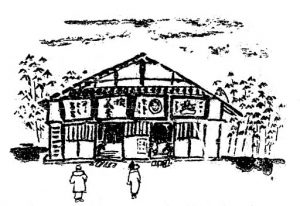「がんす横丁」シリーズ 夢の盛り場―新天地界わいの思い出― (十一)八千代座の娘 義太夫
15年8月2日
文・薄田太郎 絵・福井芳郎
中央勧商場は、流川からの東入口が淋(さび)しい通りで、両側に竹藪(やぶ)があり、八千代座の角まで出ると、大弓屋があった。この八千代座はムスメ義太夫の定小屋で、収容人員は凡(おおよ)そ四百人位(くら)い。開演時間が来れば、客がたとえ二人や三人であろうと、舞台を包んだ黄色のみすが引き上げられる。ムスメさん達は、ちからの限りおそのともなりお染ともなって泣きクズれる。開幕のお祝儀、宝の入船のかけ合いは、いとも華やかに小屋の外までひびいて来るのであるが、中をのぞくと前述のようにお客さん二、三人が碁の打ちはじめのように極めてマバラに座り込んでいたものである。客が少なくともムスメ達が声をあげての熱演はそれを称して修業といっていた。客がいなくとも修業が出来るのがフシギであるが、実は舞台ウラで師匠がこれを聞いていて引込みになってからいろいろダメが出されるような仕組みになっていた。それにしても碁石のようなマバラな客は、さぞテレクサかったであろうというとそれが実は、師匠以上にコワイ、定小屋の持主(もちぬし)だったそうである。
娘義太夫のミリョクは、あの美しい独特の結髪、花かんざしの薬玉(くすだま)のヒラヒラ、色トリドリの片ギヌ、こぼれるようなアイキョウ、―今様に例えれば、山田五十鈴扮(ふん)するところの「滝の白糸」から、マイナス水芸、プラス三味線と見台といった公式計算から、割り出された若い美ぼうの女性たちである。それだけに、キセイを聞きにくる若い客も多いが、定席のお得意は、町家の旦那達、いわゆるじょうるり天狗(てんぐ)であった。
大御所豊竹呂昇そっくりの豊竹栄昇の盛装姿が表看板に飾られ、その下に小屋の印はんてんを着た下足番の古風な姿―お祝儀から三、四番までは、ガラあきの場内が、中入後時刻にして九時過ぎには、天狗たちで一ぱいになる。花あられの入った熱い湯呑(ゆのみ)を手にしたじょうるりファンが、興に乗るにまかせて首など振っているのは、まだよい方で、中には貸たばこ盆の灰吹きに、きせるの雁首(がんくび)を叩きつけて、相拍子をうつようなサムライもある。
舞台の若い彼女たちは、ツイこのサムライの打つ乱拍子に釣り込まれて、時に舞台をしくじることもあったという。そんなワケで、これが対策に掛合いという新しい仕組(しくみ)が考えられたのか、その真疑(しんぎ)の程は知らない。
間もなく、この小屋も時流に押されて、活動シャシン館になったのは、明治四十五年の春ころであった。
(2015年8月2日中国新聞セレクト掲載)
中央勧商場は、流川からの東入口が淋(さび)しい通りで、両側に竹藪(やぶ)があり、八千代座の角まで出ると、大弓屋があった。この八千代座はムスメ義太夫の定小屋で、収容人員は凡(おおよ)そ四百人位(くら)い。開演時間が来れば、客がたとえ二人や三人であろうと、舞台を包んだ黄色のみすが引き上げられる。ムスメさん達は、ちからの限りおそのともなりお染ともなって泣きクズれる。開幕のお祝儀、宝の入船のかけ合いは、いとも華やかに小屋の外までひびいて来るのであるが、中をのぞくと前述のようにお客さん二、三人が碁の打ちはじめのように極めてマバラに座り込んでいたものである。客が少なくともムスメ達が声をあげての熱演はそれを称して修業といっていた。客がいなくとも修業が出来るのがフシギであるが、実は舞台ウラで師匠がこれを聞いていて引込みになってからいろいろダメが出されるような仕組みになっていた。それにしても碁石のようなマバラな客は、さぞテレクサかったであろうというとそれが実は、師匠以上にコワイ、定小屋の持主(もちぬし)だったそうである。
娘義太夫のミリョクは、あの美しい独特の結髪、花かんざしの薬玉(くすだま)のヒラヒラ、色トリドリの片ギヌ、こぼれるようなアイキョウ、―今様に例えれば、山田五十鈴扮(ふん)するところの「滝の白糸」から、マイナス水芸、プラス三味線と見台といった公式計算から、割り出された若い美ぼうの女性たちである。それだけに、キセイを聞きにくる若い客も多いが、定席のお得意は、町家の旦那達、いわゆるじょうるり天狗(てんぐ)であった。
大御所豊竹呂昇そっくりの豊竹栄昇の盛装姿が表看板に飾られ、その下に小屋の印はんてんを着た下足番の古風な姿―お祝儀から三、四番までは、ガラあきの場内が、中入後時刻にして九時過ぎには、天狗たちで一ぱいになる。花あられの入った熱い湯呑(ゆのみ)を手にしたじょうるりファンが、興に乗るにまかせて首など振っているのは、まだよい方で、中には貸たばこ盆の灰吹きに、きせるの雁首(がんくび)を叩きつけて、相拍子をうつようなサムライもある。
舞台の若い彼女たちは、ツイこのサムライの打つ乱拍子に釣り込まれて、時に舞台をしくじることもあったという。そんなワケで、これが対策に掛合いという新しい仕組(しくみ)が考えられたのか、その真疑(しんぎ)の程は知らない。
間もなく、この小屋も時流に押されて、活動シャシン館になったのは、明治四十五年の春ころであった。
(2015年8月2日中国新聞セレクト掲載)