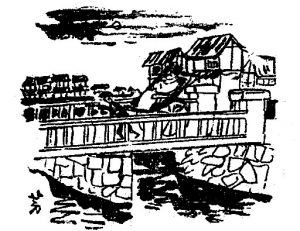「がんす横丁」シリーズ 夢の盛り場―新天地界わいの思い出― (三十三)新しい芝居(その2)
16年5月1日
文・薄田太郎 絵・福井芳郎
大正十(一九二一)年頃はオペラ全盛時代で、広島もお他聞に洩(も)れず歌劇群が来演した。新星歌劇、オペラ座など寿座の舞台もにぎやかで、石井漠の「明暗」、西本朝春、岩間桜子の国華座、松旭斎天勝も六代目張りの鏡獅子を上演すれば、村田栄子の戯曲座が新地座で得意の「舞扇」でカレンなところを見せた。新地座といえば、当時流行の安来節が、家元渡部お糸の数回の来演で、ここ数年ヒロシマの街角に安来節がハンランした。一方、小原節では、北陸の名妓(美人という意味である)万龍が、自動車での町回りで寿座に現れて、安来節の牙城をうかがったが、遂(つい)に食い込めなかった。
鈴木康義が主宰した東京少女歌劇団が現れたのもこの頃で、芸達者の谷崎とし子の「藤六人形」、松川浪子、白川澄子の「仏法僧」、貴島田鶴子のトウダンスなども寿座での上演であったが、先頃筆者が尾道市久保町の裏街を歩いていると、その当時の同歌劇団のビラがそのまま壁にベットリとはりつけられているのを見た。あれから三十年近くも風雨にさらされているなどは、まさに東京少女の奇跡で、トウダンスでは、若冠高木徳子や沢モリノがあり、ともに劇的な死を遂げたあたり、広島での在りし日のステージが思い出される。震災前年の十一年であった。
当時原信子との水銀事件で問題の美人扱いされた丹稲子が、寿座の舞台でキモノを着て「デアボロ」を唄(うた)い、一行にはシャイロック役者と定評のあった日疋重亮、後にケン劇に転じた明石潮、黒木憲三、土御門華子などがいて新しい芝居を上演した。これは新派でもなく、剣劇でもなく、沢田正二郎の初期新国劇の影響を受けての芝居で、型物にならぬ写実表現が当時の若人たちに受けたもので、老人達にはまことにあほらしい「芝居」であったらしいが、実は革新劇の一種であったワケである。
この新しい劇団も間もなく解散して日疋、明石はのちに東亜の甲陽スタジオに入ったが、巡業時代の芝居ばなしでは「広島の夜の河(かわ)は忘れられない」と、特に本川橋からの新大橋遠景や、元安橋あたり慈仙寺はなの風景を絶サンしたものである。若かりし頃の宮城道雄が琴を積んで、西の演舞場公演からの帰途、人力車にユラれて元安橋に差しかかった情景や、最近銀幕にカムバックした広島出身のハヤブサ秀人が、元安橋脚から飛び込んだ寒中水泳も、また「大地は微笑(ほほえ)む」で売り出した中野英治が、うらぶれての師走の寒空に一座の女優とこの橋上に佇(たた)ずんでいたあたり、行きずりの筆者の目には、その一コマ一コマが夢の盛り場に現れるシルエットにもなるワケである。
(2016年5月1日中国新聞セレクト掲載)
大正十(一九二一)年頃はオペラ全盛時代で、広島もお他聞に洩(も)れず歌劇群が来演した。新星歌劇、オペラ座など寿座の舞台もにぎやかで、石井漠の「明暗」、西本朝春、岩間桜子の国華座、松旭斎天勝も六代目張りの鏡獅子を上演すれば、村田栄子の戯曲座が新地座で得意の「舞扇」でカレンなところを見せた。新地座といえば、当時流行の安来節が、家元渡部お糸の数回の来演で、ここ数年ヒロシマの街角に安来節がハンランした。一方、小原節では、北陸の名妓(美人という意味である)万龍が、自動車での町回りで寿座に現れて、安来節の牙城をうかがったが、遂(つい)に食い込めなかった。
鈴木康義が主宰した東京少女歌劇団が現れたのもこの頃で、芸達者の谷崎とし子の「藤六人形」、松川浪子、白川澄子の「仏法僧」、貴島田鶴子のトウダンスなども寿座での上演であったが、先頃筆者が尾道市久保町の裏街を歩いていると、その当時の同歌劇団のビラがそのまま壁にベットリとはりつけられているのを見た。あれから三十年近くも風雨にさらされているなどは、まさに東京少女の奇跡で、トウダンスでは、若冠高木徳子や沢モリノがあり、ともに劇的な死を遂げたあたり、広島での在りし日のステージが思い出される。震災前年の十一年であった。
当時原信子との水銀事件で問題の美人扱いされた丹稲子が、寿座の舞台でキモノを着て「デアボロ」を唄(うた)い、一行にはシャイロック役者と定評のあった日疋重亮、後にケン劇に転じた明石潮、黒木憲三、土御門華子などがいて新しい芝居を上演した。これは新派でもなく、剣劇でもなく、沢田正二郎の初期新国劇の影響を受けての芝居で、型物にならぬ写実表現が当時の若人たちに受けたもので、老人達にはまことにあほらしい「芝居」であったらしいが、実は革新劇の一種であったワケである。
この新しい劇団も間もなく解散して日疋、明石はのちに東亜の甲陽スタジオに入ったが、巡業時代の芝居ばなしでは「広島の夜の河(かわ)は忘れられない」と、特に本川橋からの新大橋遠景や、元安橋あたり慈仙寺はなの風景を絶サンしたものである。若かりし頃の宮城道雄が琴を積んで、西の演舞場公演からの帰途、人力車にユラれて元安橋に差しかかった情景や、最近銀幕にカムバックした広島出身のハヤブサ秀人が、元安橋脚から飛び込んだ寒中水泳も、また「大地は微笑(ほほえ)む」で売り出した中野英治が、うらぶれての師走の寒空に一座の女優とこの橋上に佇(たた)ずんでいたあたり、行きずりの筆者の目には、その一コマ一コマが夢の盛り場に現れるシルエットにもなるワケである。
(2016年5月1日中国新聞セレクト掲載)