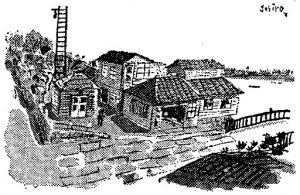「がんす横丁」シリーズ がんす横丁 (十九)柳橋界隈(かいわい)(その3)㊦
16年12月18日
文・薄田太郎 え・福井芳郎
それにつけても、いまの土手町は荒れるにまかせたような殺風景なもので、スクラップ同様に、原爆を浴びた火の見ヤグラの残骸がポツンと取り残されているのも寂しい思いがする。
あのころの土手町下の一角には赤びょうたんの看板を屋上に掲げた鍼灸(しんきゅう)屋さんがあった。竹製ボテ作りのあの赤びようたんは印象深いものであった。
また、電車道にある稲荷社は、佐官町の稲荷さんとともに十一月八日が例祭で、子供心に覚えているのは、あの稲荷さんの前には祭り提燈(ちょうちん)が飾られて、土手町から稲荷町へ降りてゆく坂を歩きながら、ユラリユラリと風にゆれている提燈に見とれたものである。街燈(がいとう)もなかったころのことで、この提燈のあかりがその道を明るく照らした印象も忘れられない。
稲荷社の右入口には平塚町の金比羅さんや下柳町のお薬師さんの祭でおなじみの「みりんかす」と「ふやけ豆」を売っていたおばさんの姿を思い出す。みりんかすや豆をそれぞれ部厚の紙袋に入れてキチンと並べてあった。いつも「石菓子」を売っていたおじさんとコンビの商売をやっていたのも思い出される。
稲荷町の社が電車道の出現でいまの位置に移され、社殿も原爆以前にも増して立派になったのも感慨無量である。稲荷さんといえば、さらに稲荷大橋の出現も、あるいはお稲荷さんのおかげであるかもしれない。このようなことをいえば、筆者がまたも「ユメの盛り場」の稲荷さんを引っぱり出したと笑われるかも知れぬ。
柳橋の東通りには理髪店があって、その店先には床にしょうぎ(床机)あるいは置座が出されて、その上では将棋好きのファンが文字通り詰めかけて、連日連夜王将戦が行われたのも、柳橋風景の一つであった。
大河の住人三代十郎兵衛のお墨付で話題をにぎわした松川町の法正寺あたりの焼け落ちた壁には、昔の名残りがうかがえる。昔の地図にある茅屋町のはまぐりは、このあたりにあったものであろう。
再び柳橋を西に渡ると、この橋のたもとには、夏時分「あまざけ」や「あめ湯」という古風なかつぎ店の姿が見られた。
また、冬にはこの土手の一角に「たき肉」の屋台店が出たもので、みそだきの一本一銭の串はなかなかに風味があった。
店のおばさんが「この商売をやるまでには、よくしごう(料理をするの意)をやりんさるのうと悪口を言われたもんでがんす」とこぼしていたが、これが広島元祖の「たき肉」の屋台であったと想(おも)うが、大正七、八年ごろのことである。
(2016年12月18日中国新聞セレクト掲載)
それにつけても、いまの土手町は荒れるにまかせたような殺風景なもので、スクラップ同様に、原爆を浴びた火の見ヤグラの残骸がポツンと取り残されているのも寂しい思いがする。
あのころの土手町下の一角には赤びょうたんの看板を屋上に掲げた鍼灸(しんきゅう)屋さんがあった。竹製ボテ作りのあの赤びようたんは印象深いものであった。
また、電車道にある稲荷社は、佐官町の稲荷さんとともに十一月八日が例祭で、子供心に覚えているのは、あの稲荷さんの前には祭り提燈(ちょうちん)が飾られて、土手町から稲荷町へ降りてゆく坂を歩きながら、ユラリユラリと風にゆれている提燈に見とれたものである。街燈(がいとう)もなかったころのことで、この提燈のあかりがその道を明るく照らした印象も忘れられない。
稲荷社の右入口には平塚町の金比羅さんや下柳町のお薬師さんの祭でおなじみの「みりんかす」と「ふやけ豆」を売っていたおばさんの姿を思い出す。みりんかすや豆をそれぞれ部厚の紙袋に入れてキチンと並べてあった。いつも「石菓子」を売っていたおじさんとコンビの商売をやっていたのも思い出される。
稲荷町の社が電車道の出現でいまの位置に移され、社殿も原爆以前にも増して立派になったのも感慨無量である。稲荷さんといえば、さらに稲荷大橋の出現も、あるいはお稲荷さんのおかげであるかもしれない。このようなことをいえば、筆者がまたも「ユメの盛り場」の稲荷さんを引っぱり出したと笑われるかも知れぬ。
柳橋の東通りには理髪店があって、その店先には床にしょうぎ(床机)あるいは置座が出されて、その上では将棋好きのファンが文字通り詰めかけて、連日連夜王将戦が行われたのも、柳橋風景の一つであった。
大河の住人三代十郎兵衛のお墨付で話題をにぎわした松川町の法正寺あたりの焼け落ちた壁には、昔の名残りがうかがえる。昔の地図にある茅屋町のはまぐりは、このあたりにあったものであろう。
再び柳橋を西に渡ると、この橋のたもとには、夏時分「あまざけ」や「あめ湯」という古風なかつぎ店の姿が見られた。
また、冬にはこの土手の一角に「たき肉」の屋台店が出たもので、みそだきの一本一銭の串はなかなかに風味があった。
店のおばさんが「この商売をやるまでには、よくしごう(料理をするの意)をやりんさるのうと悪口を言われたもんでがんす」とこぼしていたが、これが広島元祖の「たき肉」の屋台であったと想(おも)うが、大正七、八年ごろのことである。
(2016年12月18日中国新聞セレクト掲載)