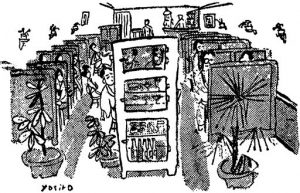「がんす横丁」シリーズ 續がんす横丁 (九)播磨屋町(その3)㊥
19年5月26日
文・薄田太郎 え・福井芳郎
喫茶店「桃源」の設備で店内の照明に東京地下鉄の間接照明を採用したのも広島最初のもので、店内に陳列された電気冷蔵庫三台も当時の広島では珍しいものだった。
レコード好きの室木君は蓄音器チニーを設備して、左手でヴァイオリンを弾いたチャップリン自作曲の「テッティナ」を聞かせたのも彼であった。また店頭に八球のラジオ、ウェスタンハウスを備えつけて、昭和三年の夏に甲子園野球の実況を直接受信して聴かせたものである。
また、この店で忘れられないのは洋画家大木茂氏や増田健夫君、それに流川の名井屋で働いて油絵を勉強していた名物男“まんじゅう”こと永久博郎君たちで、この店の壁面を利用しての三人会の洋画展覧会も行われた。
三人会の一人増田健夫君は、この店の包紙(ぶどうの意匠)やレベル(宝船のデザイン)を受持って、毎月、マッチの季節感を織込んで意匠を書いたものである。増田健夫君は当時の文学青年や画家仲間で「マスケン」の愛称で呼ばれたもので、彼が描いた「包紙」や「レベル」はその後東京商工会議所を通じてアメリカのシカゴに送られ、包装コンクールに出品されて入賞したこともある。
増健は当時、元安川河畔の商品陳列館の図案部で、余技の商業美術でいくらかの謝礼を貰(もら)っていた。金屋町に住んだ彼は、生来のぜんそくに悩まされて静養生活をつづけ、詩人大木惇夫氏や今井草二氏が発刊した「広島芸術」にも「闘病の詩」を書いて発表していた。
この病気には、生きた青ガエルをオブラートに包んでのむとよくなると聞かされて、さっそく青ガエルをのんだが、一晩中この青ガエルが胃袋の中で飛び回っているので、この小さな犠牲には相スマないような気がしたと、彼独特の哀愁を込めた詩を書いていた。
彼は昭和七、八年ごろ四十一歳で病没したが作品は一点も残さなかった洋画家である。商業美術への図案は、彼の性格をそのまま表現しているように清純そのもののデザインで、ことに色調の美しさも彼独自のものであった。今ごろでも本通り辺りを歩いていると長身の増健が現われてきそうな気がする。
この連載は、1953(昭和28)年7月から9月にかけて中国新聞夕刊に掲載した「続がんす横丁」(第1部)の復刻です。旧漢字は新漢字とし、読みにくい箇所にルビを付けました。表現は原則として当時のままとしています。
(2019年5月26日中国新聞セレクト掲載)
喫茶店「桃源」の設備で店内の照明に東京地下鉄の間接照明を採用したのも広島最初のもので、店内に陳列された電気冷蔵庫三台も当時の広島では珍しいものだった。
レコード好きの室木君は蓄音器チニーを設備して、左手でヴァイオリンを弾いたチャップリン自作曲の「テッティナ」を聞かせたのも彼であった。また店頭に八球のラジオ、ウェスタンハウスを備えつけて、昭和三年の夏に甲子園野球の実況を直接受信して聴かせたものである。
また、この店で忘れられないのは洋画家大木茂氏や増田健夫君、それに流川の名井屋で働いて油絵を勉強していた名物男“まんじゅう”こと永久博郎君たちで、この店の壁面を利用しての三人会の洋画展覧会も行われた。
三人会の一人増田健夫君は、この店の包紙(ぶどうの意匠)やレベル(宝船のデザイン)を受持って、毎月、マッチの季節感を織込んで意匠を書いたものである。増田健夫君は当時の文学青年や画家仲間で「マスケン」の愛称で呼ばれたもので、彼が描いた「包紙」や「レベル」はその後東京商工会議所を通じてアメリカのシカゴに送られ、包装コンクールに出品されて入賞したこともある。
増健は当時、元安川河畔の商品陳列館の図案部で、余技の商業美術でいくらかの謝礼を貰(もら)っていた。金屋町に住んだ彼は、生来のぜんそくに悩まされて静養生活をつづけ、詩人大木惇夫氏や今井草二氏が発刊した「広島芸術」にも「闘病の詩」を書いて発表していた。
この病気には、生きた青ガエルをオブラートに包んでのむとよくなると聞かされて、さっそく青ガエルをのんだが、一晩中この青ガエルが胃袋の中で飛び回っているので、この小さな犠牲には相スマないような気がしたと、彼独特の哀愁を込めた詩を書いていた。
彼は昭和七、八年ごろ四十一歳で病没したが作品は一点も残さなかった洋画家である。商業美術への図案は、彼の性格をそのまま表現しているように清純そのもののデザインで、ことに色調の美しさも彼独自のものであった。今ごろでも本通り辺りを歩いていると長身の増健が現われてきそうな気がする。
この連載は、1953(昭和28)年7月から9月にかけて中国新聞夕刊に掲載した「続がんす横丁」(第1部)の復刻です。旧漢字は新漢字とし、読みにくい箇所にルビを付けました。表現は原則として当時のままとしています。
(2019年5月26日中国新聞セレクト掲載)