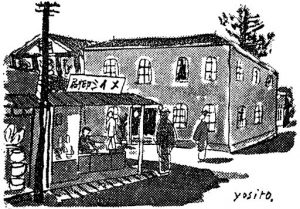「がんす横丁」シリーズ 續がんす横丁 (二十一)松井須磨子を偲(しの)んだカフェーブラジルでの会合(その1)㊦
20年1月19日
文・薄田太郎 え・福井芳郎
芸術座の広島初乗込みは大正四年の夏で、三年後の大正七年十一月五日には、芸術座を主宰した島村抱月が肺炎で急逝した。松井須磨子は生きる望みを失って、有楽座でメリメの「カルメン」上演最中、抱月氏の跡を追うて大正八年一月五日、有楽座の楽屋で自殺したことは、十一人座のメンバーにも非常なショックを与えた。
須磨子の自殺については、広島とは関係の深い小山内薫氏が次のような一文を書いているので、参考までにその抜き書きをお伝えしましょう。
芸術座の芝居で一番はやったのはトルストイの「復活」である。「復活」は言うまでもなくトルストイの小説である。「復活」はあくまでも小説として読むべき時間経過を持ったもので到底短時間の演劇でその神髄を伝え得られるものではない。然るに芸術座はこの小説のホンの筋だけをとって、これを芝居にデッチあげて、その上それへ「カチューシャ可愛いや別れのつらさ」というセンチメンタルな唄を仕込んだのである。
何よりも当ったのはこの「カチューシャの唄」であった。それがいけなかった。これが芸術座を亡ぼしたのだ。それからというもの、芸術座は何か一つの芝居をやるたびに必ず歌を入れてそれで当りを取ろうとした。ツルゲーネフの「その前夜」には吉井勇が「ゴンドラの唄」を書いた。「カルメン」には北原白秋が「煙草(たばこ)のめのめ」を書いた。トルストイの「生ける屍」にも同じ白秋の「さすらいの唄」を極めて日本式に改作した。
芸術座が前受けを前受けをと狙う傾向がだんだん露骨になって来た。二元の道はいつの間にか、金儲けという唯一元の道になってしまった。新劇運動が新劇運動としての存在を失うのは、実にこの時である。
この連載は、1953(昭和28)年7月から9月にかけて中国新聞夕刊に掲載した「続がんす横丁」(第1部)の復刻です。旧漢字は新漢字とし、読みにくい箇所にルビを付けました。表現は原則として当時のままとしています。
(2020年1月19日中国新聞セレクト掲載)
芸術座の広島初乗込みは大正四年の夏で、三年後の大正七年十一月五日には、芸術座を主宰した島村抱月が肺炎で急逝した。松井須磨子は生きる望みを失って、有楽座でメリメの「カルメン」上演最中、抱月氏の跡を追うて大正八年一月五日、有楽座の楽屋で自殺したことは、十一人座のメンバーにも非常なショックを与えた。
須磨子の自殺については、広島とは関係の深い小山内薫氏が次のような一文を書いているので、参考までにその抜き書きをお伝えしましょう。
芸術座の芝居で一番はやったのはトルストイの「復活」である。「復活」は言うまでもなくトルストイの小説である。「復活」はあくまでも小説として読むべき時間経過を持ったもので到底短時間の演劇でその神髄を伝え得られるものではない。然るに芸術座はこの小説のホンの筋だけをとって、これを芝居にデッチあげて、その上それへ「カチューシャ可愛いや別れのつらさ」というセンチメンタルな唄を仕込んだのである。
何よりも当ったのはこの「カチューシャの唄」であった。それがいけなかった。これが芸術座を亡ぼしたのだ。それからというもの、芸術座は何か一つの芝居をやるたびに必ず歌を入れてそれで当りを取ろうとした。ツルゲーネフの「その前夜」には吉井勇が「ゴンドラの唄」を書いた。「カルメン」には北原白秋が「煙草(たばこ)のめのめ」を書いた。トルストイの「生ける屍」にも同じ白秋の「さすらいの唄」を極めて日本式に改作した。
芸術座が前受けを前受けをと狙う傾向がだんだん露骨になって来た。二元の道はいつの間にか、金儲けという唯一元の道になってしまった。新劇運動が新劇運動としての存在を失うのは、実にこの時である。
この連載は、1953(昭和28)年7月から9月にかけて中国新聞夕刊に掲載した「続がんす横丁」(第1部)の復刻です。旧漢字は新漢字とし、読みにくい箇所にルビを付けました。表現は原則として当時のままとしています。
(2020年1月19日中国新聞セレクト掲載)