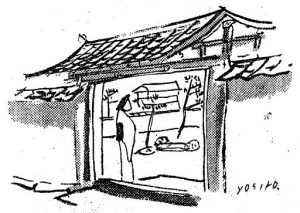「がんす横丁」シリーズ 續がんす横丁 (三十三)材木町(その4)伝福寺の俳諧師たち㊥
20年9月13日
文・薄田太郎 え・福井芳郎
多賀庵二世六合は、初代が船板でこしらえた「多賀庵」の看板を石に改造して初代の旧居に住んだというが、二代目の人気は初代にも増したものであった。
人となりは、篤実考徳と言われて、家産は衰えながらも母への孝養を忘れなかったために、天明七(1787)年藩公から賞をもらったといい、「芸備孝義伝」中の一人であった。
そして彼自身が選んだ句集「ひさご苗集」は、当時好事家に喜ばれたものと言われるが、享和二(1802)年二月十九日、八十歳で病没した。
二世の句には「今日までは耳も聞えて時鳥」が知られており、また芭蕉翁百年忌の句には「百とせのけふにあふみの時雨かな」と詠んでいる。
多賀庵三世玄蛙は山県郡有田の出身で、姓は小田、名は黙居と言い、字は春琳と言われた。
元来は医者で、広島に出て開業し、同好の士から推されて多賀庵の三世を継いだが、後に自分で多賀庵を出て元安川の畔に住み、合歓廼家(ねむのや)という号を名乗ったという。
後に彼は諸国巡歴を思いたって、山陰地方を振り出しに東北地方までの旅を重ねて、各地同好の士と交わりを結んだと言われる。彼には俳諧についての著書もあって、天保六(1835)年、六十四歳で亡くなったと言われる。彼の句には「散る外の癖なし花の吉野山」「蝶鳥につけ回されて傀儡師」がある。
また、多賀庵四世筵史は二世六合の養子となり、通称は宗七と呼ばれた。長年、広島の十日市町に住んで茶業を商ったと言われる。弘化三(1846)年四月二十七日に亡くなった。享年七十四であった。「一あらし過ぎけり露の落ちる音」は彼の最後の句といわれている。
この連載は、1953(昭和28)年7月から9月にかけて中国新聞夕刊に掲載した「続がんす横丁」(第1部)の復刻です。旧漢字は新漢字とし、読みにくい箇所にルビを付けました。表現は原則として当時のままとしています。
(2020年9月13日中国新聞セレクト掲載)
多賀庵二世六合は、初代が船板でこしらえた「多賀庵」の看板を石に改造して初代の旧居に住んだというが、二代目の人気は初代にも増したものであった。
人となりは、篤実考徳と言われて、家産は衰えながらも母への孝養を忘れなかったために、天明七(1787)年藩公から賞をもらったといい、「芸備孝義伝」中の一人であった。
そして彼自身が選んだ句集「ひさご苗集」は、当時好事家に喜ばれたものと言われるが、享和二(1802)年二月十九日、八十歳で病没した。
二世の句には「今日までは耳も聞えて時鳥」が知られており、また芭蕉翁百年忌の句には「百とせのけふにあふみの時雨かな」と詠んでいる。
多賀庵三世玄蛙は山県郡有田の出身で、姓は小田、名は黙居と言い、字は春琳と言われた。
元来は医者で、広島に出て開業し、同好の士から推されて多賀庵の三世を継いだが、後に自分で多賀庵を出て元安川の畔に住み、合歓廼家(ねむのや)という号を名乗ったという。
後に彼は諸国巡歴を思いたって、山陰地方を振り出しに東北地方までの旅を重ねて、各地同好の士と交わりを結んだと言われる。彼には俳諧についての著書もあって、天保六(1835)年、六十四歳で亡くなったと言われる。彼の句には「散る外の癖なし花の吉野山」「蝶鳥につけ回されて傀儡師」がある。
また、多賀庵四世筵史は二世六合の養子となり、通称は宗七と呼ばれた。長年、広島の十日市町に住んで茶業を商ったと言われる。弘化三(1846)年四月二十七日に亡くなった。享年七十四であった。「一あらし過ぎけり露の落ちる音」は彼の最後の句といわれている。
この連載は、1953(昭和28)年7月から9月にかけて中国新聞夕刊に掲載した「続がんす横丁」(第1部)の復刻です。旧漢字は新漢字とし、読みにくい箇所にルビを付けました。表現は原則として当時のままとしています。
(2020年9月13日中国新聞セレクト掲載)