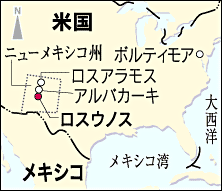知られざるヒバクシャ 劣化ウラン弾の実態 第1部 超大国の陰 米国 <1> 誤射 体中に破片食い込む 骨がん?苦闘の日々
00年4月4日
一九九一年の湾岸戦争で、軍事超大国アメリカを軸にした多国籍軍は、圧倒的戦力でイラク軍を撃破した。米軍の戦闘による戦死者は百四十八人。戦争は短期間で終結した。凱旋(がいせん)した夫や妻、息子や娘の無事をともに喜び合うはずだった留守家族。が、その喜びもつかの間、帰還米兵の多くが体の不調を訴え、命をも失っていった。放射能兵器の劣化ウラン弾などが、体を侵していったのである。(田城明、写真も)
ニューメキシコ州最大の都市アルバカーキ市から南へ約七十キロ。ロスウノス町の新興住宅街にジェリー・ウィートさん(32)の家はあった。
週末の午前十時。妻のレベッカさん(30)に起こされたウィートさんは、肩まで伸びた金髪を後ろで束ねながら、二階から下りてきた。アルバカーキ中央郵便局の職員。前日も夜勤で深夜の帰宅だった。
「あの戦争以来、体調が狂ってしまった。腹痛や関節の痛み。今は左腕のここが一番気になるんだ」。食堂のいすに腰を下ろした彼は、Tシャツのそでをまくり上げ、傷口に目をやった。
九八年十一月、アルバカーキ退役軍人病院で骨の一部を取り出した際の手術痕である。医師たちは、腕の痛みを訴えるウィートさんの骨の生体組織検査を九月に実施。二カ月後に手術をし、切り取った骨の部分に金属を埋め込んだ。
「骨に腫瘍(しゅよう)ができていたんだ。劣化ウランの影響に違いない。でも、病院は認めようとしない。『がんじゃないけど、取り出すだけ』だって」
自軍の戦車で被弾
ウィートさんには、劣化ウランが原因だとするだけの確信があった。湾岸戦争での地上戦が始まって三日目の九一年二月二十六日。ひどい砂あらしの中、戦闘用装甲車でイラク南部を進攻中にイラク軍と遭遇、交戦中に二度砲弾が命中した。いずれも自軍戦車からの誤射によるものだった。
ドライバーのウィートさんは最初の砲撃でしばらく意識を失った。気がつくと、着衣が燃えていた。防弾チョッキなどを急いで脱いだ直後、再び目前で火柱が上がる。体中が焼けるように熱かった。首、背中、腰…。劣化ウラン弾の破片が体内に食い込み、皮膚組織を焼いた。装甲車はそれでも走り、野戦病院までたどり着く。
除隊後に事実知る
「救出した五人を含め、九人全員が奇跡的に生きていた」。翌日、医師たちが深さ一~二センチまで彼の体に食い込んだ破片を取り出した。二十五個以上でてきた。治療後、友軍による誤射の事実は知らされぬまま、汚染された装甲車に戻る。そして駐留先のドイツに戻る三月初旬まで、隊とともに行動した。
誤射と知ったのは、除隊後の九二年三月。ロスアラモス国立研究所に勤務する父が、息子が持ち帰った破片をガイガーカウンターで調べ、放射能を帯びていることが分かったのだ。
「ひどい話さ。九三年にボルティモアの退役軍人病院で尿検査を受けたら、劣化ウランが検出された。でも、正常の範囲だっていう」
体内に取り込まれた劣化ウラン粒子は、肺や腎臓(じんぞう)、やがては血液を通じて骨にもたまるといわれる。ウィートさんは、検査や手術の際に「民間の研究機関でも、取り出した組織や骨を分析してもらいたい」と、病院側に強く要望した。しかし、聞き入れてはもらえなかった。
頭や腕に今も破片
後頭部と右腕には、まだ一個ずつ劣化ウラン弾の破片が残っている、という。毎日、鎮痛剤を取りながらの生活が続く。
「がんでなければ骨を切り取ったりはしないさ。でも、まだ負けるわけにはいかない。子どもが二人もいるからね」。ウィートさんはそう言って、隣の部屋で遊ぶ長男のジョセフちゃん(9つ)と二男のデレックちゃん(3つ)を見やった。
(2000年4月4日朝刊掲載)
ニューメキシコ州最大の都市アルバカーキ市から南へ約七十キロ。ロスウノス町の新興住宅街にジェリー・ウィートさん(32)の家はあった。
週末の午前十時。妻のレベッカさん(30)に起こされたウィートさんは、肩まで伸びた金髪を後ろで束ねながら、二階から下りてきた。アルバカーキ中央郵便局の職員。前日も夜勤で深夜の帰宅だった。
「あの戦争以来、体調が狂ってしまった。腹痛や関節の痛み。今は左腕のここが一番気になるんだ」。食堂のいすに腰を下ろした彼は、Tシャツのそでをまくり上げ、傷口に目をやった。
九八年十一月、アルバカーキ退役軍人病院で骨の一部を取り出した際の手術痕である。医師たちは、腕の痛みを訴えるウィートさんの骨の生体組織検査を九月に実施。二カ月後に手術をし、切り取った骨の部分に金属を埋め込んだ。
「骨に腫瘍(しゅよう)ができていたんだ。劣化ウランの影響に違いない。でも、病院は認めようとしない。『がんじゃないけど、取り出すだけ』だって」
自軍の戦車で被弾
ウィートさんには、劣化ウランが原因だとするだけの確信があった。湾岸戦争での地上戦が始まって三日目の九一年二月二十六日。ひどい砂あらしの中、戦闘用装甲車でイラク南部を進攻中にイラク軍と遭遇、交戦中に二度砲弾が命中した。いずれも自軍戦車からの誤射によるものだった。
ドライバーのウィートさんは最初の砲撃でしばらく意識を失った。気がつくと、着衣が燃えていた。防弾チョッキなどを急いで脱いだ直後、再び目前で火柱が上がる。体中が焼けるように熱かった。首、背中、腰…。劣化ウラン弾の破片が体内に食い込み、皮膚組織を焼いた。装甲車はそれでも走り、野戦病院までたどり着く。
除隊後に事実知る
「救出した五人を含め、九人全員が奇跡的に生きていた」。翌日、医師たちが深さ一~二センチまで彼の体に食い込んだ破片を取り出した。二十五個以上でてきた。治療後、友軍による誤射の事実は知らされぬまま、汚染された装甲車に戻る。そして駐留先のドイツに戻る三月初旬まで、隊とともに行動した。
誤射と知ったのは、除隊後の九二年三月。ロスアラモス国立研究所に勤務する父が、息子が持ち帰った破片をガイガーカウンターで調べ、放射能を帯びていることが分かったのだ。
「ひどい話さ。九三年にボルティモアの退役軍人病院で尿検査を受けたら、劣化ウランが検出された。でも、正常の範囲だっていう」
体内に取り込まれた劣化ウラン粒子は、肺や腎臓(じんぞう)、やがては血液を通じて骨にもたまるといわれる。ウィートさんは、検査や手術の際に「民間の研究機関でも、取り出した組織や骨を分析してもらいたい」と、病院側に強く要望した。しかし、聞き入れてはもらえなかった。
頭や腕に今も破片
後頭部と右腕には、まだ一個ずつ劣化ウラン弾の破片が残っている、という。毎日、鎮痛剤を取りながらの生活が続く。
「がんでなければ骨を切り取ったりはしないさ。でも、まだ負けるわけにはいかない。子どもが二人もいるからね」。ウィートさんはそう言って、隣の部屋で遊ぶ長男のジョセフちゃん(9つ)と二男のデレックちゃん(3つ)を見やった。
(2000年4月4日朝刊掲載)