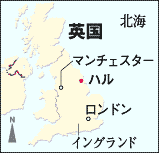知られざるヒバクシャ 劣化ウラン弾の実態 第4部 同盟国の重荷 英国 <1> 国防義勇隊員 「国に奉仕」重い代償 体力衰え死を予感
00年6月2日
一九九一年の湾岸戦争で英国は、米国に次ぐ五万三千人の兵力を中東へ派遣した。うち約三万人が前線や周辺の砂漠地帯に駐留。同盟国の米軍とともに、イラク軍に劣化ウラン弾を使った。交戦に伴う英軍の戦死者は四十九人。多国籍軍は圧倒的勝利を収めた。だが九年が過ぎた今、退役兵の死者は交戦時の十倍に達し、病状を訴える者は六千人に上る。退役兵らは劣化ウラン被曝(ばく)などに伴う病気の認知を国から得られぬまま、苦難の日々を送る。(田城明、写真も)
ロンドンから北へ約三百キロ。かつて漁港として栄えたイングランド中東部のハル市は、北海にほど近いハンバー川河口にあった。人口二十五万人の市北部住宅地にレイ・ブリストウさん(42)を訪ねた。
2カ月の湾岸体験
「足がすっかり弱くなってね。随分前から支えがないと歩けないんだ」。出迎えてくれたブリストウさんは、つえを支えに居間に向かい、ソファに腰を下ろした。「わずか二カ月余りの湾岸体験で、自分の体じゃなくなってしまった」。ゆっくりとした口調に、悔しさがにじむ。
高校卒業後、社交ダンスのインストラクターの資格を取って夜間に教える傍ら、昼間は医療技術者として地元の病院の救急室で働いた。「国にも奉仕したい」と、十七歳で国防義勇隊に登録。週末などに訓練を受けた。
イラクがクウェートに侵攻して三カ月後の一九九〇年十一月、「医療班スタッフとして中東へ出向いてほしい」と要請があった。
「救急医療現場での経験と軍事訓練の積み重ねを生かし、今こそ国に奉仕する時」。妻で看護婦のデボラさん(35)に相談することもなく参戦を決意。幼かったレイチェルさん(14)とクレアさん(12)の二人の娘を残し、九一年一月初旬、サウジアラビアへ飛んだ。
イラク国境近くに二百床の野戦病院を設営し、負傷兵の治療に当たった。「運ばれてくるのはほとんどがイラク兵。特に地上戦(二月二十四日~二十八日)の間は、足が切断されたり、内臓が飛び出した兵士などひどいものだった」。脱がせた服からは、ほこりが舞い上がった。
むごい光景は救急医療室で見慣れており、ショックを受けるというほどではなかった。「ただ戦争前までは健康だった若者が負傷を負い、死んでいくのが悲しかった。目前の現実が、戦争の代償の大きさを突きつけてきた」。その時の様子を思い出し、目を潤ませるブリストウさんには当時なお、自身の健康喪失までが代償に含まれているとは思いも及ばなかった。
帰国と同時に発病
体調の悪化は、三月十五日の帰国とほぼ同時に始まった。頭痛、全身疲労、胃腸障害…。湾岸戦争に伴う疾病について何の情報もなかった。九三年になり、病院でたまたま手にした女性雑誌の記事が目に留まった。「一人の湾岸戦争退役兵の病状について触れていた。まるで自分のことが書かれているようで…」
妻にもその記事を見せ、病気の原因と治療法を探る夫妻の努力が始まった。体調悪化で病院勤務を断念した九六年、カナダの専門家に尿検査を頼んだ。高レベルの劣化ウランが検出された。
「前線から離れていたので驚いたよ。きっと負傷したイラク兵の服などに付着した劣化ウラン粒子を、体内に大量に取り込んだに違いない」。あの時のほこりを思い出した。国防省に問い合わせても「心配はいらない」の一点張り。何の解決にもならなかった。
先は「スローな死」
食事療法とさまざまな薬の摂取。それでも年々体力は衰え、関節痛も増すばかり。記憶力の喪失も激しくなってきた。「今では死の順番を待っているようなもの。ヒロシマ、ナガサキのスローな死と同じだよ…」
希望の見えない闘病生活。「妻と成長した娘が自分の状態を理解してくれるようになったのが唯一の救い」。ブリストウさんは、学校から帰宅したばかりの二人に笑みを送った。
(2000年6月2日朝刊掲載)
ロンドンから北へ約三百キロ。かつて漁港として栄えたイングランド中東部のハル市は、北海にほど近いハンバー川河口にあった。人口二十五万人の市北部住宅地にレイ・ブリストウさん(42)を訪ねた。
2カ月の湾岸体験
「足がすっかり弱くなってね。随分前から支えがないと歩けないんだ」。出迎えてくれたブリストウさんは、つえを支えに居間に向かい、ソファに腰を下ろした。「わずか二カ月余りの湾岸体験で、自分の体じゃなくなってしまった」。ゆっくりとした口調に、悔しさがにじむ。
高校卒業後、社交ダンスのインストラクターの資格を取って夜間に教える傍ら、昼間は医療技術者として地元の病院の救急室で働いた。「国にも奉仕したい」と、十七歳で国防義勇隊に登録。週末などに訓練を受けた。
イラクがクウェートに侵攻して三カ月後の一九九〇年十一月、「医療班スタッフとして中東へ出向いてほしい」と要請があった。
「救急医療現場での経験と軍事訓練の積み重ねを生かし、今こそ国に奉仕する時」。妻で看護婦のデボラさん(35)に相談することもなく参戦を決意。幼かったレイチェルさん(14)とクレアさん(12)の二人の娘を残し、九一年一月初旬、サウジアラビアへ飛んだ。
イラク国境近くに二百床の野戦病院を設営し、負傷兵の治療に当たった。「運ばれてくるのはほとんどがイラク兵。特に地上戦(二月二十四日~二十八日)の間は、足が切断されたり、内臓が飛び出した兵士などひどいものだった」。脱がせた服からは、ほこりが舞い上がった。
むごい光景は救急医療室で見慣れており、ショックを受けるというほどではなかった。「ただ戦争前までは健康だった若者が負傷を負い、死んでいくのが悲しかった。目前の現実が、戦争の代償の大きさを突きつけてきた」。その時の様子を思い出し、目を潤ませるブリストウさんには当時なお、自身の健康喪失までが代償に含まれているとは思いも及ばなかった。
帰国と同時に発病
体調の悪化は、三月十五日の帰国とほぼ同時に始まった。頭痛、全身疲労、胃腸障害…。湾岸戦争に伴う疾病について何の情報もなかった。九三年になり、病院でたまたま手にした女性雑誌の記事が目に留まった。「一人の湾岸戦争退役兵の病状について触れていた。まるで自分のことが書かれているようで…」
妻にもその記事を見せ、病気の原因と治療法を探る夫妻の努力が始まった。体調悪化で病院勤務を断念した九六年、カナダの専門家に尿検査を頼んだ。高レベルの劣化ウランが検出された。
「前線から離れていたので驚いたよ。きっと負傷したイラク兵の服などに付着した劣化ウラン粒子を、体内に大量に取り込んだに違いない」。あの時のほこりを思い出した。国防省に問い合わせても「心配はいらない」の一点張り。何の解決にもならなかった。
先は「スローな死」
食事療法とさまざまな薬の摂取。それでも年々体力は衰え、関節痛も増すばかり。記憶力の喪失も激しくなってきた。「今では死の順番を待っているようなもの。ヒロシマ、ナガサキのスローな死と同じだよ…」
希望の見えない闘病生活。「妻と成長した娘が自分の状態を理解してくれるようになったのが唯一の救い」。ブリストウさんは、学校から帰宅したばかりの二人に笑みを送った。
(2000年6月2日朝刊掲載)