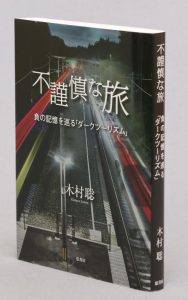『書評』 不謹慎な旅 木村聡著 過去・現在の影を観る
22年5月16日
「Go To」とやらの再開を見越してパック旅行のPRが目立つ。だが何事もなかったかのように、人はコロナ前の日常に果たして戻れるのだろうか。フォトジャーナリストの著者が名付けた「不謹慎な旅」こそ時代が求めているような気がするのだ。
著者の旅は「負の記憶」をたどる。光だけではなく、影も観(み)る「観影」への誘いだ。40カ所にも及ぶ旅先を全て挙げることはできないが、例えば「麻薬大国ニッポン」と題したページを開くと…。
著者はケシが研究用に栽培される東京都薬用植物園を訪ねる。厳重な管理体制に「麻薬大国」を想像できないが、戦前の日本ではケシ畑は絵はがきになる名所だった。著者は和歌山県で「ケシ採り、昔よー行った。カゴを首に下げて、ヘラで採ったのをこうこすりつけてな」という証言を銭湯の客から得る。収穫を手伝うと授業は休み。子どもには楽しい思い出だった。
そのケシはやがてアヘンと化して統治していた台湾などで利益を生み、戦費となる。大阪府のある村では「国家財政を助けるために国内自給すべし」と栽培に奔走する人物もいたという。麻薬ビジネスは決して異国の暗黒社会の専売特許ではなかったことを知る、過去への旅である。
ヒロシマの地も踏んだ。原爆慰霊碑の碑文の「主語」はかつて論争の火種となった。あろうことか、碑は今なお塗料をまかれるなど犯罪行為にさらされる。主語は誰なのか―。著者は碑前で人々に意見を聞き、最も琴線に触れたのは「ひとりひとりだと思います」と答えた修学旅行中の小学生の一言だったという。
著者は戦前の日本の原爆開発計画に触れ、ウランを含む鉱石を採取していた福島県石川町を訪ねる。ここでも子どもたちが動員された。人は過ちと気付かずに過ちに加担することもある。無関係に思える旅はどこかで結び付く。
俗に言う「自殺の名所」も旅先。風光明媚(めいび)な土地土地で人は命を救う手だてを模索していた。得難い旅人のまなざしを通じて知る、ニッポン内外の過去と現在である。(佐田尾信作・客員特別編集委員)
弦書房・2200円
(2022年5月15日朝刊掲載)
著者の旅は「負の記憶」をたどる。光だけではなく、影も観(み)る「観影」への誘いだ。40カ所にも及ぶ旅先を全て挙げることはできないが、例えば「麻薬大国ニッポン」と題したページを開くと…。
著者はケシが研究用に栽培される東京都薬用植物園を訪ねる。厳重な管理体制に「麻薬大国」を想像できないが、戦前の日本ではケシ畑は絵はがきになる名所だった。著者は和歌山県で「ケシ採り、昔よー行った。カゴを首に下げて、ヘラで採ったのをこうこすりつけてな」という証言を銭湯の客から得る。収穫を手伝うと授業は休み。子どもには楽しい思い出だった。
そのケシはやがてアヘンと化して統治していた台湾などで利益を生み、戦費となる。大阪府のある村では「国家財政を助けるために国内自給すべし」と栽培に奔走する人物もいたという。麻薬ビジネスは決して異国の暗黒社会の専売特許ではなかったことを知る、過去への旅である。
ヒロシマの地も踏んだ。原爆慰霊碑の碑文の「主語」はかつて論争の火種となった。あろうことか、碑は今なお塗料をまかれるなど犯罪行為にさらされる。主語は誰なのか―。著者は碑前で人々に意見を聞き、最も琴線に触れたのは「ひとりひとりだと思います」と答えた修学旅行中の小学生の一言だったという。
著者は戦前の日本の原爆開発計画に触れ、ウランを含む鉱石を採取していた福島県石川町を訪ねる。ここでも子どもたちが動員された。人は過ちと気付かずに過ちに加担することもある。無関係に思える旅はどこかで結び付く。
俗に言う「自殺の名所」も旅先。風光明媚(めいび)な土地土地で人は命を救う手だてを模索していた。得難い旅人のまなざしを通じて知る、ニッポン内外の過去と現在である。(佐田尾信作・客員特別編集委員)
弦書房・2200円
(2022年5月15日朝刊掲載)