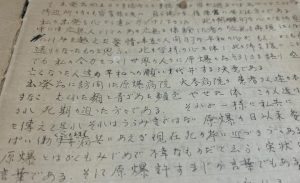広島サミット原点の地で <2> 残ったケロイド
23年2月11日
差別続く日々 心にも傷
あれから78年になる今も右手の指は変形し、口元はゆがんだままだ。18歳で被爆した阿部静子さん(95)=広島市南区=は、原爆の熱線に生涯刻まれた傷痕を顔や体に抱え、反戦、反核を訴えてきた。「原爆で見苦しい姿になった。子どもたちに同じ思いをさせたくない、その一念でした」
1945年8月6日朝、中野村(現安芸区)から平塚町(現中区)へ建物疎開作業に動員され、被爆した。爆心地から約1・5キロ。屋根上から10メートル吹き飛ばされた。「気付いた時には辺りが薄暗く、皮膚が焼けた臭いがした」
繰り返し手術も
熱線で顔は焼けただれ、右腕の皮は爪の先までむけて垂れ下がった。その腕を胸の前に上げ、皮膚をぶら下げながら歩いて逃げた。人相が変わり、臨時救護所に迎えに来た父は、わが子だとなかなか信じてくれなかった。
自宅で母親と姉の懸命な看病を受け、生き延びた。やけどにいいと聞き、すりおろしたジャガイモを顔に塗布。ようやく痛みが引いても、やけどした皮膚は盛り上がり、顔は真っ赤に腫れた。目や口が引きつり、食べ物も唾液もこぼれる。日常生活がままならない状態が続いた。
終戦から4カ月後に、9歳上の夫、三郎さん(92年に73歳で死去)が南方から復員。離婚も覚悟していた妻を「自分も戦地で手足を失っていたかもしれない」と温かく包んだ。
阿部さんは被爆翌年、長男の妊娠を機に現在の広島県立広島病院(南区)に3カ月ほど入院し、皮膚の移植手術を繰り返し受けた。ただ、ケロイドは消えてくれなかった。近所の子どもに「赤鬼」とはやし立てられ、街中で擦れ違う人に奇異の目を向けられる。同居するしゅうとめには、夫の陰で離婚を迫られた。「心をえぐられ、何度も死にたいと思いました」
泣き暮らす日々に、夫や3人の子どもと共に支えになったのは同じ境遇の被爆者仲間だ。「原爆1号」と呼ばれた吉川清さん(86年に74歳で死去)たちと親交を深め、56年に「原爆の生き証人」として被爆者援護を求める国会請願団に加わった。前年には、広島で被爆した独身女性25人がケロイド治療のために渡米。国内外のメディアを通じ「原爆乙女」「ヒロシマ・ガールズ」の存在が、広く知られるようになった。
「巡礼」先で証言
米ソ冷戦下の64年、阿部さんにも渡米の機会が訪れる。米国出身の平和活動家バーバラ・レイノルズさんが提唱した「世界平和巡礼」で約3カ月間、米国や旧ソ連、欧州の各国を回って証言した。
出発時の日記には「全力を尽くし、むなしく苦しみ亡くなった人たちの平和への願いを代弁する」という決意をつづった。米国でトルーマン元大統領との面会に同行し、在職中の原爆投下を必要悪とした姿勢に失望。帰国後、平和運動や証言活動にさらにまい進するようになった。
数年前から高齢者施設で暮らす。被爆地である先進7カ国首脳会議(G7サミット)を前に、30分の面会時間で取材に応じた。「世界中が人殺しの競争ばかりして、地球が駄目になる。首脳たちは『絶対この世で核兵器を使わない』と心に決めてお帰りいただきたい」(桑島美帆)
(2023年2月13日朝刊掲載)