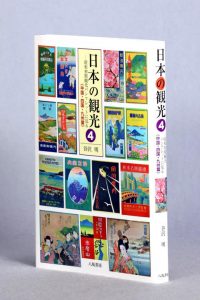「聖地の発見」 庶民の関心事 昭和初期の観光案内図 中国地方分まとめ刊行 広島や尾道 吉田初三郎らの絵図を収録
23年7月1日
民俗学者宮本常一の門下で愛知淑徳大名誉教授の谷沢明さんが「日本の観光4 昭和初期観光パンフレットに見る≪中国・四国・九州篇≫」を著した。鳥瞰(ちょうかん)図の手法を用いてデフォルメされた観光案内図をふんだんに収録し、かつての「善男善女」たちの心持ちを思い起こさせてくれよう。
谷沢さんは愛知県東浦町郷土資料館が所蔵する「服部徳次郎氏旧蔵コレクション」などを活用し、とかく旅を終えると捨てられる観光案内を地域ごとに分類。「大正の広重」と呼ばれ、広島への原爆投下の瞬間を描いた鳥瞰図でも知られる絵師吉田初三郎らの絵図を収録した。本書はシリーズ第4巻で中国地方は「鳥取・松江・出雲」「岡山・広島・尾道」「萩・山口・秋芳洞」に章立てした。
松江・出雲の観光案内図には今はない「中海宍道湖航路」が見える。松江大橋を起点に六つの路線が湖面を行き交い、一畑軽便鉄道小境灘駅(当時)下船で山上の一畑薬師に参詣する船便もあったようだ。今のように湖岸に沿って鉄道や車で往来するのとは違う景色が見えたことだろう。
吉田の作になる「宮島広島名所図絵」も現代人には新鮮に映るのではないか。太田川下流のデルタに立地する「水都」の印象を強く打ち出し、元宇品、江波、草津が行楽地であること、「大本営跡」以外の軍施設は明示されていないことなどが分かる。同じ吉田の作「尾道市」は向島側から尾道水道越しに山手の町並みを描いていて「海の自然美の眺望台」という、うたい文句と合致している。
谷沢さんは宮本が初代所長を務めた近畿日本ツーリスト日本観光文化研究所で長く活動し、古い町並みや建築に詳しい。出版に当たって絵図に描かれた土地を実際に旅したという。
観光とは何だろう。谷沢さんは「訪れた土地の放つ光に照らされることであろう。その輝きが、わが身を浄化させてくれる」と後書きで述べている。生きる力が湧き出るような「聖地の発見」が庶民の一大関心事だった時代があった。
八坂書房刊、A5判変型256ページ、3080円。宮島や福山市・鞆の浦は第1巻に当たる「日本の観光」の「瀬戸内海を巡る船旅」で詳述している。(客員特別編集委員・佐田尾信作)
(2023年7月1日朝刊掲載)
谷沢さんは愛知県東浦町郷土資料館が所蔵する「服部徳次郎氏旧蔵コレクション」などを活用し、とかく旅を終えると捨てられる観光案内を地域ごとに分類。「大正の広重」と呼ばれ、広島への原爆投下の瞬間を描いた鳥瞰図でも知られる絵師吉田初三郎らの絵図を収録した。本書はシリーズ第4巻で中国地方は「鳥取・松江・出雲」「岡山・広島・尾道」「萩・山口・秋芳洞」に章立てした。
松江・出雲の観光案内図には今はない「中海宍道湖航路」が見える。松江大橋を起点に六つの路線が湖面を行き交い、一畑軽便鉄道小境灘駅(当時)下船で山上の一畑薬師に参詣する船便もあったようだ。今のように湖岸に沿って鉄道や車で往来するのとは違う景色が見えたことだろう。
吉田の作になる「宮島広島名所図絵」も現代人には新鮮に映るのではないか。太田川下流のデルタに立地する「水都」の印象を強く打ち出し、元宇品、江波、草津が行楽地であること、「大本営跡」以外の軍施設は明示されていないことなどが分かる。同じ吉田の作「尾道市」は向島側から尾道水道越しに山手の町並みを描いていて「海の自然美の眺望台」という、うたい文句と合致している。
谷沢さんは宮本が初代所長を務めた近畿日本ツーリスト日本観光文化研究所で長く活動し、古い町並みや建築に詳しい。出版に当たって絵図に描かれた土地を実際に旅したという。
観光とは何だろう。谷沢さんは「訪れた土地の放つ光に照らされることであろう。その輝きが、わが身を浄化させてくれる」と後書きで述べている。生きる力が湧き出るような「聖地の発見」が庶民の一大関心事だった時代があった。
八坂書房刊、A5判変型256ページ、3080円。宮島や福山市・鞆の浦は第1巻に当たる「日本の観光」の「瀬戸内海を巡る船旅」で詳述している。(客員特別編集委員・佐田尾信作)
(2023年7月1日朝刊掲載)