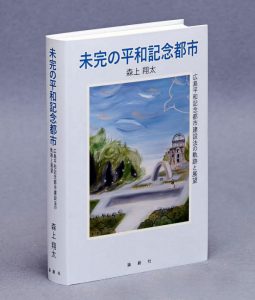平和都市法 今日的意義を問う 広島市職員の森上翔太さん 研究を基に本出版
24年8月9日
市民との対話・協働 理念の根幹
75年前の8月6日、公布施行された「広島平和記念都市建設法」。被爆地の「復興の礎」とされ、広島が「平和都市」たる法的根拠でもあるが、現在の私たちにどれだけなじみがあるだろう。広島市職員の森上翔太さん(40)が法律学の視点から同法を究め、「未完の平和記念都市―広島平和記念都市建設法の軌跡と展望」(写真・論創社)にまとめた。史料を丹念に調べて制定過程や込められた理念に迫り、今日的意義を問い直している。(森田裕美)
平和都市法は、広島市を「恒久の平和を誠実に実現しようとする理想の象徴」とするため、憲法95条に基づく住民投票を経て制定された全国初の地方特別法である。平和関連施設の整備への国の支援や旧軍用地の無償譲与などが規定され、平和記念公園整備の礎にもなったが、復興の完成とともに役割を終えたと見る向きが強い。
「この法律が忘れ去られてしまうのはもったいない」。そんな思いから森上さんは、500ページ余りに及ぶ本書で、同法がどのように生まれどう運用されたか、そもそも同法のいう「平和記念都市」とは何か、史料や文献を掘り起こし、法解釈や地方特別法としての独自性、国際的な位置づけなど包括的に探究した。
広島市出身の森上さんは東京大で国際関係論を学び、同大大学院法学政治学研究科を修了。衆議院法制局で立法の専門家として働いた。2016~17年には英ケンブリッジ大に客員研究員として籍を置き、研究の奥深さにも触れた。国内外での経験を得て古里への思いが強まり、5年前、市職員に転じた。
折しも21年、市立大大学院平和学研究科に博士後期課程が新設。平和都市法を研究テーマに据えると指導教員の永井均教授に「世に問うべき研究だ」と背中を押された。
平日は仕事をしながら休日に国会図書館などに通い、手探りで膨大な資料に当たる日々。今年3月まで2年間、外務省に出向し東京赴任していたのも首都圏での調査には幸いした。「一日図書館にいても何も得られない日も少なくなかった」が、新資料も発見した。
制定過程では、市公文書館に残る複数の草案を分析。同法の設計者は当時参院議事部長の寺光忠氏というのが通説だが、参院法制局課長だった枚田四郎右衛門氏の可能性が高いことを指摘した。同法への連合国軍総司令部(GHQ)の関与についてはマッカーサー最高司令官の副官であるバンカー大佐と任都栗司市議会議長(当時)が面会した事実も突き止めた。
全編を通し緻密な調査に圧倒されるが、白眉は同法が現在の市政や市民にとってどんな意味を持つかを検討した終盤だろう。森上さんは同法の存在意義をとりわけ第6条に見いだす。
≪広島市の市長は、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、広島平和記念都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない≫
この6条の規定から「市長と市民の対話を通じた協働関係の構築」の重要性を読み解く。同法の意義は「『平和記念都市』とは何か、という明確に規定されていない内容にこそあるのでは」と森上さん。
「平和都市」を名乗る地は世界に数あるが、森上さんの調査によれば法律で定められているのは広島市だけである。「平和都市法の軌跡をたどれば軍都・広島の歴史や復興に向けた先人たちのたゆまぬ努力が浮かび上がる」。時を経て同法にふたたび目が向けられることを願う。
(2024年8月9日朝刊掲載)