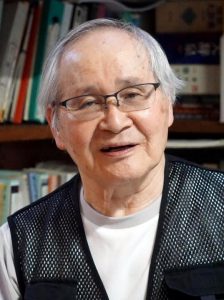探訪 まちの赤れんが <5> 保存と活用を聞く
24年8月21日
1914年完成の赤れんが建物で広島市最大級の被爆建物「旧陸軍被服支廠(ししょう)」(南区)は築110年だ。全国に点在する築100年超の赤れんが建物の保存と活用に向けたポイントは何か。2002年の開館で年800万人余りを集客する「横浜赤レンガ倉庫」(横浜市)の改修に携わった建築家と、初期に運営を担った元経営者に考えを聞いた。(樋口浩二)
集客 官民で役割分担を
キリンビールを中心に2000年7月に設立しした運営会社「横浜赤レンガ」の初代社長を務めた。巨大な倉庫だけに初期投資はかさみ、飲食店の入る2号館の改装費は38億円に。40年ほどで回収するスキーム(枠組み)を描いた。重視したのは安定した集客。いかにリピーターをつくれるかが勝負と肝に銘じ、テナント誘致に当たった。
毎年市に払う賃料だけで1億6千万円あり、相当な集客が必要だった。どう「本物」を提供する店舗を集めるか。観光地によくある都市名入りのキーホルダーなどではなく、独自の食品や特産品をそろえた店にこだわった。広島ゆかりのカフェ「チャノマ」のように自ら出店を名乗り出てくれる事業者もあった。
開業7年目に純利益4千万円とようやく黒字に。以降は、利益が伸びた。来場者アンケートの記述をグループ分けし、顧客の心情を分析した。「夜景がきれい」「心が落ち着いてほっとする」など箇条書きして整理し、満足感を高める仕掛けを考えた。結果、来場者の3分の2がリピーターになった。
倉庫前での企画にも注力した。秋のオクトーバーフェストなど季節イベントを軸に、細かい催事を入れ込む。13年に筆頭株主は変わったが、力の入れようは引き継がれている。
横浜市中心部と結ぶ歩道整備やバス路線の創設で市が支えてくれた。インフラ整備は自治体の得意分野。一方で集客には民間が知恵を絞る。官民の役割分担が大切だ。広島の旧陸軍被服支廠の活用にも通じるだろう。築年数や規模が横浜赤レンガ倉庫と似ていて、国重要文化財でもある。人を呼び込む潜在力がある。
むらさわ・あきら
横浜市出身。横浜国立大卒。キリンビールに入社し東京支社マーケティング部長などを経て、1999年に横浜赤レンガ倉庫の開設準備に着手。2000年から08年まで運営会社社長。73歳。
元の姿と利便性を両立
建築家として国内外で3千を超えるプロジェクトに関わった。中でも、横浜赤レンガ倉庫はかなり印象深い仕事の一つだった。改修工事を進めた2000年からの2年間は、毎日のように現場に通った。
私が担ったのは構造設計。あれだけの巨大な倉庫2棟をどう後世に残していくか。貫いたのはできる限りありのままの姿をとどめることだ。
れんがや石などを積み上げる組積造りにはもともとの応力(強さ)がある。コンピューター解析で応力の弱い部分を特定した。その部分を中心に特製の樹脂を注入し、強度を高めた。内観、外観とも完成当初の姿を残すことを心がけた。
人を呼び込むための改修の工夫も施した。芸術、文化向けの1号館は3階の一部をホールにするのが横浜市の注文だった。もともとあった仕切りの壁を取っ払う代わりに、屋根を鉄骨の筋交いで補強するなどして強度を保った。
使われない建物は朽ちていく。広島市の被爆建物「旧陸軍被服支廠」は横浜赤レンガ倉庫とほぼ同世代。多くの人が訪れる活用策を官民で練ることが重要になる。
被爆にも耐え抜いた貴重な建築物。広島県出身の私も思い入れがある。耐震改修に多額のコストがかかるのは当然だが、人を呼び込む活用法が定まれば、民間から資金を集めることが可能だ。横浜がそうだったように。
耐震改修をきっかけによみがえり、多くの人を引き寄せる歴史的建造物は少なくない。後世に残すことで歴史が継がれ、さらに新たな一ページが加わっていく。そうして名建築と呼ばれる地域の宝に育っていくのだと思う。(おわり)
いまがわ・のりひで
尾道市出身。三原工業高(現如水館高)を経て日本大理工学部卒。東京大生産技術研究所などで勤め、1978年に設計事務所を設立。2000年に東京電機大教授。17年から現職。77歳。
(2024年8月21日朝刊掲載)
横浜赤レンガ倉庫運営会社元社長 村沢彰さん
集客 官民で役割分担を
キリンビールを中心に2000年7月に設立しした運営会社「横浜赤レンガ」の初代社長を務めた。巨大な倉庫だけに初期投資はかさみ、飲食店の入る2号館の改装費は38億円に。40年ほどで回収するスキーム(枠組み)を描いた。重視したのは安定した集客。いかにリピーターをつくれるかが勝負と肝に銘じ、テナント誘致に当たった。
毎年市に払う賃料だけで1億6千万円あり、相当な集客が必要だった。どう「本物」を提供する店舗を集めるか。観光地によくある都市名入りのキーホルダーなどではなく、独自の食品や特産品をそろえた店にこだわった。広島ゆかりのカフェ「チャノマ」のように自ら出店を名乗り出てくれる事業者もあった。
開業7年目に純利益4千万円とようやく黒字に。以降は、利益が伸びた。来場者アンケートの記述をグループ分けし、顧客の心情を分析した。「夜景がきれい」「心が落ち着いてほっとする」など箇条書きして整理し、満足感を高める仕掛けを考えた。結果、来場者の3分の2がリピーターになった。
倉庫前での企画にも注力した。秋のオクトーバーフェストなど季節イベントを軸に、細かい催事を入れ込む。13年に筆頭株主は変わったが、力の入れようは引き継がれている。
横浜市中心部と結ぶ歩道整備やバス路線の創設で市が支えてくれた。インフラ整備は自治体の得意分野。一方で集客には民間が知恵を絞る。官民の役割分担が大切だ。広島の旧陸軍被服支廠の活用にも通じるだろう。築年数や規模が横浜赤レンガ倉庫と似ていて、国重要文化財でもある。人を呼び込む潜在力がある。
むらさわ・あきら
横浜市出身。横浜国立大卒。キリンビールに入社し東京支社マーケティング部長などを経て、1999年に横浜赤レンガ倉庫の開設準備に着手。2000年から08年まで運営会社社長。73歳。
東京電機大名誉教授 今川憲英さん
元の姿と利便性を両立
建築家として国内外で3千を超えるプロジェクトに関わった。中でも、横浜赤レンガ倉庫はかなり印象深い仕事の一つだった。改修工事を進めた2000年からの2年間は、毎日のように現場に通った。
私が担ったのは構造設計。あれだけの巨大な倉庫2棟をどう後世に残していくか。貫いたのはできる限りありのままの姿をとどめることだ。
れんがや石などを積み上げる組積造りにはもともとの応力(強さ)がある。コンピューター解析で応力の弱い部分を特定した。その部分を中心に特製の樹脂を注入し、強度を高めた。内観、外観とも完成当初の姿を残すことを心がけた。
人を呼び込むための改修の工夫も施した。芸術、文化向けの1号館は3階の一部をホールにするのが横浜市の注文だった。もともとあった仕切りの壁を取っ払う代わりに、屋根を鉄骨の筋交いで補強するなどして強度を保った。
使われない建物は朽ちていく。広島市の被爆建物「旧陸軍被服支廠」は横浜赤レンガ倉庫とほぼ同世代。多くの人が訪れる活用策を官民で練ることが重要になる。
被爆にも耐え抜いた貴重な建築物。広島県出身の私も思い入れがある。耐震改修に多額のコストがかかるのは当然だが、人を呼び込む活用法が定まれば、民間から資金を集めることが可能だ。横浜がそうだったように。
耐震改修をきっかけによみがえり、多くの人を引き寄せる歴史的建造物は少なくない。後世に残すことで歴史が継がれ、さらに新たな一ページが加わっていく。そうして名建築と呼ばれる地域の宝に育っていくのだと思う。(おわり)
いまがわ・のりひで
尾道市出身。三原工業高(現如水館高)を経て日本大理工学部卒。東京大生産技術研究所などで勤め、1978年に設計事務所を設立。2000年に東京電機大教授。17年から現職。77歳。
(2024年8月21日朝刊掲載)