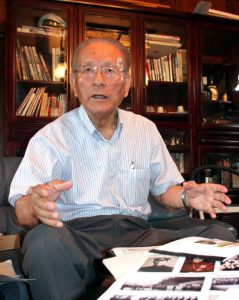回天初出撃80年 <上> 証言
24年11月8日
20歳前後の若者が乗り込み、命を落とした旧日本海軍の特攻兵器「回天」。訓練基地があった周南市大津島を最初の出撃隊がたってから8日で丸80年となる。当時を知る関係者は少なくなり、老いも深めた。証言をいかに受け止め、記憶をつないでいけるか―。私たちに問われている。(井上龍太郎)
終戦間近の島で見た表情を、忘れないでいる。島で育った同市川崎の元高校教諭田中賢一さん(86)。当時、出撃隊を見送った。「皆ええ男で若いお兄ちゃん。精悍(せいかん)な真っ黒の顔ではなく、きれいな顔で。平然としていた」。極秘の作戦。自身は現在でいう小学1年生で、兵士の顔を見ないよう先生に言われた。ただ、我慢できず頭を下げたまま上目遣いに見た。
島に回天の基地ができたのは1944年9月。上部が白く塗られた「魚雷」と高速艇が徳山湾や周防灘を行き来する訓練を、自宅や山から見ながら過ごしていた。
魚雷と思っていた機体が特攻兵器と知ったのは戦後だった。田中さんは島を離れて教員に。郷土史研究会の会長を務め、体験も記してきた。「1週間後には死なないといけない状況に置かれた若者が、どうしてあんなにも平然としていられたのか。胸の内はどんな思いだったのか」。表情を思い浮かべ、つぶやいた。
周防灘に浮かぶ約4・7平方キロの島。戦時下の様子を語れる証言者は激減した。徳山市史によると、島の住民は55年に2390人。現在は171人(9月末時点)と1割に満たない。
回天の搭乗員も同様だ。訓練を受けたのは1375人(うち106人が戦死)。回天顕彰会(周南市)の石丸省悟副会長代行(73)は「出撃がなく、戦後を生きた搭乗員のうち少なくとも1人の存命は確認できている。しかし、多くが亡くなっている」と指摘する。
回天記念館(同市)の元研究員三崎英和さん(68)は、市が2019年に刊行した回天の記念誌の編集を担当した。経験を基に「命令書や指示書は多くが焼却処分され、調べ尽くされていない。事実を知る上で、証言は今なお大切」と強調する。
毎春、島を慰霊に訪れる清積勲四郎さん(96)=愛媛県松前町。回天を載せて出撃した潜水艦「伊58」の乗組員だった。士官室の雑務係で、回天の搭乗員を艦内に迎えた際は「別れの杯をするから、酒をもってこい」との指示を受けたという。
回天を発射する潜水艦も大きな危険を伴った。8隻が撃沈されるなどして戻らず、乗組員の戦死者は計811人に上る。清積さんは「僕たちもいつ死ぬか分からない状況。回天に対する特別な気持ちはなかった」と説明。その上で「僕たちの代わりに亡くなった。守ってくれた」と言葉をつなぐ。
回天は戦後、海中に投棄されている。田中さんは9月、終戦から5年後ごろの記憶を冊子にまとめた。大津島そばの洲島。海から引き揚げたとみられる赤さびた「回天」が輪切りにされる作業を、友だちと目撃したとの内容だ。「朝鮮特需で古鉄が必要だった」とみる。「回天の最後を見届けたのは私たちだけじゃないか。残しておきたかった」
回天
魚雷に多量の爆薬を搭載し、1人乗りの搭乗席を内部に設けた直径1メートル、全長14.75メートルの特攻兵器。旧日本軍が、悪化した戦局を打開するため、使用する機会を失っていた魚雷をベースに開発した。潜水艦から放たれ、敵艦に体当たりする。1944年9月、周南市大津島に初めて訓練基地が開設され、44年11月8日、最初の出撃隊の「菊水隊」が出発した。整備員たちも含めた戦死者は145人。うち搭乗員は106人で平均年齢は20.9歳。
(2024年11月8日朝刊掲載)
平然とした顔 脳裏に
乏しい資料 聞き取り大切
終戦間近の島で見た表情を、忘れないでいる。島で育った同市川崎の元高校教諭田中賢一さん(86)。当時、出撃隊を見送った。「皆ええ男で若いお兄ちゃん。精悍(せいかん)な真っ黒の顔ではなく、きれいな顔で。平然としていた」。極秘の作戦。自身は現在でいう小学1年生で、兵士の顔を見ないよう先生に言われた。ただ、我慢できず頭を下げたまま上目遣いに見た。
島に回天の基地ができたのは1944年9月。上部が白く塗られた「魚雷」と高速艇が徳山湾や周防灘を行き来する訓練を、自宅や山から見ながら過ごしていた。
魚雷と思っていた機体が特攻兵器と知ったのは戦後だった。田中さんは島を離れて教員に。郷土史研究会の会長を務め、体験も記してきた。「1週間後には死なないといけない状況に置かれた若者が、どうしてあんなにも平然としていられたのか。胸の内はどんな思いだったのか」。表情を思い浮かべ、つぶやいた。
周防灘に浮かぶ約4・7平方キロの島。戦時下の様子を語れる証言者は激減した。徳山市史によると、島の住民は55年に2390人。現在は171人(9月末時点)と1割に満たない。
回天の搭乗員も同様だ。訓練を受けたのは1375人(うち106人が戦死)。回天顕彰会(周南市)の石丸省悟副会長代行(73)は「出撃がなく、戦後を生きた搭乗員のうち少なくとも1人の存命は確認できている。しかし、多くが亡くなっている」と指摘する。
回天記念館(同市)の元研究員三崎英和さん(68)は、市が2019年に刊行した回天の記念誌の編集を担当した。経験を基に「命令書や指示書は多くが焼却処分され、調べ尽くされていない。事実を知る上で、証言は今なお大切」と強調する。
毎春、島を慰霊に訪れる清積勲四郎さん(96)=愛媛県松前町。回天を載せて出撃した潜水艦「伊58」の乗組員だった。士官室の雑務係で、回天の搭乗員を艦内に迎えた際は「別れの杯をするから、酒をもってこい」との指示を受けたという。
回天を発射する潜水艦も大きな危険を伴った。8隻が撃沈されるなどして戻らず、乗組員の戦死者は計811人に上る。清積さんは「僕たちもいつ死ぬか分からない状況。回天に対する特別な気持ちはなかった」と説明。その上で「僕たちの代わりに亡くなった。守ってくれた」と言葉をつなぐ。
回天は戦後、海中に投棄されている。田中さんは9月、終戦から5年後ごろの記憶を冊子にまとめた。大津島そばの洲島。海から引き揚げたとみられる赤さびた「回天」が輪切りにされる作業を、友だちと目撃したとの内容だ。「朝鮮特需で古鉄が必要だった」とみる。「回天の最後を見届けたのは私たちだけじゃないか。残しておきたかった」
回天
魚雷に多量の爆薬を搭載し、1人乗りの搭乗席を内部に設けた直径1メートル、全長14.75メートルの特攻兵器。旧日本軍が、悪化した戦局を打開するため、使用する機会を失っていた魚雷をベースに開発した。潜水艦から放たれ、敵艦に体当たりする。1944年9月、周南市大津島に初めて訓練基地が開設され、44年11月8日、最初の出撃隊の「菊水隊」が出発した。整備員たちも含めた戦死者は145人。うち搭乗員は106人で平均年齢は20.9歳。
(2024年11月8日朝刊掲載)