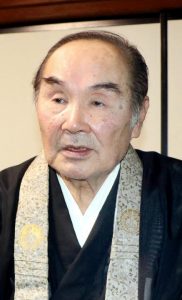崇徳教社 伝道脈々と 私塾設立から150年 中山間地域中心に10支部
24年11月25日
崇徳中高(崇徳学園、広島市西区)のかつての経営母体だった「真宗崇徳教社」が、現在も脈々と伝道に励んでいる。「平和を愛する浄土真宗の教えを共有し続けたい」と、中山間地域を中心に10支部が活動を続けるほか、広島市中心部での講演会も20回を超えた。前身の私塾設立から来年で150年となるのを前に、現状を見た。(山田祐)
浄土真宗本願寺派報正寺(広島県安芸太田町)の本堂に8月下旬、近隣の僧侶や門徒の計約30人が集まった。崇徳教社の支部の一つで、町内20の寺でつくる「太田部」の大会が開かれていた。
この日は3日間の大会日程の2日目。講師に招かれた同派万行寺(東京)の本多静芳住職が説いたのは、宗祖親鸞(しんらん)が大切にしていた「他力」の教え。阿弥陀仏に全てを委ねることで、自分中心に考えてしまいがちな心の在りように気付ける―。「命とは何代にもわたる積み重ね。先祖代々受け継いできた仏法を大切にする生活こそが、皆さんの背中を押してくれている」と語りかけた。
大会では戦没者の追悼法要も営み、太田部部長で同派法専寺(安芸太田町)の佐々木亮(まこと)住職が「武器や核兵器のない、全ての人々が平和に暮らせる社会の実現に向けて歩んでいこう」と力を込めた。
太田部の大会は1910(明治43)年にスタート。当初は僧侶向けの研修会だったが、やがて門徒たちも聴聞する形に変わったという。終戦直後や新型コロナウイルス禍中を除き、年1、2回のペースで続けてきた。
崇徳教社の歴史は1875年、安芸門徒により広島市内に創設された私塾「学仏場」にさかのぼる。77年に「進徳教校」となり、82年、経営母体として教会結社の進徳教社(翌年に崇徳教社と改名)を整えた上で、現在の崇徳中高の校地を造成、移転させた。学校法人崇徳学園の発足に伴い、経営を移すのは1951(昭和26)年。同様の結社は本願寺の呼びかけもあって全国各地で生まれたが、今も続く事例は珍しいという。
県内各地に最大31支部ができたが、現在残るのは10支部。太田部のほか、東広島市や広島市安佐北区など中山間地域を中心に活動が続く。
近年は都市部での布教を目的とした行事も取り入れている。年1回ペースでの大規模な講演会。21回目が今月1日、県民文化センター(広島市中区)であった。
訪れた約300人を前に、同派報専坊(中区)の冨樫恵生住職が安芸門徒の歴史をテーマに語った。明治期、ハワイに労働者として渡った「官約移民」の多くが広島県民だったことに触れ、「忍耐強さと前向きさを併せ持ったのが安芸門徒。その土地に住んでいることに思いをはせてほしい」と呼びかけた。
崇徳教社理事長を務める浄土真宗本願寺派法専寺(呉市)前住職の毛利滉(こう)さんの話
広島県西部を中心とする地域で、人々の精神面に大きな影響を与えていたのが浄土真宗でした。
例えば私の寺がある呉市音戸町一帯では、漁師さんは親鸞聖人の月命日の16日は漁をしませんでした。それほど命を大切にする教えを重んじたのです。そうした文化が形として残ったものの一つが、崇徳教社です。
戦前までは県西部各地に支部がありました。原爆投下を受けた広島市の都心部では姿を消し、その後は中山間地域を中心に残った支部が一生懸命活動してくれています。
阿弥陀仏に身を委ねることを愚直に説き続けた親鸞聖人の教えが根付いた地域。原爆被害を受けたことについても、敵討ちをしようという発想ではなく、黙々と復興に向かって立ち上がりました。広島東洋カープのファンが一丸となって応援する姿もその表れのように思います。
核兵器に反対しなくてはいけないのは当然のことです。私を妊娠中だった母は親戚を捜すため、被爆直後の広島に入っています。「みんなが死んでしまったのに1人だけええことはできん」との言葉が忘れられません。投下した相手に怒りを向けない強さと、その苦しみを思います。
長期化しているロシアのウクライナ侵攻、悪化する中東情勢…。核兵器がまた使われてしまわないかという心配が広がっています。親鸞聖人は「世の中安穏なれ、仏法広まれ」と願われました。崇徳教社や各支部が発し続けてきたその心が、世界に広まることを願います。
(2024年11月25日朝刊掲載)
浄土真宗本願寺派報正寺(広島県安芸太田町)の本堂に8月下旬、近隣の僧侶や門徒の計約30人が集まった。崇徳教社の支部の一つで、町内20の寺でつくる「太田部」の大会が開かれていた。
この日は3日間の大会日程の2日目。講師に招かれた同派万行寺(東京)の本多静芳住職が説いたのは、宗祖親鸞(しんらん)が大切にしていた「他力」の教え。阿弥陀仏に全てを委ねることで、自分中心に考えてしまいがちな心の在りように気付ける―。「命とは何代にもわたる積み重ね。先祖代々受け継いできた仏法を大切にする生活こそが、皆さんの背中を押してくれている」と語りかけた。
大会では戦没者の追悼法要も営み、太田部部長で同派法専寺(安芸太田町)の佐々木亮(まこと)住職が「武器や核兵器のない、全ての人々が平和に暮らせる社会の実現に向けて歩んでいこう」と力を込めた。
太田部の大会は1910(明治43)年にスタート。当初は僧侶向けの研修会だったが、やがて門徒たちも聴聞する形に変わったという。終戦直後や新型コロナウイルス禍中を除き、年1、2回のペースで続けてきた。
崇徳教社の歴史は1875年、安芸門徒により広島市内に創設された私塾「学仏場」にさかのぼる。77年に「進徳教校」となり、82年、経営母体として教会結社の進徳教社(翌年に崇徳教社と改名)を整えた上で、現在の崇徳中高の校地を造成、移転させた。学校法人崇徳学園の発足に伴い、経営を移すのは1951(昭和26)年。同様の結社は本願寺の呼びかけもあって全国各地で生まれたが、今も続く事例は珍しいという。
県内各地に最大31支部ができたが、現在残るのは10支部。太田部のほか、東広島市や広島市安佐北区など中山間地域を中心に活動が続く。
近年は都市部での布教を目的とした行事も取り入れている。年1回ペースでの大規模な講演会。21回目が今月1日、県民文化センター(広島市中区)であった。
訪れた約300人を前に、同派報専坊(中区)の冨樫恵生住職が安芸門徒の歴史をテーマに語った。明治期、ハワイに労働者として渡った「官約移民」の多くが広島県民だったことに触れ、「忍耐強さと前向きさを併せ持ったのが安芸門徒。その土地に住んでいることに思いをはせてほしい」と呼びかけた。
命大切にする教え 広がり願う
崇徳教社理事長を務める浄土真宗本願寺派法専寺(呉市)前住職の毛利滉(こう)さんの話
広島県西部を中心とする地域で、人々の精神面に大きな影響を与えていたのが浄土真宗でした。
例えば私の寺がある呉市音戸町一帯では、漁師さんは親鸞聖人の月命日の16日は漁をしませんでした。それほど命を大切にする教えを重んじたのです。そうした文化が形として残ったものの一つが、崇徳教社です。
戦前までは県西部各地に支部がありました。原爆投下を受けた広島市の都心部では姿を消し、その後は中山間地域を中心に残った支部が一生懸命活動してくれています。
阿弥陀仏に身を委ねることを愚直に説き続けた親鸞聖人の教えが根付いた地域。原爆被害を受けたことについても、敵討ちをしようという発想ではなく、黙々と復興に向かって立ち上がりました。広島東洋カープのファンが一丸となって応援する姿もその表れのように思います。
核兵器に反対しなくてはいけないのは当然のことです。私を妊娠中だった母は親戚を捜すため、被爆直後の広島に入っています。「みんなが死んでしまったのに1人だけええことはできん」との言葉が忘れられません。投下した相手に怒りを向けない強さと、その苦しみを思います。
長期化しているロシアのウクライナ侵攻、悪化する中東情勢…。核兵器がまた使われてしまわないかという心配が広がっています。親鸞聖人は「世の中安穏なれ、仏法広まれ」と願われました。崇徳教社や各支部が発し続けてきたその心が、世界に広まることを願います。
(2024年11月25日朝刊掲載)