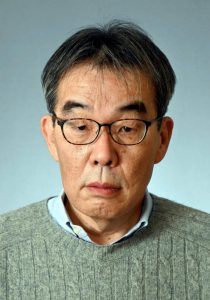ノーベル平和賞と被団協 取材者の証言 <6> 元特別編集委員 西本雅実
24年12月10日
「生きていてよかった」世界に
国家ではなく人間の立場で考える
日本被団協の始まりを伝える写真があった。広島でいち早く声を上げた被爆者らが、1956年8月10日「結成大会」の垂れ幕がかかる長崎国際文化会館で写る。
前列の女性3人は、代表委員・事務局長となる藤居平一さん(1996年に80歳で死去)が3月に率いた初の「国会請願」にも参加し、治療費の国庫負担などを求めた。5月結成の広島県被団協や長崎、愛媛などから約800人が参集した日本被団協の出発に立ち会ったのだ。 その一人、阿部静子さん(97)の半生を今春から有志らと聞き編さんする中で写真を見つけた。
阿部さんは45年8月6日、広島市の建物疎開作業に動員されて爆心地から東南約1・5キロで被爆した。復員した夫や義母と生まれ育った奥海田村(現広島県海田町)で暮らし、男児を授かる。しかし、顔や右半身の忌まわしい傷痕にさいなまれた。外出すると、胸をえぐられるような視線や冷やかしにもさらされた。
「隠れて暮らす日々」が続いていた52年夏、原爆ドームそばの土産物店をたまたまのぞいた。世界的なグラフ誌ライフの紹介から「原爆一号」と呼ばれた吉川清さん(86年に74歳で死去)の店。米軍主導の占領統治が明けたこの年8月に設けた「原爆被害者の会」の事務所を置いていた。
広島でも社会の片隅に追いやられ孤立していた被爆者の集まりに阿部さんは通う。
「原爆に苦しむ人たちと話し合うようになり、仲間によって慰められ元気をもらいました」。そこで出会った作家山代巴に促されて体験を書き収録される。53年発行「原爆に生きて」には、被団協の礎をつくる先人たちが夫や子を失った苛烈な体験記を寄せている。
写真で阿部さんの右にいる、村戸由子さん(2022年9月21日に90歳で死去)は55年に広島市で開かれた第1回原水爆禁止世界大会でこう訴えた。「われわれだけでもうたくさんです」。国内外の約1900人から激励の拍手を受けて演壇を降り、思わず「生きていてよかった」の言葉が口を突いた。
新たな決意も示すこの述懐や、阿部さんが国会請願から戻る列車内で「今の心境」と書いて藤居さんに手渡した詩の一節、「生きていてよかったと 思いつづけられるように」は日本被団協の結成大会宣言「世界への挨拶(あいさつ)」に織り込まれる。
「人類の生命と幸福を守るとりでとして役立ちますならば、私たちは心から『生きていてよかった』と喜ぶことができるでしょう」 くしくも被団協結成の年に僕は生まれた。「遭(お)うた者でないと本当のことは分からんよね」。母の吐露や、朝晩の読経を欠かさなかった祖父母の沈黙に接してきた。
80年代半ばから原爆報道に携わり、被爆者健康手帳の申請資格すらない「原爆孤児」、援護から切り捨てられた在韓被爆者を取材した。原爆で人間はどうなったのか、何が続いているか。顧みられない人々の歩みや息遣い、知られざる記録と記憶を追いかけた。
平和記念公園となった爆心地一帯にいた住民や動員学徒の生と死を掘り起こし、後輩記者の力も借りて1882人の遺影を掲載した。公園内の国立広島原爆死没者追悼平和祈念館は2002年の開館を前に、遺族の同意を得てこれを収めた。
祈念館は「誤った国策により犠牲」との説明を付ける。広島の被爆者7団体と行政との橋渡し役を担った近藤幸四郎さんの粘り強い訴えからだ。開館直後に69歳で逝った近藤さんは「死者を悼む人間的な感情や共感を大事にしてこそ平和運動だ」とよく語っていた。
核兵器を国家の側ではなく人間の立場から考える。「生きていてよかった」世界をつくるのは私たち一人一人のはずである。(おわり)
にしもと・まさみ
1980年中国新聞社入社。原爆関連の主な特集連載に95年「検証ヒロシマ」、98~2000年「遺影は語る」、14~15年「伝えるヒロシマ」など。68歳。
(2024年12月10日朝刊掲載)