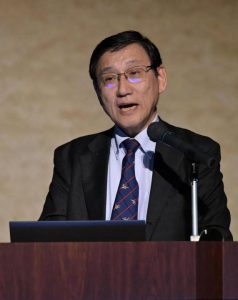世界の核被害 実態を議論 広島で国際シンポ 詳報
24年12月16日
広島市立大広島平和研究所と中国新聞社、長崎大核兵器廃絶研究センター(RECNA)主催の国際シンポジウム「グローバルに核被害をとらえ直す―いま改めて『ノーモア・ヒバクシャ』」が11月30日、広島市中区の広島国際会議場であった。今年は、米国の水爆実験でマグロ漁船「第五福竜丸」などが被災してから70年。広島と長崎にとどまらない戦後の核被害の実態と背景について、登壇者が掘り下げ議論。市民約220人が耳を傾けた。(金崎由美、新山京子、頼金育美)
ドキュメンタリー映画「サイレント・フォールアウト」(76分)は、米国内で続いた大気圏内核実験が、1945年7月16日の「トリニティ・サイト」で行われた実験も含め101回、地下核実験は828回に及んだ事実と、被曝の実態を伝えている。
だから当初は米国での上映を想定して制作した。作品のキーワードとしたのは、「当事者意識」だ。核兵器の製造や実験の過程で世界中が放射能で汚染されている。映画を通じて「誰がヒバクシャなのか」を問うた。
今年7、8月の43日間、米国内の計20カ所で現地の人たちの協力を得て上映した。驚くことに、鑑賞した人の大半が自分の国が放射性物質で汚染されていることを認識していなかった。
米国で上映会に参加する際、二つの話をする。一つ目は、50~60年代に米国の女性たちが子どもたちの乳歯を集め、蓄積した放射性物質を調べて放射能汚染を証明したことだ。これが当時のケネディ米大統領を動かし、大気圏内核実験の中止につながった。もし女性たちが行動を起こさなければ、放射能汚染はさらに進んでいただろう。
二つ目は、「自分はヒバクシャだ」と皆に当事者意識を持ってほしいということ。あなたたちは命をささげるという交換条件で核兵器を持っているのだと知ってください、と。核兵器を持つべきか、持たざるべきか、という次元で議論する以前に、核保有国の自国民がこれほどまでに被曝させられている現実を知るべきだ。その実態を国民に伝えない政府の責任を問わなければいけない。
米国民向けに作った映画だが、日本でも上映されていることをうれしく思っている。核問題について当事者意識を持ち、環境問題としても考えてもらえるよう、できる限り自らの活動を続けたい。
いとう・ひであき
1960年生まれ。幼稚園教諭からテレビの世界へ転身し番組制作の傍ら映画「X年後」シリーズ制作。2023年「サイレント・フォールアウト」公開。20年度芸術選奨文部科学大臣賞、日本記者クラブ賞特別賞、ギャラクシー賞大賞など受賞。
2011年、非政府組織(NGO)ピースボート主催の世界一周の船旅に参加した。同じく乗船した被爆者から体験を直接聞くのは初めてだった。さらに、被曝した人が地球上に大勢いることも知ったことが現在の活動のきっかけになった。
オーストラリアの先住民と出会い、ウラン採掘でコミュニティーが被害を受けている上、ウランが日本の原発用に輸出されていると聞いた。私は、発電された電気を使う側にいる。普段の生活が被曝とつながっていることに衝撃を受けた。
22年、核兵器禁止条約第1回締約国会議に参加して、核被害地から来た同世代と交流した。帰国後、勉強会「世界のヒバクシャと出会うユースセッション」を始めた。日本の若者がオンライン上で核被害の当事者らと「出会う」機会だ。
米核実験で最大規模のブラボー実験から70年の節目となる今年は、太平洋のマーシャル諸島を訪れた。1946年に米核実験のため移住を強いられたビキニ環礁の首長と出会った。除染が進まず今も帰還できない。「ふるさとに帰りたい」との思いを聞いた。
首都マジュロでは、学生が放射性降下物の被害を受けた環礁に住んでいた曽祖母について語ってくれた。以前「核実験も戦争だ」と言う曽祖母に「戦争はもう終わった」と返したことを後悔しているという。
現地では温暖化による海面上昇で、米国が汚染土を廃棄した「ルニット・ドーム」から汚染が広がる懸念も聞いた。核問題は気候危機や植民地主義と交差していると痛感する。
ビキニの人たちは故郷への愛と悲しみを込めた歌を披露していた。心揺さぶられたのは、多様な表現方法で人々が思いを伝えていたこと。人間の人生や苦しみを心で受け止め、学び続けたい。
せと・まゆ
1991年生まれ。早稲田大在学中に外務省委嘱のユース非核特使としてピースボート主催の船旅で被爆者と世界一周。核政策を知りたい広島若者有権者の会(カクワカ広島)メンバーとして2022年の核兵器禁止条約第1回締約国会議に参加。
核兵器システムと核抑止を支える科学技術は高度化し、脆弱(ぜいじゃく)性とも隣り合わせであることが重い課題となっている。ジャーナリストのエリック・シュローサー氏は、技術者が工具を一つ落としたことが大陸間弾道ミサイル(ICBM)の爆発事故につながった1980年の米国の例を明かしている。だが、現在の核兵器システムははるかに複雑だ。
米国は核兵器を「近代化」させ、弾頭数は減らしても「質」の維持を図っている。核爆弾B61を出力調整できるようにしたことから「使いやすさ」が核戦争のリスクを高めると指摘された。核搭載可能なロシアの極超音速弾道ミサイルは米国との間を10分以内で滑空する。現在のミサイル防衛では防げず、戦略的安定性を揺るがす。
台頭著しいサイバー兵器や、通常兵器に多用され始めた人工知能(AI)は、情報技術が攻撃されれば影響はシステム全体に及ぶ。核抑止への依存がいかに危険か。これからは弾頭数だけでなく、質的規制が課題だ。従来の軍備管理・軍縮を超え「行動規範」からのアプローチが必要だ。
科学者や技術者の行動規範も問われる。原爆開発の「マンハッタン計画」に参加した物理学者ジェームズ・フランクは戦争末期には対日使用に反対。ジョセフ・ロートブラットは途中で計画から去り、戦後に科学者の平和団体「パグウォッシュ会議」設立に関わった。
科学技術が軍事目的に利用されないよう、社会を反戦争へと変革しなければならない。日本でも日本学術会議への政治圧力や、安全保障予算を増やして大学の研究を促す動きがあるが、「予算」と「戦争」を切り離し、科学を自律的にする必要がある。科学者や技術者の社会的責任と市民社会による監視が重要だ。
すずき・たつじろう
1951年生まれ。75年東京大卒。78年米マサチューセッツ工科大修士。88年に東京大で博士号(工学)。2010年1月~14年3月、内閣府原子力委員会委員長代理。核兵器と戦争の根絶を目指す科学者集団パグウォッシュ会議評議員。
中国新聞社は79年前の被爆体験を原点に、原爆報道を続けている。今も終わっていない問題だからだ。ヒロシマの体験は決して「過去」や「ローカル」な問題でなく、グローバルな現在の問題といえる。今も世界では戦争で血が流れ、実戦使用こそされないが核による脅しは続く。また核開発の過程でヒバクシャは生まれ続けている。それゆえ核被害を含む暴力に敏感に反応し報じてきた。
例えば1989~90年の連載企画「世界のヒバクシャ」は先輩記者が当時の米ソ、太平洋の島々、アフリカなど15カ国21地域をルポし20部構成で紹介。当時ほとんど報じられていなかった旧ソ連セミパラチンスク核実験場の実態やアフリカ・ナミビアのウラン鉱山などを取材し、地球規模で広がる核汚染を問うた。
被爆地で原爆被害者の声に耳を傾けてきた私も世界の核被害者と出会ってきた。かつて米国が核実験を繰り返したマーシャル諸島に約1カ月滞在し取材した経験がある。そこで見たのは人間を苦しめ続ける核の非人道性に加え、大国による「植民地主義」だった。現地の人々は実験により住み慣れた地を奪われ、被曝して健康障害に苦しんでいたが、それが何によるものかさえ長く知らされてこなかった。若者は古里を知らずローカルフードも口にできない。除染作業はより貧しい地域からの出稼ぎ労働者が担っていた。大国の核開発が弱い立場の人々の犠牲の上に成り立っている現実を目の当たりにした。
私たちはグローバルに核被害を考えるとき背景にある植民地主義や構造的暴力の問題に目を向ける必要があるのではないか。ともすればパワーゲームの道具として語られる核兵器は、開発段階から計り知れない被害を生む。それを可視化し、きのこ雲の下の人間の視点から伝え続ける。
もりた・ひろみ
1973年生まれ。お茶の水女子大卒業後、97年中国新聞社入社。報道部、文化部、論説委員などを経て、現在ヒロシマ平和メディアセンター。被爆者援護や世界の核被害者、原爆や戦争にまつわる表象・表現、記憶の継承などについて取材を重ねている。
「グローバルヒバクシャ」とは広島と長崎に原爆が投下された1945年以降に被曝(ひばく)した全ての人を指す。核実験、原発事故、核兵器や核燃料の製造過程における当事者である。
核兵器が熱線、爆風、放射線を放出させた瞬間だけが被曝ではない。グローバルヒバクシャの大多数は広島の「黒い雨」と同様、目に見えない放射性微粒子を体に取り込み内部被曝した。中部太平洋マーシャル諸島で米国が行った水爆実験では、約100キロ離れた位置にいたマグロ漁船「第五福竜丸」の全員が焼津に帰港後、入院。1人は半年後に亡くなった。
核実験は南米と南極大陸を除く全ての大陸で2121回も行われてきた。核実験場を置くのは植民地や旧植民地、民族や宗教的な少数派が住む地だ。英国とフランスは自国領土で実験を行ったことが一度もない。
核保有国の初期の原子炉は、兵器用プルトニウムを生産するため軍によって建設された。57年に旧ソ連と英国で重大な原子力事故が起こった。かつてウラン採掘が行われ、核廃棄物が大量に残る米国の先住民準自治領ナバホ・ネーションでは、追跡調査の対象者全員の尿からウランの痕跡が認められた。
米軍の研究者はある極秘調査で、人々を殺害し恐怖を与えるため、爆発後の放射性微粒子が利用できるとした。放射性降下物自体が「兵器」になるという意味である。
戦争で核攻撃されることへの恐れから、もっぱら直接被曝がもたらす影響が注目されてきた。だが実際、冷戦期には8・6日に1回の核爆発があり、放射性降下物が降り注いだ。核実験場近くの住民にとって「核実験」は「核攻撃」だ。旧植民地や周縁に追いやられた人々には、冷戦期こそ「限定核戦争」だった。
核兵器が実戦使用されるかどうかに終始する議論では、核保有国が核兵器を造り、実験し、配備展開する前から既に「使用」されており、人間や生態系全体に対する暴力を及ぼしているという事実が見えなくなる。核抑止や「核のタブー」の存在がよく議論されるが、本当は既に使われている。核兵器は、存在自体が暴力なのだ。
1960年米フロリダ州生まれ。2004年にイリノイ大で博士号(歴史学)。05年に広島市立大広島平和研究所へ。16年から現職。科学技術分野の歴史家として核テクノロジーの歴史と環境への影響やグローバルヒバクシャ問題を研究。
基調講演者と報告者による討論を23日付「平和」で詳報します
(2024年12月16日朝刊掲載)
「皆ヒバクシャ」事実伝えたい
映画監督 伊東英朗氏
ドキュメンタリー映画「サイレント・フォールアウト」(76分)は、米国内で続いた大気圏内核実験が、1945年7月16日の「トリニティ・サイト」で行われた実験も含め101回、地下核実験は828回に及んだ事実と、被曝の実態を伝えている。
だから当初は米国での上映を想定して制作した。作品のキーワードとしたのは、「当事者意識」だ。核兵器の製造や実験の過程で世界中が放射能で汚染されている。映画を通じて「誰がヒバクシャなのか」を問うた。
今年7、8月の43日間、米国内の計20カ所で現地の人たちの協力を得て上映した。驚くことに、鑑賞した人の大半が自分の国が放射性物質で汚染されていることを認識していなかった。
米国で上映会に参加する際、二つの話をする。一つ目は、50~60年代に米国の女性たちが子どもたちの乳歯を集め、蓄積した放射性物質を調べて放射能汚染を証明したことだ。これが当時のケネディ米大統領を動かし、大気圏内核実験の中止につながった。もし女性たちが行動を起こさなければ、放射能汚染はさらに進んでいただろう。
二つ目は、「自分はヒバクシャだ」と皆に当事者意識を持ってほしいということ。あなたたちは命をささげるという交換条件で核兵器を持っているのだと知ってください、と。核兵器を持つべきか、持たざるべきか、という次元で議論する以前に、核保有国の自国民がこれほどまでに被曝させられている現実を知るべきだ。その実態を国民に伝えない政府の責任を問わなければいけない。
米国民向けに作った映画だが、日本でも上映されていることをうれしく思っている。核問題について当事者意識を持ち、環境問題としても考えてもらえるよう、できる限り自らの活動を続けたい。
いとう・ひであき
1960年生まれ。幼稚園教諭からテレビの世界へ転身し番組制作の傍ら映画「X年後」シリーズ制作。2023年「サイレント・フォールアウト」公開。20年度芸術選奨文部科学大臣賞、日本記者クラブ賞特別賞、ギャラクシー賞大賞など受賞。
人と地域社会の被害 出会いから知る
核政策を知りたい広島若者有権者の会 瀬戸麻由氏
2011年、非政府組織(NGO)ピースボート主催の世界一周の船旅に参加した。同じく乗船した被爆者から体験を直接聞くのは初めてだった。さらに、被曝した人が地球上に大勢いることも知ったことが現在の活動のきっかけになった。
オーストラリアの先住民と出会い、ウラン採掘でコミュニティーが被害を受けている上、ウランが日本の原発用に輸出されていると聞いた。私は、発電された電気を使う側にいる。普段の生活が被曝とつながっていることに衝撃を受けた。
22年、核兵器禁止条約第1回締約国会議に参加して、核被害地から来た同世代と交流した。帰国後、勉強会「世界のヒバクシャと出会うユースセッション」を始めた。日本の若者がオンライン上で核被害の当事者らと「出会う」機会だ。
米核実験で最大規模のブラボー実験から70年の節目となる今年は、太平洋のマーシャル諸島を訪れた。1946年に米核実験のため移住を強いられたビキニ環礁の首長と出会った。除染が進まず今も帰還できない。「ふるさとに帰りたい」との思いを聞いた。
首都マジュロでは、学生が放射性降下物の被害を受けた環礁に住んでいた曽祖母について語ってくれた。以前「核実験も戦争だ」と言う曽祖母に「戦争はもう終わった」と返したことを後悔しているという。
現地では温暖化による海面上昇で、米国が汚染土を廃棄した「ルニット・ドーム」から汚染が広がる懸念も聞いた。核問題は気候危機や植民地主義と交差していると痛感する。
ビキニの人たちは故郷への愛と悲しみを込めた歌を披露していた。心揺さぶられたのは、多様な表現方法で人々が思いを伝えていたこと。人間の人生や苦しみを心で受け止め、学び続けたい。
せと・まゆ
1991年生まれ。早稲田大在学中に外務省委嘱のユース非核特使としてピースボート主催の船旅で被爆者と世界一周。核政策を知りたい広島若者有権者の会(カクワカ広島)メンバーとして2022年の核兵器禁止条約第1回締約国会議に参加。
新興する技術 新たな規範が必要だ
長崎大核兵器廃絶研究センター教授 鈴木達治郎教授
核兵器システムと核抑止を支える科学技術は高度化し、脆弱(ぜいじゃく)性とも隣り合わせであることが重い課題となっている。ジャーナリストのエリック・シュローサー氏は、技術者が工具を一つ落としたことが大陸間弾道ミサイル(ICBM)の爆発事故につながった1980年の米国の例を明かしている。だが、現在の核兵器システムははるかに複雑だ。
米国は核兵器を「近代化」させ、弾頭数は減らしても「質」の維持を図っている。核爆弾B61を出力調整できるようにしたことから「使いやすさ」が核戦争のリスクを高めると指摘された。核搭載可能なロシアの極超音速弾道ミサイルは米国との間を10分以内で滑空する。現在のミサイル防衛では防げず、戦略的安定性を揺るがす。
台頭著しいサイバー兵器や、通常兵器に多用され始めた人工知能(AI)は、情報技術が攻撃されれば影響はシステム全体に及ぶ。核抑止への依存がいかに危険か。これからは弾頭数だけでなく、質的規制が課題だ。従来の軍備管理・軍縮を超え「行動規範」からのアプローチが必要だ。
科学者や技術者の行動規範も問われる。原爆開発の「マンハッタン計画」に参加した物理学者ジェームズ・フランクは戦争末期には対日使用に反対。ジョセフ・ロートブラットは途中で計画から去り、戦後に科学者の平和団体「パグウォッシュ会議」設立に関わった。
科学技術が軍事目的に利用されないよう、社会を反戦争へと変革しなければならない。日本でも日本学術会議への政治圧力や、安全保障予算を増やして大学の研究を促す動きがあるが、「予算」と「戦争」を切り離し、科学を自律的にする必要がある。科学者や技術者の社会的責任と市民社会による監視が重要だ。
すずき・たつじろう
1951年生まれ。75年東京大卒。78年米マサチューセッツ工科大修士。88年に東京大で博士号(工学)。2010年1月~14年3月、内閣府原子力委員会委員長代理。核兵器と戦争の根絶を目指す科学者集団パグウォッシュ会議評議員。
背景に植民地主義や構造的暴力
中国新聞社 森田裕美記者
中国新聞社は79年前の被爆体験を原点に、原爆報道を続けている。今も終わっていない問題だからだ。ヒロシマの体験は決して「過去」や「ローカル」な問題でなく、グローバルな現在の問題といえる。今も世界では戦争で血が流れ、実戦使用こそされないが核による脅しは続く。また核開発の過程でヒバクシャは生まれ続けている。それゆえ核被害を含む暴力に敏感に反応し報じてきた。
例えば1989~90年の連載企画「世界のヒバクシャ」は先輩記者が当時の米ソ、太平洋の島々、アフリカなど15カ国21地域をルポし20部構成で紹介。当時ほとんど報じられていなかった旧ソ連セミパラチンスク核実験場の実態やアフリカ・ナミビアのウラン鉱山などを取材し、地球規模で広がる核汚染を問うた。
被爆地で原爆被害者の声に耳を傾けてきた私も世界の核被害者と出会ってきた。かつて米国が核実験を繰り返したマーシャル諸島に約1カ月滞在し取材した経験がある。そこで見たのは人間を苦しめ続ける核の非人道性に加え、大国による「植民地主義」だった。現地の人々は実験により住み慣れた地を奪われ、被曝して健康障害に苦しんでいたが、それが何によるものかさえ長く知らされてこなかった。若者は古里を知らずローカルフードも口にできない。除染作業はより貧しい地域からの出稼ぎ労働者が担っていた。大国の核開発が弱い立場の人々の犠牲の上に成り立っている現実を目の当たりにした。
私たちはグローバルに核被害を考えるとき背景にある植民地主義や構造的暴力の問題に目を向ける必要があるのではないか。ともすればパワーゲームの道具として語られる核兵器は、開発段階から計り知れない被害を生む。それを可視化し、きのこ雲の下の人間の視点から伝え続ける。
もりた・ひろみ
1973年生まれ。お茶の水女子大卒業後、97年中国新聞社入社。報道部、文化部、論説委員などを経て、現在ヒロシマ平和メディアセンター。被爆者援護や世界の核被害者、原爆や戦争にまつわる表象・表現、記憶の継承などについて取材を重ねている。
基調講演
核兵器 存在自体が暴力
広島市立大広島平和研究所 ロバート・ジェイコブズ教授
「グローバルヒバクシャ」とは広島と長崎に原爆が投下された1945年以降に被曝(ひばく)した全ての人を指す。核実験、原発事故、核兵器や核燃料の製造過程における当事者である。
核兵器が熱線、爆風、放射線を放出させた瞬間だけが被曝ではない。グローバルヒバクシャの大多数は広島の「黒い雨」と同様、目に見えない放射性微粒子を体に取り込み内部被曝した。中部太平洋マーシャル諸島で米国が行った水爆実験では、約100キロ離れた位置にいたマグロ漁船「第五福竜丸」の全員が焼津に帰港後、入院。1人は半年後に亡くなった。
核実験は南米と南極大陸を除く全ての大陸で2121回も行われてきた。核実験場を置くのは植民地や旧植民地、民族や宗教的な少数派が住む地だ。英国とフランスは自国領土で実験を行ったことが一度もない。
核保有国の初期の原子炉は、兵器用プルトニウムを生産するため軍によって建設された。57年に旧ソ連と英国で重大な原子力事故が起こった。かつてウラン採掘が行われ、核廃棄物が大量に残る米国の先住民準自治領ナバホ・ネーションでは、追跡調査の対象者全員の尿からウランの痕跡が認められた。
米軍の研究者はある極秘調査で、人々を殺害し恐怖を与えるため、爆発後の放射性微粒子が利用できるとした。放射性降下物自体が「兵器」になるという意味である。
戦争で核攻撃されることへの恐れから、もっぱら直接被曝がもたらす影響が注目されてきた。だが実際、冷戦期には8・6日に1回の核爆発があり、放射性降下物が降り注いだ。核実験場近くの住民にとって「核実験」は「核攻撃」だ。旧植民地や周縁に追いやられた人々には、冷戦期こそ「限定核戦争」だった。
核兵器が実戦使用されるかどうかに終始する議論では、核保有国が核兵器を造り、実験し、配備展開する前から既に「使用」されており、人間や生態系全体に対する暴力を及ぼしているという事実が見えなくなる。核抑止や「核のタブー」の存在がよく議論されるが、本当は既に使われている。核兵器は、存在自体が暴力なのだ。
1960年米フロリダ州生まれ。2004年にイリノイ大で博士号(歴史学)。05年に広島市立大広島平和研究所へ。16年から現職。科学技術分野の歴史家として核テクノロジーの歴史と環境への影響やグローバルヒバクシャ問題を研究。
基調講演者と報告者による討論を23日付「平和」で詳報します
(2024年12月16日朝刊掲載)