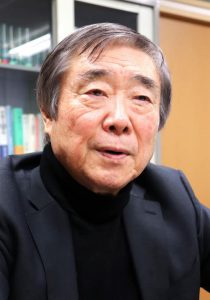[歩く 聞く 考える] 被爆80年と「原爆裁判」 国際法違反の判決 学び直そう 日本反核法律家協会会長 大久保賢一さん
25年1月22日
広島、長崎の原爆投下を国際法違反とした「原爆裁判」が再び注目を集める。1963年の東京地裁判決に携わった三淵嘉子裁判官が昨年のNHKドラマ「虎に翼」のモデルとなったからだ。裁判記録を継承する日本反核法律家協会の大久保賢一会長(78)=埼玉県所沢市=は新著「『原爆裁判』を現代に活(い)かす」(日本評論社)を刊行した。被爆80年を迎え、裁判に学び直すべきものを聞いた。(特別論説委員・岩崎誠、写真も)
―8年に及ぶ原爆裁判では被害者5人が日本政府に賠償を求めました。詳しく描いたドラマに協力したとか。
当時の原告代理人で私たちの協会を創設した故松井康浩弁護士の遺族から訴状、答弁書、準備書面、証拠申請書、鑑定書などの原本が寄贈されています。ドラマのスタッフが何回か来られ、資料を提供しました。原爆という残虐な兵器が被爆者に何をもたらしたのか。それに法や裁判がどう向き合うかを正面から問いかけるドラマでしたね。
―日本被団協のノーベル平和賞受賞も重なる中で、この裁判を見つめ直す意味は。
核兵器という究極の暴力に法という知恵が挑戦した史上初のケースでした。提起した問題の一つは被爆者の救済をどうするか。もう一つは原爆投下の違法性を問い、核兵器をどう禁止するかです。核兵器のない世界に向けて進む中で再度、原爆裁判に立ち戻りたいと考えます。
―判決のポイントとは。
賠償請求は棄却しますが、米国の原爆投下は国際法に照らして明確に違反すると断じました。当時の国際法を点検し、無防備都市への無差別爆撃であることと、不必要な苦痛を与えたという2点について国際法学者の鑑定人3人の意見を入れて違反と踏み込んだのです。現在の核兵器禁止条約という到達点につながる大きな意味を持っています。
もう一つは被爆者支援に消極的な日本政府や国会に「政治の貧困を嘆かずにはおられない」と言ったことです。いまだ不十分とはいえ現行の被爆者援護法に至った援護施策に影響を与えました。しかし平和賞の受賞演説で被団協の田中熙巳(てるみ)代表委員は日本政府が原爆の死者への国家補償を拒むことを指摘しました。今なお政治の貧困が解消されていないことが怒りのスピーチになったと思います。
―裁判は国家補償の問題をどう判断したのですか。
原爆投下は違法としても被害を受けた人に請求権を認める国際法はなく、個別的な請求権はない。そんな理屈で請求を棄却しましたが、判決は戦争災害に対しては結果責任に基づく国家補償の問題が生じる、とも明言しています。なぜ矛盾するようなことを言ったか。あまりにもひどい原爆被害に政府と国会が何もしないことへの裁判官の怒りが表れたと私は見ています。
―原爆以外の空襲なども同じではないでしょうか。
その通りです。被爆者は一定に救済があるのに他の戦災にはありません。戦争被害は国民が等しく受忍しなくてはならないという「受忍論」が政府の立場ですが、判決が戦争被害全体の救済の必要性を展開したことに注目します。
―今に積み残された論点が原爆裁判から読み取れます。とりわけ国の姿勢です。
被告(国)は原爆投下は国際法違反に当たらないと主張しました。しかし投下直後には国際法違反だと米国に抗議し、非人道兵器の廃棄を要求しています。まさに手のひら返しです。しかも原爆投下が自国民の被害を減らしたとまで裁判で言っています。米国の核とドルに依存してこの国を進める考え方になっていたのです。日米同盟の拡大核抑止に「核共有」。このところの動きを見ると当時の主張が一貫して続くどころか悪くなっています。核兵器のない世界を目指すと言いつつ核の傘に依存するのは詭弁(きべん)です。
―貴重な裁判資料は公開しているのですね。
私たちの協会のウェブサイトでほとんどの内容をアーカイブズ化しました。田中代表委員が受賞演説で言及したNPO法人「ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会」にいずれ引き継ぎ、後世に役立ててほしいと思います。
おおくぼ・けんいち
長野市生まれ。東北大卒。法務省勤務を経て1979年弁護士登録、埼玉弁護士会所属。94年に発足した日本反核法律家協会の活動に携わり、2020年に5代目会長に就任。日本弁護士連合会では憲法問題対策本部核兵器廃絶部会長を務める。著書に「憲法ルネサンス」「『核兵器廃絶』と憲法9条」など。
(2025年1月22日朝刊掲載)
―8年に及ぶ原爆裁判では被害者5人が日本政府に賠償を求めました。詳しく描いたドラマに協力したとか。
当時の原告代理人で私たちの協会を創設した故松井康浩弁護士の遺族から訴状、答弁書、準備書面、証拠申請書、鑑定書などの原本が寄贈されています。ドラマのスタッフが何回か来られ、資料を提供しました。原爆という残虐な兵器が被爆者に何をもたらしたのか。それに法や裁判がどう向き合うかを正面から問いかけるドラマでしたね。
―日本被団協のノーベル平和賞受賞も重なる中で、この裁判を見つめ直す意味は。
核兵器という究極の暴力に法という知恵が挑戦した史上初のケースでした。提起した問題の一つは被爆者の救済をどうするか。もう一つは原爆投下の違法性を問い、核兵器をどう禁止するかです。核兵器のない世界に向けて進む中で再度、原爆裁判に立ち戻りたいと考えます。
―判決のポイントとは。
賠償請求は棄却しますが、米国の原爆投下は国際法に照らして明確に違反すると断じました。当時の国際法を点検し、無防備都市への無差別爆撃であることと、不必要な苦痛を与えたという2点について国際法学者の鑑定人3人の意見を入れて違反と踏み込んだのです。現在の核兵器禁止条約という到達点につながる大きな意味を持っています。
もう一つは被爆者支援に消極的な日本政府や国会に「政治の貧困を嘆かずにはおられない」と言ったことです。いまだ不十分とはいえ現行の被爆者援護法に至った援護施策に影響を与えました。しかし平和賞の受賞演説で被団協の田中熙巳(てるみ)代表委員は日本政府が原爆の死者への国家補償を拒むことを指摘しました。今なお政治の貧困が解消されていないことが怒りのスピーチになったと思います。
―裁判は国家補償の問題をどう判断したのですか。
原爆投下は違法としても被害を受けた人に請求権を認める国際法はなく、個別的な請求権はない。そんな理屈で請求を棄却しましたが、判決は戦争災害に対しては結果責任に基づく国家補償の問題が生じる、とも明言しています。なぜ矛盾するようなことを言ったか。あまりにもひどい原爆被害に政府と国会が何もしないことへの裁判官の怒りが表れたと私は見ています。
―原爆以外の空襲なども同じではないでしょうか。
その通りです。被爆者は一定に救済があるのに他の戦災にはありません。戦争被害は国民が等しく受忍しなくてはならないという「受忍論」が政府の立場ですが、判決が戦争被害全体の救済の必要性を展開したことに注目します。
―今に積み残された論点が原爆裁判から読み取れます。とりわけ国の姿勢です。
被告(国)は原爆投下は国際法違反に当たらないと主張しました。しかし投下直後には国際法違反だと米国に抗議し、非人道兵器の廃棄を要求しています。まさに手のひら返しです。しかも原爆投下が自国民の被害を減らしたとまで裁判で言っています。米国の核とドルに依存してこの国を進める考え方になっていたのです。日米同盟の拡大核抑止に「核共有」。このところの動きを見ると当時の主張が一貫して続くどころか悪くなっています。核兵器のない世界を目指すと言いつつ核の傘に依存するのは詭弁(きべん)です。
―貴重な裁判資料は公開しているのですね。
私たちの協会のウェブサイトでほとんどの内容をアーカイブズ化しました。田中代表委員が受賞演説で言及したNPO法人「ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会」にいずれ引き継ぎ、後世に役立ててほしいと思います。
おおくぼ・けんいち
長野市生まれ。東北大卒。法務省勤務を経て1979年弁護士登録、埼玉弁護士会所属。94年に発足した日本反核法律家協会の活動に携わり、2020年に5代目会長に就任。日本弁護士連合会では憲法問題対策本部核兵器廃絶部会長を務める。著書に「憲法ルネサンス」「『核兵器廃絶』と憲法9条」など。
(2025年1月22日朝刊掲載)