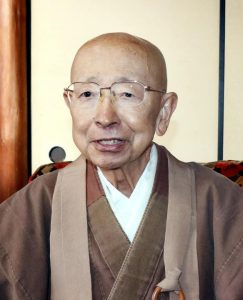平和の伝道 被爆80年に寄せて <上> 被爆2世の臨済宗妙心寺派前管長 小倉宗俊さん(76)=愛知県
25年1月27日
被爆80年の節目の年、平和のために宗教の立場からできることも大きいはずだ。大切な一年を決意新たに迎え、核兵器の愚かさにあらためて思いを致す宗教者や信徒の言葉を2回連載で紹介する。(山田祐)
iv style="font-size:106%;font-weight:bold;">核の非人道性 知らせる 僧侶として一個人として iv>
≪終戦後に生まれた小倉さんが、広島市で被爆した父秋夫さんの体験を初めて聞かされたのは高校生の頃だった。≫
父の左の首筋から腕にかけてケロイドが残っています。幼い頃から不思議に思っていましたが、その理由をはっきりと教えてくれたのは私が高校生になってからでした。過酷な体験であるがゆえに、口にするまでに相当な時間を必要としたのでしょう。
京都で生花店を営んでいた父は旧陸軍に召集され、1945年8月6日を広島で迎えました。原爆が投下された時にいた詳細な場所は聞かされていませんが、どこか屋外で会議をしていたそうです。父の後ろ側から光が襲ってきました。前方に並んでいた仲間たちはそれを正面から受けました。大勢が亡くなったそうです。
終戦後に京都に戻ってからのことも話してくれました。病院に行っても医師は治療法を知らない。世界で初めての核兵器による攻撃なのだから当然ですよね。施された治療は塩水に漬けるだけ。なかなか治らず苦労したようです。
仏教に当てはめて考えるとこうなります。言葉にできないほどの苦しみに向き合えるだけの己をどうやってつくっていくか―。しかし被爆の惨状を経験した心の痛みは、宗教では測れないものであったと思っています。
父は幸い、103歳になった今も施設で元気に過ごしてくれています。言葉に尽くせないほどの苦しみに耐えられるだけの精神力を育ててきたことに敬服しています。
≪2018年から6年間、臨済宗の最大宗派である妙心寺派の管長を務めた小倉さん。核兵器廃絶への思いを常に抱いてきた。≫
父の被爆体験を聞いても、すぐには自分ごとととらえることはできませんでした。向き合うようになったのは30歳を過ぎた頃からです。被爆2世の健康診断の受診を勧める通知を国から受け取ったのがきっかけでした。初めて「私も当事者なんだ」と思ったんです。
仏教徒として一番大切にしなくてはいけないのは平和だと理解していましたが、核兵器の非人道性を知らせることも大きな務めだと思うようになりました。年齢を重ねて妙心寺派管長という立場になったのも大切なご縁だったのだと思います。
戦争や核兵器の愚かさはみんな知っているはずなのになぜなくならないのか。自分のことを分かったつもりになるだけで、他人のことを理解しようとしないからでしょう。
被爆から長い月日がたち、日本国内でも原爆の恐ろしさの実感が薄れているように思えます。そんな中で昨年末、日本被団協がノーベル平和賞を受賞したのは本当に大きかった。私自身も「(核兵器廃絶に向けて)もっとしっかりせえ」と警鐘を鳴らしていただいたような感覚です。
父のように心に深い傷を負い、語れないままでいる方も多くいるでしょう。身をもって体験した人の言葉は重い。父が断片的に語ってくれた経験でさえも、世界に向けた警鐘になります。僧侶として一個人として、原爆の恐ろしさを語り継いでいかなければいけないと思っています。
≪欧州や中東の紛争で核の威嚇も相次ぐ中、僧侶としての役割を考え続けている。≫
禅宗は「己をいかに磨くか」に懸けるものです。その基軸は大切にしつつも、修行の成果を世間に返さなければいけないと私は考えます。修行を通して行き着く根本にあるのが「和」です。それを実現するために、各寺院も力をつけなくてはいけません。
禅宗では坐禅(ざぜん)によって己を見つけようとします。浄土真宗の門徒さんなら南無阿弥陀仏のお念仏でしょう。南無阿弥陀仏の6文字に全てを懸ける。自己中心的な思いをなくして、他者とともに一生懸命生きていく―。宗派は違っても目指すところは同じなんです。
己を磨き、他者とともにある自分をつくっていく。そこに湧き出るものが平和でないわけがありません。
今は愛知県犬山市の自坊に隠居の身でいますが、するべきことは管長時代と何にも変わりません。身近な人、目の前の方々に一つ一つ、平和のありがたさを説いていくということしかありません。多くの人と会う機会を持ち続けていきたいと思っています。
(2025年1月27日朝刊掲載)
≪終戦後に生まれた小倉さんが、広島市で被爆した父秋夫さんの体験を初めて聞かされたのは高校生の頃だった。≫
父の左の首筋から腕にかけてケロイドが残っています。幼い頃から不思議に思っていましたが、その理由をはっきりと教えてくれたのは私が高校生になってからでした。過酷な体験であるがゆえに、口にするまでに相当な時間を必要としたのでしょう。
京都で生花店を営んでいた父は旧陸軍に召集され、1945年8月6日を広島で迎えました。原爆が投下された時にいた詳細な場所は聞かされていませんが、どこか屋外で会議をしていたそうです。父の後ろ側から光が襲ってきました。前方に並んでいた仲間たちはそれを正面から受けました。大勢が亡くなったそうです。
終戦後に京都に戻ってからのことも話してくれました。病院に行っても医師は治療法を知らない。世界で初めての核兵器による攻撃なのだから当然ですよね。施された治療は塩水に漬けるだけ。なかなか治らず苦労したようです。
仏教に当てはめて考えるとこうなります。言葉にできないほどの苦しみに向き合えるだけの己をどうやってつくっていくか―。しかし被爆の惨状を経験した心の痛みは、宗教では測れないものであったと思っています。
父は幸い、103歳になった今も施設で元気に過ごしてくれています。言葉に尽くせないほどの苦しみに耐えられるだけの精神力を育ててきたことに敬服しています。
≪2018年から6年間、臨済宗の最大宗派である妙心寺派の管長を務めた小倉さん。核兵器廃絶への思いを常に抱いてきた。≫
父の被爆体験を聞いても、すぐには自分ごとととらえることはできませんでした。向き合うようになったのは30歳を過ぎた頃からです。被爆2世の健康診断の受診を勧める通知を国から受け取ったのがきっかけでした。初めて「私も当事者なんだ」と思ったんです。
仏教徒として一番大切にしなくてはいけないのは平和だと理解していましたが、核兵器の非人道性を知らせることも大きな務めだと思うようになりました。年齢を重ねて妙心寺派管長という立場になったのも大切なご縁だったのだと思います。
戦争や核兵器の愚かさはみんな知っているはずなのになぜなくならないのか。自分のことを分かったつもりになるだけで、他人のことを理解しようとしないからでしょう。
被爆から長い月日がたち、日本国内でも原爆の恐ろしさの実感が薄れているように思えます。そんな中で昨年末、日本被団協がノーベル平和賞を受賞したのは本当に大きかった。私自身も「(核兵器廃絶に向けて)もっとしっかりせえ」と警鐘を鳴らしていただいたような感覚です。
父のように心に深い傷を負い、語れないままでいる方も多くいるでしょう。身をもって体験した人の言葉は重い。父が断片的に語ってくれた経験でさえも、世界に向けた警鐘になります。僧侶として一個人として、原爆の恐ろしさを語り継いでいかなければいけないと思っています。
≪欧州や中東の紛争で核の威嚇も相次ぐ中、僧侶としての役割を考え続けている。≫
禅宗は「己をいかに磨くか」に懸けるものです。その基軸は大切にしつつも、修行の成果を世間に返さなければいけないと私は考えます。修行を通して行き着く根本にあるのが「和」です。それを実現するために、各寺院も力をつけなくてはいけません。
禅宗では坐禅(ざぜん)によって己を見つけようとします。浄土真宗の門徒さんなら南無阿弥陀仏のお念仏でしょう。南無阿弥陀仏の6文字に全てを懸ける。自己中心的な思いをなくして、他者とともに一生懸命生きていく―。宗派は違っても目指すところは同じなんです。
己を磨き、他者とともにある自分をつくっていく。そこに湧き出るものが平和でないわけがありません。
今は愛知県犬山市の自坊に隠居の身でいますが、するべきことは管長時代と何にも変わりません。身近な人、目の前の方々に一つ一つ、平和のありがたさを説いていくということしかありません。多くの人と会う機会を持ち続けていきたいと思っています。
(2025年1月27日朝刊掲載)