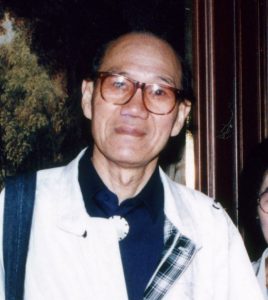[ヒロシマドキュメント 被爆80年] 1974年6月 「原爆の絵」募集開始
25年4月23日
惨禍を伝える2225枚届く
1974年6月。被爆の記憶を描いた「原爆の絵」を市民から募るキャンペーンが始まった。NHK中国本部(現広島放送局)が企画。被爆から30年が迫り、「体験の風化」がいわれる中、ローカル番組やニュースで呼びかけると、脳裏に刻む惨禍の光景が寄せられた。
19歳で被爆した高蔵信子(あきこ)さん(2020年に94歳で死去)は2枚を描いた。当時高校生だった長男浩亮さん(67)=広島市安佐北区=は、母が自宅の居間で絵筆を握る姿を覚えている。家族に体験をあまり語らなかったといい「生き残った罪悪感を抱えているようでした」と振り返る。
生前の証言などによれば、芸備銀行(現広島銀行)に勤めていた高蔵さんは45年8月6日、紙屋町(現中区)の本店にいた。爆心地から約260メートル東。光った途端に体を床にたたきつけられた。
「黒い雨」飲む
失った意識を同僚の叫び声で取り戻し、外へ。街は猛火に包まれ、耐えがたい熱さを感じた。雨が降り、少しでものどを潤そうと空に向けて口を開いた。放射性降下物を含む「黒い雨」とは知るよしもなかった。
逃げる道すがらには、倒れた遺体の中の30歳前後の男性の指に目を奪われた。青い炎を出して先から焼け落ち、薄墨色の液体が手のひらを伝って流れ落ちていた。「かつてはこの手で愛児を抱き、本の頁(ページ)もめくられたであろう事を思いますと、今もなお深い悲しみで胸が一杯になります」(10年刊「語りつごう あの日 あの頃」収録)
原爆のさく裂時に爆心地から500メートル以内にいた人はほとんど助からず、広島大などの「爆心地復元調査」の過程で確認された72年時点の生存者は78人だった。高蔵さんは戦後、報恩寺(安佐北区)の坊守となり、運営する保育園で園児の成長を見守った。
雨に口を開く自身と、燃える指を水彩画に描くと、証言活動を始め、80歳過ぎまで続けた。浩亮さんは「平和の尊さを伝える使命を感じていたのでしょう」と語る。
キャンペーンは、小林岩吉さん(91年に93歳で死去)が妻子を捜し歩いた市内の惨状を描いた絵を、74年5月にNHKに持ち込んだのがきっかけ。同様に家族を失った悲しみを絵に込める市民たちがいた。
弟の最期描く
山下正人さん(95年に70歳で死去)は2歳下の弟伍(あつむ)さんの最期を水彩画に描いた。建物疎開の作業中に被爆後、鼻血や脱毛に襲われ、血を吐き、苦しみながら8月31日に逝った。原爆放射線の恐ろしさをありありと示し、長女米又理恵さん(69)=西区=は「言葉では表せないけど、絵ならできると思ったのでは」と推し量る。
絵は75年にかけて758人から2225枚が寄せられた。02年にもNHK、原爆資料館、中国新聞社などが呼びかけ1338枚が集まった。これらを含め資料館が計約5千枚を所蔵。高蔵さん、山下さんの絵は常設展示している。(山下美波)
(2025年4月23日朝刊掲載)