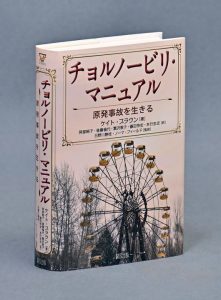『書評』 チョルノービリ・マニュアル ケイト・ブラウン著 阿部純子・後藤倫代・繁沢敦子・藤田怜史・本行忠志訳/日野川静枝・ノーマ・フィールド監訳
25年8月24日
原発事故の影響と教訓
タイトルの「チョルノービリ・マニュアル」は1986年8月、旧ソ連のウクライナ保健省が「親愛なる同志諸君」に宛て、配ったパンフレットを指すのだという。同志諸君とは、同年4月のチョルノービリ(チェルノブイリ)原発事故の被曝(ひばく)地域の住民である。
マニュアルは自信たっぷりこう呼びかけたそうだ。「村内に居住し働くことで被害を被ることはない」。ところが読み進めると「次の指示に沿って行動して下さい」と続く。木の実とキノコは摂取しない、子どもは森に立ち入らない、地元産の肉や牛乳は取らない…。
この矛盾は何なのか。科学史家である著者は30年後の現地を訪ね、事故処理に携わった兵士や放射能汚染地域の住民に聞き取り調査し、公文書など多くの資料を掘り起こす。原発事故の放射線影響調査や医学の知見、政治利用の過程をたどる。「終わりのない大惨事から結論を導き出すのは難しい」としつつ、続く健康影響や環境破壊、得られる教訓をつまびらかにしたのが本書である。
見えてくるのは、絶対安全といわれる技術にも失敗があること。原子炉の多くは都会から遠く、経済的に行き詰まった地域に立っていること。事故が起きても、政治は安全性を強調し住民らの怒りをなだめて納得させること。さらに情報開示の不十分さと社会を覆う冷笑主義が、それらを不可視化する現実だ。
読んでいると不意に広島・長崎や福島が二重写しになる。政治が、人数や金額といった数字を人命とてんびんにかけ、見えない放射線を恐怖するか受け入れるかで被害者を分断し、自己責任にすり替えていく展開である。著者は日本の福島第1原発事故後の対応も「国民の健康と安全より国の生産性とプライドを優先した」と断じる。
そしてそうした姿勢は核兵器開発と表裏一体であり、さらなるヒバクシャを生み続けたと突く。核時代の地球に生きる一人として、背筋が伸びる一冊である。(森田裕美・論説委員)
緑風出版・4620円
(2025年8月24日朝刊掲載)