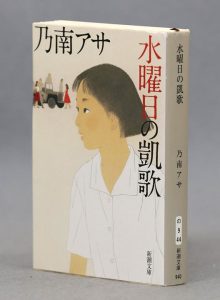[A Book for Peace 森田裕美 この一冊] 「水曜日の凱歌」 乃南アサ著(新潮文庫)
25年9月1日
犠牲強いる社会の酷薄
日本では8月15日を「終戦の日」と呼ぶ。1945年同日以降を「戦後」としたりもするが、この日を境に突如平和が訪れたわけではない。敗戦の混乱の中、人々は怒りや惨めさを抱え、生きるためにもがいていた。
本書は、14歳の少女鈴子の視点から敗戦後の半年余りを描いた長編小説である。題材は、進駐軍向け慰安所を運営した特殊慰安施設協会(RAA)。当時の内務省の指令で各地につくられた組織である。「一般婦女子を守るため」の「防波堤」として「女事務員募集」などと集められた女性が、進駐軍兵士の性の相手をさせられた。そんな負の歴史に正面から向き合う。
物語は、空襲で「がらんどう」になった東京から始まる。戦前は裕福だった鈴子も家を失い、母と女二人きり。父の友人「おじさま」に頼って生きるしかない。英語ができる母はやがておじさまのつてでRAAの通訳として働くことになったが…。
誰もが「生き延びるため」。だが鈴子は割り切れない。搾取される女の人を目の当たりにし胸を痛める。RAAに間接的であれ協力する母と、そのおかげで食べている自身の相反性にも苦しむ。
結局RAAは数カ月後、進駐軍によって閉鎖させられ、女性たちは放り出される。鈴子の目を通して描かれるのは、権力を持つ者が遂行した戦争で、立場が弱い人、とりわけ女性が犠牲を強いられる社会の酷薄だ。
物語の最後は46年4月の水曜日。婦人参政権が認められ、戦後初の総選挙が行われた日である。タイトルに込められた意味が明らかになるラストはすがすがしい。
戦後80年。不可視化され忘却されてきた歴史の断面に光を当て、教訓を学ぶ機会としたい。
これも!
①平井和子著「占領下の女性たち」(岩波書店)
②村上勝彦著「進駐軍向け特殊慰安所RAA」(ちくま新書)
③芝田英昭著「占領期の性暴力」(新日本出版社)
(2025年9月1日朝刊掲載)