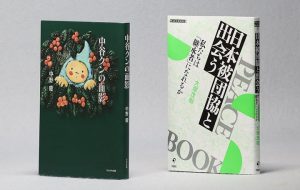被爆者の体験 どう向き合う 元編集者で著述家 大塚さん2冊刊行 運動や継承「多様なアプローチで」
25年9月22日
日本被団協の初代事務局長・故藤居平一氏の評伝などを執筆してきた、元編集者で著述家の大塚茂樹さん(67)=写真・川崎市=が戦後80年の今夏、被爆者運動や記憶の継承について考える2冊を刊行した。
「日本被団協と出会う」(旬報社)は、昨年ノーベル平和賞を受けた日本被団協についての解説書の趣である。田中熙巳(てるみ)代表委員のノルウェー・オスロでの受賞スピーチに始まり、被爆者の実情や運動の歩み、訴えなどを、基本から解きほぐした。
被爆者一人一人は身をもって体験したそれぞれの「地獄」は語れても、原爆被害の全体像を語るのは困難であることなどに触れ、体験のない世代が被爆者の語りにどう向き合うか、どう継承するかも鋭く問いかける。
もう1冊は、大塚さんがフィクションを書くときの筆名、中野慶名義の小説で「中谷クンの面影」(かもがわ出版)。主人公の66歳の女性が、かつての同級生が著した児童書を通じ、被爆者の人生に意識を向けていく物語だ。本の中で主人公が別の本を読むという入れ子のようなユニークな構成になっている。
主人公が読むのは、四半世紀前に刊行された中野慶著「やんばる君」。アトピーに悩む少年が広島を訪れ、被爆者からケロイドの痕がかゆいと聞いたことから自らの肌感覚を重ね、被爆者の体験に分け入っていくストーリーだ。主人公はかゆみという接点から原爆に迫った同級生を通じ、被爆者の人生に興味を抱く。
「継承というと若い世代に光が当たりがちだが、戦後十数年たって生まれてきた私たちの世代はどうか」と大塚さん。そんな問題意識が執筆の背景にあったという。
東京育ちの大塚さんは被爆地に縁はない。20代になって原爆や被爆者の問題に関心を持ち、自分なりに学び考えてきた。他の著作に絵本「新井貴浩物語」(南々社)もある大塚さんは「遠くにいながら童心で広島に触れる本に関わったことも、今につながっている」と振り返る。
ノーベル平和賞授賞式に合わせ、オスロでも取材した大塚さん。「被爆者の体験や思いを血肉化するのは難しい。でも、どんなに距離があってもいろいろなアプローチで接近はできる。広島や原爆に接点のない読者にも届くといい」と思いを込める。(森田裕美)
(2025年9月22日朝刊掲載)
「日本被団協と出会う」(旬報社)は、昨年ノーベル平和賞を受けた日本被団協についての解説書の趣である。田中熙巳(てるみ)代表委員のノルウェー・オスロでの受賞スピーチに始まり、被爆者の実情や運動の歩み、訴えなどを、基本から解きほぐした。
被爆者一人一人は身をもって体験したそれぞれの「地獄」は語れても、原爆被害の全体像を語るのは困難であることなどに触れ、体験のない世代が被爆者の語りにどう向き合うか、どう継承するかも鋭く問いかける。
もう1冊は、大塚さんがフィクションを書くときの筆名、中野慶名義の小説で「中谷クンの面影」(かもがわ出版)。主人公の66歳の女性が、かつての同級生が著した児童書を通じ、被爆者の人生に意識を向けていく物語だ。本の中で主人公が別の本を読むという入れ子のようなユニークな構成になっている。
主人公が読むのは、四半世紀前に刊行された中野慶著「やんばる君」。アトピーに悩む少年が広島を訪れ、被爆者からケロイドの痕がかゆいと聞いたことから自らの肌感覚を重ね、被爆者の体験に分け入っていくストーリーだ。主人公はかゆみという接点から原爆に迫った同級生を通じ、被爆者の人生に興味を抱く。
「継承というと若い世代に光が当たりがちだが、戦後十数年たって生まれてきた私たちの世代はどうか」と大塚さん。そんな問題意識が執筆の背景にあったという。
東京育ちの大塚さんは被爆地に縁はない。20代になって原爆や被爆者の問題に関心を持ち、自分なりに学び考えてきた。他の著作に絵本「新井貴浩物語」(南々社)もある大塚さんは「遠くにいながら童心で広島に触れる本に関わったことも、今につながっている」と振り返る。
ノーベル平和賞授賞式に合わせ、オスロでも取材した大塚さん。「被爆者の体験や思いを血肉化するのは難しい。でも、どんなに距離があってもいろいろなアプローチで接近はできる。広島や原爆に接点のない読者にも届くといい」と思いを込める。(森田裕美)
(2025年9月22日朝刊掲載)