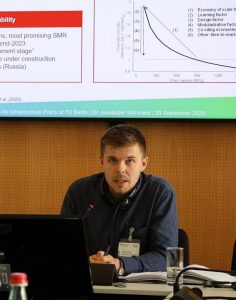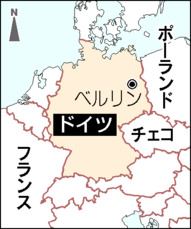脱原発と脱炭素両立模索 ドイツ政府招待 エネルギー事情取材
25年10月17日
欧州最大の経済大国ドイツが、全ての原発を止め、再生可能エネルギーの導入を拡大している。風力や太陽光で発電する設備を増やし、総発電量に占める再エネの比率は約6割に上る。一方、電気代は主要国の中でも高く、産業界は懸念を募らせる。ドイツ政府の招きで9月下旬から10月上旬にかけて現地を訪ね、脱原発と脱炭素の両立を目指す現状と課題を見た。(小川満久)
「(世界的に普及している)軽水炉のコストは他の発電技術より高い」。ドイツ経済・エネルギー省で取材に応じたベルリン工科大のアレクサンダー・ヴィマース博士研究員(核エネルギー)は、そう主張した。関連施設や放射性廃棄物の長期にわたる安全管理、建設費の高騰などを挙げ、原発のコスト面での優位性に疑問を投げかける。
ドイツ政府が脱原発を決めたのは、東京電力福島第1原発事故から3カ月後の2011年6月。当時は17基の原発があり、電力供給の約2割を担っていた。しかし、安全が担保されないとして、再エネを拡大しながら段階的に原発の運転を止める方向にかじを切る。23年4月に最後の3基が停止した。
脱原発の完了から2年半が過ぎた今、高い電気料金が課題となっている。9月の卸電力価格は1メガワット時当たり84ユーロ(約1万5千円)で、原発を積極的に使うフランスの2・4倍になった。原因は複合的で、22年のロシアによるウクライナ侵攻でロシア産の天然ガスの供給が途絶え、火力発電に使う天然ガスの調達コストが、かつてより高まった面もある。
燃料を使わない風力や太陽光由来の再エネが拡大すれば、電気代の低下も見込まれる。だが、ドイツ産業界の関係者は「競合国に比べて電気代がかなり高い。電気料金で産業の競争力が妨げられてはならない」と訴える。電力の安定供給が確保されるべきだとする考えも示す。
日本は福島第1原発の事故後に掲げた「原発依存度低減」から「原発を最大限活用する」方針に転換し、ドイツとは真逆の道を歩む。エネルギー基本計画で示す40年度の電源構成目標は、原子力が2割程度、再エネが4~5割。中国地方では中国電力が昨年12月に島根原発2号機(松江市)を約13年ぶりに再稼働した。30年度までに新設の3号機も稼働する予定。中電は30年度以降に原子力の比率を2~3割とする方針だ。
ベルリンに拠点を置くスタートアップ(新興企業)「STOFF2」のオフィス。高さ4メートル、幅5メートル、奥行き1・5メートルの試作機が存在感を放つ。余った再エネ電力で稼働すれば、生産時にCO₂を出さない「グリーン水素」を安く生み出せるという。
試作機は蓄電池のような仕組みだ。電気を流すと、亜鉛イオンを含む溶液から亜鉛を生成し、エネルギーをためる。放電する際に水素を生み出す。セバスチャン・シップ社長は「水素生産とエネルギー貯蔵の技術を組みわせた画期的な装置」と強調する。
再エネは天候で出力が変動するのがネックだ。余った再エネの電気でグリーン水素を生産し、燃料に活用できれば、トータルで再エネの出力拡大へ道が開ける。同社はドイツを含む欧州で需要が見込めるとして、来年にもエネルギー事業者などに向けて発売する。
ベルリン南部の再開発エリアでは、新設した複数のデータセンターの廃熱を近くの住宅に暖房の熱源として供給する計画も進んでいた。ヒートポンプを組み合わせ、27年以降に5千戸以上に届ける。
複数の企業と共同で事業を進めるベルリンのガス系列会社のGASAGソリューションプラスは「廃熱を活用するドイツで最大級のプロジェクト」と説明する。天然ガスなど従来の化石燃料からの転換を進め、住環境の脱炭素に取り組む。
1990年の東西ドイツ統一から35年の節目を翌日に控えた10月2日。冷戦時代に東西対立を象徴した「ベルリンの壁」の跡を訪れた。近くにそびえるブランデンブルク門は、優しい光に照らされていた。この照明を含め、ドイツの電力を支えているのが再エネだ。
24年の総発電量に占める比率は59・4%と前年より3・4ポイント上がった。内訳は、洋上を含む風力が31・5%と最も多く、太陽光13・8%、バイオマス6・5%などが続く。4割程度を占める火力発電は、石炭の割合を減らして天然ガスを増やすなど、二酸化炭素(CO₂)の削減も進む。
ただ、国内だけで電力を賄っているわけではない。欧州に広がる送配電網を使い、23年には電力の輸入総量が輸出総量を21年ぶりに上回った。24年はさらに輸入総量が増えている。輸入電力には原発由来も含まれる。
国内の送電網の拡充も課題だ。風力発電所は主にドイツ北部に集中するが、大規模工場などが集まる南部に十分な電力を送るための増強が遅れているという。世界自然保護基金(WWF)ドイツのビビアン・ラダッツ気候・エネルギー担当ディレクターは「整備に対する住民訴訟が頻発し、各州の規制も妨げになっている」と説明する。
日本では、中国地方と九州を結ぶ送電線などの増強が計画されている。天候に左右されやすい再エネ電力の比率が高まる中、需給バランスをどう取り、脱炭素電力を求める消費地に届けるか。送電網の整備は両国共通の課題になっている。
中国地方の未来 考えるヒントに
「福島第1原発の事故があったのに、なぜ日本は原発に回帰したのか」。現地で何度か聞かれた質問だ。ドイツでは原発の安全性に対する懐疑論が想像以上に根強かった。福島での事故の影響を踏まえ、日本が改めて重く受け止めるべき問いかけだろう。
一方で、再エネの導入拡大については、課題も含めて参考にするべき点は多い。送電網の増強は、中国地方を含めた日本で今後さらにクローズアップされるだろう。余った再エネの電力を他のエリアに融通すれば、無駄なく活用できる。電力の需給バランスを維持し、大規模停電を防ぐ効果も見込める。
自動車産業など製造業が盛んな点で日本と似通うドイツ。脱原発や脱炭素を進めながら、国際的な産業競争力をどう高めていくのか。中国地方の産業やエネルギーシステムの未来を考えるヒントにもなるだけに、その動向に注目していきたい。
(2025年10月17日朝刊掲載)
全17基停止後 電気代高く産業界から懸念
「(世界的に普及している)軽水炉のコストは他の発電技術より高い」。ドイツ経済・エネルギー省で取材に応じたベルリン工科大のアレクサンダー・ヴィマース博士研究員(核エネルギー)は、そう主張した。関連施設や放射性廃棄物の長期にわたる安全管理、建設費の高騰などを挙げ、原発のコスト面での優位性に疑問を投げかける。
ドイツ政府が脱原発を決めたのは、東京電力福島第1原発事故から3カ月後の2011年6月。当時は17基の原発があり、電力供給の約2割を担っていた。しかし、安全が担保されないとして、再エネを拡大しながら段階的に原発の運転を止める方向にかじを切る。23年4月に最後の3基が停止した。
脱原発の完了から2年半が過ぎた今、高い電気料金が課題となっている。9月の卸電力価格は1メガワット時当たり84ユーロ(約1万5千円)で、原発を積極的に使うフランスの2・4倍になった。原因は複合的で、22年のロシアによるウクライナ侵攻でロシア産の天然ガスの供給が途絶え、火力発電に使う天然ガスの調達コストが、かつてより高まった面もある。
燃料を使わない風力や太陽光由来の再エネが拡大すれば、電気代の低下も見込まれる。だが、ドイツ産業界の関係者は「競合国に比べて電気代がかなり高い。電気料金で産業の競争力が妨げられてはならない」と訴える。電力の安定供給が確保されるべきだとする考えも示す。
日本は福島第1原発の事故後に掲げた「原発依存度低減」から「原発を最大限活用する」方針に転換し、ドイツとは真逆の道を歩む。エネルギー基本計画で示す40年度の電源構成目標は、原子力が2割程度、再エネが4~5割。中国地方では中国電力が昨年12月に島根原発2号機(松江市)を約13年ぶりに再稼働した。30年度までに新設の3号機も稼働する予定。中電は30年度以降に原子力の比率を2~3割とする方針だ。
期待の新技術 グリーン水素安く 暖房に廃熱を供給
ベルリンに拠点を置くスタートアップ(新興企業)「STOFF2」のオフィス。高さ4メートル、幅5メートル、奥行き1・5メートルの試作機が存在感を放つ。余った再エネ電力で稼働すれば、生産時にCO₂を出さない「グリーン水素」を安く生み出せるという。
試作機は蓄電池のような仕組みだ。電気を流すと、亜鉛イオンを含む溶液から亜鉛を生成し、エネルギーをためる。放電する際に水素を生み出す。セバスチャン・シップ社長は「水素生産とエネルギー貯蔵の技術を組みわせた画期的な装置」と強調する。
再エネは天候で出力が変動するのがネックだ。余った再エネの電気でグリーン水素を生産し、燃料に活用できれば、トータルで再エネの出力拡大へ道が開ける。同社はドイツを含む欧州で需要が見込めるとして、来年にもエネルギー事業者などに向けて発売する。
ベルリン南部の再開発エリアでは、新設した複数のデータセンターの廃熱を近くの住宅に暖房の熱源として供給する計画も進んでいた。ヒートポンプを組み合わせ、27年以降に5千戸以上に届ける。
複数の企業と共同で事業を進めるベルリンのガス系列会社のGASAGソリューションプラスは「廃熱を活用するドイツで最大級のプロジェクト」と説明する。天然ガスなど従来の化石燃料からの転換を進め、住環境の脱炭素に取り組む。
再エネ6割に 送電網の拡充必要 電力輸入も
1990年の東西ドイツ統一から35年の節目を翌日に控えた10月2日。冷戦時代に東西対立を象徴した「ベルリンの壁」の跡を訪れた。近くにそびえるブランデンブルク門は、優しい光に照らされていた。この照明を含め、ドイツの電力を支えているのが再エネだ。
24年の総発電量に占める比率は59・4%と前年より3・4ポイント上がった。内訳は、洋上を含む風力が31・5%と最も多く、太陽光13・8%、バイオマス6・5%などが続く。4割程度を占める火力発電は、石炭の割合を減らして天然ガスを増やすなど、二酸化炭素(CO₂)の削減も進む。
ただ、国内だけで電力を賄っているわけではない。欧州に広がる送配電網を使い、23年には電力の輸入総量が輸出総量を21年ぶりに上回った。24年はさらに輸入総量が増えている。輸入電力には原発由来も含まれる。
国内の送電網の拡充も課題だ。風力発電所は主にドイツ北部に集中するが、大規模工場などが集まる南部に十分な電力を送るための増強が遅れているという。世界自然保護基金(WWF)ドイツのビビアン・ラダッツ気候・エネルギー担当ディレクターは「整備に対する住民訴訟が頻発し、各州の規制も妨げになっている」と説明する。
日本では、中国地方と九州を結ぶ送電線などの増強が計画されている。天候に左右されやすい再エネ電力の比率が高まる中、需給バランスをどう取り、脱炭素電力を求める消費地に届けるか。送電網の整備は両国共通の課題になっている。
記者の視点 小川満久
中国地方の未来 考えるヒントに
「福島第1原発の事故があったのに、なぜ日本は原発に回帰したのか」。現地で何度か聞かれた質問だ。ドイツでは原発の安全性に対する懐疑論が想像以上に根強かった。福島での事故の影響を踏まえ、日本が改めて重く受け止めるべき問いかけだろう。
一方で、再エネの導入拡大については、課題も含めて参考にするべき点は多い。送電網の増強は、中国地方を含めた日本で今後さらにクローズアップされるだろう。余った再エネの電力を他のエリアに融通すれば、無駄なく活用できる。電力の需給バランスを維持し、大規模停電を防ぐ効果も見込める。
自動車産業など製造業が盛んな点で日本と似通うドイツ。脱原発や脱炭素を進めながら、国際的な産業競争力をどう高めていくのか。中国地方の産業やエネルギーシステムの未来を考えるヒントにもなるだけに、その動向に注目していきたい。
(2025年10月17日朝刊掲載)