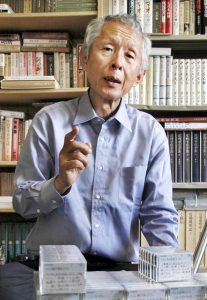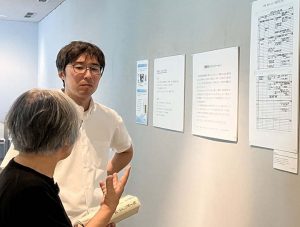[歩く 聞く 考える] 論説委員 森田裕美 伊藤明彦さんの「遺言」 被爆者の叫び伝える「共犯者」に
25年10月22日
被爆から80年を迎えたことし、ある故人に光が当たっている。千人にも及ぶ被爆者の肉声を録音し続けたことで知られる元長崎放送記者の伊藤明彦さん(2009年に72歳で死去)である。
8月には、伊藤さんをモデルにした本木雅弘さん主演のドラマ「八月の声を運ぶ男」をNHKが放映。長崎市の国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館は9月末まで伊藤さんの歩みをたどる特別展を開いた。過去の著作も注目されている。こうした動きを、生前の伊藤さんとわずかに接した一人として、感慨深く受け止めている。
没後16年。伊藤さんを知らない人、忘れている人も多いのではないか。伊藤さんは1936年東京で生まれ、父親の仕事で44年に長崎へ。45年8月9日は疎開先の山口県にいて直爆は免れたが、10日後、自宅に戻り入市被爆した。
長崎放送に勤めていた68年、被爆者の声の収録と長期的な保存を目的にラジオ番組を企画。初代担当になったが転勤となり、70年に退職して東京へ。70年代を中心に皿洗いや夜警などパート労働をしながら、退職金で買った録音機を携え、独自に収録を続けた。断られた人も含め、21都府県に2千人を訪ねたというから驚く。録音した音声はテープやCDにして全国の図書館や学校へ寄贈している。
かつて筆者が取材した伊藤さんは物静かだが眼光鋭く、いかにも近寄り難かった。その仕事ぶりには畏怖の念を抱いていたが、訃報を聞いてからは、ほとんど思い出すこともなくなっていた。
記憶をよみがえらせてくれたのは長崎市で出版社「編集室水平線」を営む編集者西浩孝さん(43)である。昨年から伊藤さんの著作を、新たな書籍シリーズ(全6巻)として世に送り出している。
昨年末、第1巻が職場に届き、一気に読んだ。収められているのは、伊藤さんがある男性との出会いを通して「被爆体験」とは何か根底から問いかけるノンフィクション「未来からの遺言」(80年)と、それを基にした「シナリオ被爆太郎伝説」(99年)である。
本書の中で、長崎での被爆体験とその後の苦難を語る男性は鮮烈な印象を残す。だが伊藤さんが調べていくと彼は当日長崎にいなかったことが分かる。彼の語りは作り話なのか―。伊藤さんは、このような「被爆太郎」ともいえる男性がいかに生まれたのか繰り返し考え、ある結論を見いだす。
伊藤さんが声を集める過程でどんな経験をし、どう考えたか。思索をつづった言葉に心揺さぶられた。語らない・語れない被爆者が存在すること、被爆者の語りが全て事実とは限らないこと、被爆体験を聞くことで被爆者でない者が原爆を追体験するような感覚…。被爆者取材を続けてきた一人として思い当たることも多かった。
西さんによる著作の復刊を通して、伊藤さんに出会い直している人は少なくないようだ。編集室水平線には情報提供や問い合わせを含め、大きな反響があるという。
ヒロシマ・フィールドワーク実行委員会代表の中川幹朗さん(67)もその一人。広島市内の学校へ寄贈された音声テープの所在をいくつか問い合わせて確認し、西さんに伝えた。伊藤さんの著書を読み、「本気」に心打たれた。
伊藤さんの姿は、尊敬するヒロシマの先人の姿にも重なるのだという。身元不明や引き取り手のない遺骨が納められた平和記念公園内の原爆供養塔に40年以上通い清掃を続けた故佐伯敏子さんや、原爆資料の収集分析に心血を注いだ故田原幻吉さんだ。
組織に寄りかからず、たった一人で原爆の不条理を告発し続け、無念の死者の尊厳を回復しようとした先人の姿を、私たちはいま一度思い返す必要があるのだろう。
東区で加納実紀代資料室サゴリを運営する高雄きくえさん(76)も「未来からの遺言」に心奪われた。伊藤さんをより深く知りたくて長崎に足を運び、西さんに話を聞いた。広島にいながらピンとこなかった被爆体験を伝えるという行為について考えさせられたと話す。「聞き、受け止めた側の身体をくぐり抜けた言葉が紡がれて初めて伝えるという行為は完成するのだと思った」
「被爆体験の風化」が危ぶまれ「継承」が叫ばれて久しい。だがその「被爆体験」とは何か、それをどう受け継ぐのか。私たちはどれだけ根源的に問うているだろう。言葉や形ばかりになっていないか。そうした問題を考え続ける姿勢こそ、伊藤さんが未来に残したかったことなのかもしれない。
伊藤さんは「未来からの遺言」の中で、被爆者の声を集める自身を「原子爆弾投下の犯罪行為を裁く歴史の公判廷維持に必要な、被害者の調書をとって歩く、よれよれのレインコートにどた靴をはいた刑事」に重ねていたと記す。さらに「被爆者の胸のうちにメラメラと燃え続ける悲しみ、怒り、叫びの炎」を人々の胸に燃え移らせる「放火犯になりたい」とも。西さんは巻末に寄せた一文で「〈共犯者〉になりたい」とつづる。
中川さんからの問い合わせをきっかけに、広島市内の高校では生徒たちが伊藤さんについて調べる動きも生まれていると聞く。「共犯者」は着実に増えている。
(2025年10月22日朝刊掲載)
8月には、伊藤さんをモデルにした本木雅弘さん主演のドラマ「八月の声を運ぶ男」をNHKが放映。長崎市の国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館は9月末まで伊藤さんの歩みをたどる特別展を開いた。過去の著作も注目されている。こうした動きを、生前の伊藤さんとわずかに接した一人として、感慨深く受け止めている。
没後16年。伊藤さんを知らない人、忘れている人も多いのではないか。伊藤さんは1936年東京で生まれ、父親の仕事で44年に長崎へ。45年8月9日は疎開先の山口県にいて直爆は免れたが、10日後、自宅に戻り入市被爆した。
長崎放送に勤めていた68年、被爆者の声の収録と長期的な保存を目的にラジオ番組を企画。初代担当になったが転勤となり、70年に退職して東京へ。70年代を中心に皿洗いや夜警などパート労働をしながら、退職金で買った録音機を携え、独自に収録を続けた。断られた人も含め、21都府県に2千人を訪ねたというから驚く。録音した音声はテープやCDにして全国の図書館や学校へ寄贈している。
かつて筆者が取材した伊藤さんは物静かだが眼光鋭く、いかにも近寄り難かった。その仕事ぶりには畏怖の念を抱いていたが、訃報を聞いてからは、ほとんど思い出すこともなくなっていた。
記憶をよみがえらせてくれたのは長崎市で出版社「編集室水平線」を営む編集者西浩孝さん(43)である。昨年から伊藤さんの著作を、新たな書籍シリーズ(全6巻)として世に送り出している。
昨年末、第1巻が職場に届き、一気に読んだ。収められているのは、伊藤さんがある男性との出会いを通して「被爆体験」とは何か根底から問いかけるノンフィクション「未来からの遺言」(80年)と、それを基にした「シナリオ被爆太郎伝説」(99年)である。
本書の中で、長崎での被爆体験とその後の苦難を語る男性は鮮烈な印象を残す。だが伊藤さんが調べていくと彼は当日長崎にいなかったことが分かる。彼の語りは作り話なのか―。伊藤さんは、このような「被爆太郎」ともいえる男性がいかに生まれたのか繰り返し考え、ある結論を見いだす。
伊藤さんが声を集める過程でどんな経験をし、どう考えたか。思索をつづった言葉に心揺さぶられた。語らない・語れない被爆者が存在すること、被爆者の語りが全て事実とは限らないこと、被爆体験を聞くことで被爆者でない者が原爆を追体験するような感覚…。被爆者取材を続けてきた一人として思い当たることも多かった。
西さんによる著作の復刊を通して、伊藤さんに出会い直している人は少なくないようだ。編集室水平線には情報提供や問い合わせを含め、大きな反響があるという。
ヒロシマ・フィールドワーク実行委員会代表の中川幹朗さん(67)もその一人。広島市内の学校へ寄贈された音声テープの所在をいくつか問い合わせて確認し、西さんに伝えた。伊藤さんの著書を読み、「本気」に心打たれた。
伊藤さんの姿は、尊敬するヒロシマの先人の姿にも重なるのだという。身元不明や引き取り手のない遺骨が納められた平和記念公園内の原爆供養塔に40年以上通い清掃を続けた故佐伯敏子さんや、原爆資料の収集分析に心血を注いだ故田原幻吉さんだ。
組織に寄りかからず、たった一人で原爆の不条理を告発し続け、無念の死者の尊厳を回復しようとした先人の姿を、私たちはいま一度思い返す必要があるのだろう。
東区で加納実紀代資料室サゴリを運営する高雄きくえさん(76)も「未来からの遺言」に心奪われた。伊藤さんをより深く知りたくて長崎に足を運び、西さんに話を聞いた。広島にいながらピンとこなかった被爆体験を伝えるという行為について考えさせられたと話す。「聞き、受け止めた側の身体をくぐり抜けた言葉が紡がれて初めて伝えるという行為は完成するのだと思った」
「被爆体験の風化」が危ぶまれ「継承」が叫ばれて久しい。だがその「被爆体験」とは何か、それをどう受け継ぐのか。私たちはどれだけ根源的に問うているだろう。言葉や形ばかりになっていないか。そうした問題を考え続ける姿勢こそ、伊藤さんが未来に残したかったことなのかもしれない。
伊藤さんは「未来からの遺言」の中で、被爆者の声を集める自身を「原子爆弾投下の犯罪行為を裁く歴史の公判廷維持に必要な、被害者の調書をとって歩く、よれよれのレインコートにどた靴をはいた刑事」に重ねていたと記す。さらに「被爆者の胸のうちにメラメラと燃え続ける悲しみ、怒り、叫びの炎」を人々の胸に燃え移らせる「放火犯になりたい」とも。西さんは巻末に寄せた一文で「〈共犯者〉になりたい」とつづる。
中川さんからの問い合わせをきっかけに、広島市内の高校では生徒たちが伊藤さんについて調べる動きも生まれていると聞く。「共犯者」は着実に増えている。
(2025年10月22日朝刊掲載)