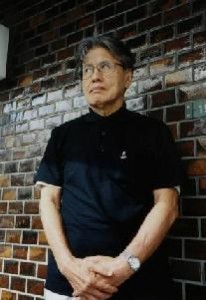原爆文学21世紀へ 後編 作品―そのとき・それから <1>
10年7月6日
■記者 梅原勝己
20世紀後半に誕生した原爆文学。科学技術の極北としての原爆に対し、文学は半世紀の間、どう対決し、どんな実りをもたらしたのか。横浜市の神奈川近代文学館では、「ヒロシマ・ナガサキ原爆文学展」が10月7日から開催される。21世紀に向けた検証が進む中で、広島に軸足を置いた作家たちは今、何を考えているのか。ヒロシマの表現について、その軌跡を振り返る。
後に「ヒロシマ・ノート」としてまとめられる大江健三郎のルポが雑誌「世界」で連載開始された1963年、深草獅子郎=本名・松坂義孝=は、広島の外から眺めているだけでは見えない、被爆者の心に潜む欲望を伝えたいと思った。「被爆者は死に直面するまで沈黙したがる、ということをね。自分の悲惨さをさらしたいと思ってはいないこと、毎年来る8月6日のために口を割らせようとするものを、圧力と感じている者がいることを知ってほしかったんだ」
その私信は、1965年に刊行されたとき、プロローグに引用され、大江はこうこたえる。<これは広島について沈黙する唯一の権利を持つ人々について書いた僕のエッセイに対する共感の言葉として書かれた手紙ではあるが…同時に広島の外部の人間である自分の文章全体に、鋭い批判のムチが加えられたことにも気付かざるをえない>
ただ、深草自身は大江のルポに全面的な共感を寄せてはいない。例えば<かれらは深甚な暗さを秘めた恐ろしい目をしている><彼女らの内心の深甚な不安はかわらない>と描写される被爆者。被爆したハイティーンの娘が結婚し出産したという事実に対し、<このような絶望的なほどの勇敢さ、それは人間の脆さと強靱さに、ともにかかわって、真に人間的だというべきであろうと思う>という反応。とりわけ、医学生であった深草が、医師であった父親を背負い救護活動に協力したという「威厳に満ちた被爆者」としてのエピソードについての違和感は強い。「私が背負ったことは事実だ。ただ、私が終始、威厳に満ちた行動をとっていたわけではない。状況におびえて逃げようとしたことも本当なんだ」
原民喜が「壊滅の序曲」で描いたような、どこにでもある家庭内の不協和音が深草一家にもあった。「父親の『威厳に満ちた行動』があったから、私の父親への確執が消えたわけではない。私は父親を背負ったそのときも、生き延びた戦後の生活でも反感を抱きつづけたんだ」
多くの原爆文学が、被爆体験と関係なく存在する、人の心の普遍的な葛藤(かっとう)を、「威厳に満ちた」描写や「ウラミ」に収れんする形容によって塗りつぶしてしまっていることに、不満を感じていた。それに対し深草は、こんな単純なプランを提起する。<たとえば、被爆して、ひととおりの悲惨な目にあった家族が、健康を回復し、人間として再生できたという物語はないものだろうか>(「雑記二章」歯車14号、1961年刊)
1955年の同人誌「歯車」創刊以来、中原中也や木下杢太郎などの論考を発表してきた深草にとって、「広島三文オペラ」は、これまでに残した唯一の小説。女性の性器内に残ったペンシルホルダーを取り出す手術を被爆者手帳で行ってくれと頼む患者、原爆孤老にペニスボーンを埋め込む手術を提案する医者…。ブレヒトの異化効果に学んだ、良識的には反発されるエピソードに満ちている。
「諧謔(かいぎゃく)ととられては心外なんだ。被爆者はみっともないことにかかわってはならないのか、世の中の片隅で恨み言をつぶやき続けていればいいのか、という思いを代弁する表現なのだから」
「歯車」が休刊して8年。文字通り「沈黙する被爆者」となった最近の深草の脳裏を去来するのは、こんな考えだ。「被爆者として死ぬのは、まっぴらだ。普通のへそ曲がりのジジイとして死ぬために、うまい抜け道はないものだろうか」(敬称略)
<メモ>
「広島三文オペラ」は、「中国新聞」朝刊1963年12月13日から翌年1月12日まで連載。同年4月に私家版としてまとめられた。男性性器が消失する流行病が発生する。広島のみで猛威をふるうため、残留放射能が去った後の土壌に染み込んだ「ウラミ」が、発症の要因と判断される。固有名詞を持たない医師や青年がとぼけた行動をするさまを、乾いた文体で描く。
深草獅子郎は1924年、広島市生まれ。爆心地から1.5キロの幟町で被爆。「秋墳鬼唄」(歯車9号、1959年刊)、「しらぬまに、秋」(同21号、1971年刊)などで、原爆や原爆文学に論及しているほか、ロバート・リフトンの評論「死の内の生命」で「医師作家」としてインタビューに応じている。広島市在住。
(2000年9月25日朝刊掲載)
深草獅子郎と「広島三文オペラ」 特別扱いに違和感 沈黙を守る被爆者
20世紀後半に誕生した原爆文学。科学技術の極北としての原爆に対し、文学は半世紀の間、どう対決し、どんな実りをもたらしたのか。横浜市の神奈川近代文学館では、「ヒロシマ・ナガサキ原爆文学展」が10月7日から開催される。21世紀に向けた検証が進む中で、広島に軸足を置いた作家たちは今、何を考えているのか。ヒロシマの表現について、その軌跡を振り返る。
後に「ヒロシマ・ノート」としてまとめられる大江健三郎のルポが雑誌「世界」で連載開始された1963年、深草獅子郎=本名・松坂義孝=は、広島の外から眺めているだけでは見えない、被爆者の心に潜む欲望を伝えたいと思った。「被爆者は死に直面するまで沈黙したがる、ということをね。自分の悲惨さをさらしたいと思ってはいないこと、毎年来る8月6日のために口を割らせようとするものを、圧力と感じている者がいることを知ってほしかったんだ」
その私信は、1965年に刊行されたとき、プロローグに引用され、大江はこうこたえる。<これは広島について沈黙する唯一の権利を持つ人々について書いた僕のエッセイに対する共感の言葉として書かれた手紙ではあるが…同時に広島の外部の人間である自分の文章全体に、鋭い批判のムチが加えられたことにも気付かざるをえない>
ただ、深草自身は大江のルポに全面的な共感を寄せてはいない。例えば<かれらは深甚な暗さを秘めた恐ろしい目をしている><彼女らの内心の深甚な不安はかわらない>と描写される被爆者。被爆したハイティーンの娘が結婚し出産したという事実に対し、<このような絶望的なほどの勇敢さ、それは人間の脆さと強靱さに、ともにかかわって、真に人間的だというべきであろうと思う>という反応。とりわけ、医学生であった深草が、医師であった父親を背負い救護活動に協力したという「威厳に満ちた被爆者」としてのエピソードについての違和感は強い。「私が背負ったことは事実だ。ただ、私が終始、威厳に満ちた行動をとっていたわけではない。状況におびえて逃げようとしたことも本当なんだ」
原民喜が「壊滅の序曲」で描いたような、どこにでもある家庭内の不協和音が深草一家にもあった。「父親の『威厳に満ちた行動』があったから、私の父親への確執が消えたわけではない。私は父親を背負ったそのときも、生き延びた戦後の生活でも反感を抱きつづけたんだ」
多くの原爆文学が、被爆体験と関係なく存在する、人の心の普遍的な葛藤(かっとう)を、「威厳に満ちた」描写や「ウラミ」に収れんする形容によって塗りつぶしてしまっていることに、不満を感じていた。それに対し深草は、こんな単純なプランを提起する。<たとえば、被爆して、ひととおりの悲惨な目にあった家族が、健康を回復し、人間として再生できたという物語はないものだろうか>(「雑記二章」歯車14号、1961年刊)
1955年の同人誌「歯車」創刊以来、中原中也や木下杢太郎などの論考を発表してきた深草にとって、「広島三文オペラ」は、これまでに残した唯一の小説。女性の性器内に残ったペンシルホルダーを取り出す手術を被爆者手帳で行ってくれと頼む患者、原爆孤老にペニスボーンを埋め込む手術を提案する医者…。ブレヒトの異化効果に学んだ、良識的には反発されるエピソードに満ちている。
「諧謔(かいぎゃく)ととられては心外なんだ。被爆者はみっともないことにかかわってはならないのか、世の中の片隅で恨み言をつぶやき続けていればいいのか、という思いを代弁する表現なのだから」
「歯車」が休刊して8年。文字通り「沈黙する被爆者」となった最近の深草の脳裏を去来するのは、こんな考えだ。「被爆者として死ぬのは、まっぴらだ。普通のへそ曲がりのジジイとして死ぬために、うまい抜け道はないものだろうか」(敬称略)
<メモ>
「広島三文オペラ」は、「中国新聞」朝刊1963年12月13日から翌年1月12日まで連載。同年4月に私家版としてまとめられた。男性性器が消失する流行病が発生する。広島のみで猛威をふるうため、残留放射能が去った後の土壌に染み込んだ「ウラミ」が、発症の要因と判断される。固有名詞を持たない医師や青年がとぼけた行動をするさまを、乾いた文体で描く。
深草獅子郎は1924年、広島市生まれ。爆心地から1.5キロの幟町で被爆。「秋墳鬼唄」(歯車9号、1959年刊)、「しらぬまに、秋」(同21号、1971年刊)などで、原爆や原爆文学に論及しているほか、ロバート・リフトンの評論「死の内の生命」で「医師作家」としてインタビューに応じている。広島市在住。
(2000年9月25日朝刊掲載)