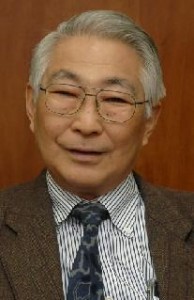福島第1原発事故 放射性物質 人体への影響は
11年3月25日
■記者 衣川圭
東京電力福島第1原発の事故で、農作物などから放射性物質が検出されている。生活の上で何に注意するべきなのか。放射線影響研究所(広島市南区)の大久保利晃理事長(71)に聞いた。
―茨城県のホウレンソウから基準値の27倍の放射性ヨウ素が検出されました。人体に影響はありますか。
汚染された野菜を1、2度食べたくらいでは影響はない。放射性物質は、洗ったり煮たりする過程でかなり減る。ただ体内に蓄積されると一定期間、放射線を出し続ける。放射線を外から浴びるのと対比してこれを「内部被曝(ひばく)」と呼んでいる。汚染された野菜は食べないにこしたことはない。
―どのくらい出続けるのですか。また注意すべき点は。
ヨウ素131の半減期(放射線の強さが半分に減る)は8日間と短いが、ストロンチウムなどは数十年と長く、骨などに蓄積すると白血病の原因になる。
ただ葉物野菜は国の出荷停止の指示で出回ることはないだろう。チェルノブイリ原発の事故では、食物連鎖によって家畜などに影響が出た。家畜や魚などの定期的なチェックは欠かせない。同じ産地の同じものを集中して食べないことは、リスク回避になる。
―年齢によって被曝の影響に違いはありますか。
ヨウ素が甲状腺に蓄積することで発症する甲状腺がんの危険性は小さい子どもほど高い。ヨウ素は成長期に多く取り込まれるからだ。また染色体が傷つきやすいのは細胞分裂時。細胞分裂が盛んな若い人ほど影響を受けやすい。広島の原爆でも若い被爆者ほどがんになりやすいというデータがある。
おおくぼ・としてる氏
慶応大医学部卒。産業医科大教授、同学長などを経て、2005年4月、放影研副理事長に就任。同年7月から現職。専門は環境医学。
(2011年3月23日朝刊掲載)
放影研・大久保理事長に聞く
東京電力福島第1原発の事故で、農作物などから放射性物質が検出されている。生活の上で何に注意するべきなのか。放射線影響研究所(広島市南区)の大久保利晃理事長(71)に聞いた。
―茨城県のホウレンソウから基準値の27倍の放射性ヨウ素が検出されました。人体に影響はありますか。
汚染された野菜を1、2度食べたくらいでは影響はない。放射性物質は、洗ったり煮たりする過程でかなり減る。ただ体内に蓄積されると一定期間、放射線を出し続ける。放射線を外から浴びるのと対比してこれを「内部被曝(ひばく)」と呼んでいる。汚染された野菜は食べないにこしたことはない。
―どのくらい出続けるのですか。また注意すべき点は。
ヨウ素131の半減期(放射線の強さが半分に減る)は8日間と短いが、ストロンチウムなどは数十年と長く、骨などに蓄積すると白血病の原因になる。
ただ葉物野菜は国の出荷停止の指示で出回ることはないだろう。チェルノブイリ原発の事故では、食物連鎖によって家畜などに影響が出た。家畜や魚などの定期的なチェックは欠かせない。同じ産地の同じものを集中して食べないことは、リスク回避になる。
―年齢によって被曝の影響に違いはありますか。
ヨウ素が甲状腺に蓄積することで発症する甲状腺がんの危険性は小さい子どもほど高い。ヨウ素は成長期に多く取り込まれるからだ。また染色体が傷つきやすいのは細胞分裂時。細胞分裂が盛んな若い人ほど影響を受けやすい。広島の原爆でも若い被爆者ほどがんになりやすいというデータがある。
おおくぼ・としてる氏
慶応大医学部卒。産業医科大教授、同学長などを経て、2005年4月、放影研副理事長に就任。同年7月から現職。専門は環境医学。
(2011年3月23日朝刊掲載)